- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
Ⅰ 東日本大震災の前後の時期
苦しみや重い不安や悲しみのただ中にいる人たちを支援する仏教者の活動が目立つようになっている。日本の仏教者による自殺予防活動はこうした活動のあり方の一つの様態として捉えることができる。苦しみや悲しみのただ中にいる人々への支援ということでは,東日本大震災の被災地での活動はそのよい例だ。そこで注目すべき働きを行ったのが,栗原市通大寺の金田諦應住職らによる傾聴喫茶カフェデモンクだ。このカフェデモンクは臨床宗教師の活動の場として大いに力を発揮した。
臨床宗教師の育成を提唱したのは,仙台と周辺地域で在宅の死の見取りの医療を続けてきた故岡部健医師である。臨床宗教師会の発足は2015年だが,岡部医師がその準備となる取り組みを進めていったのは2000年代のことだが,同じ時期に苦悩する人々への仏教者の新たな支援の取り組みも進んでいた。「無縁社会」などとよばれるように,社会の底辺に取り残されたり,行き場を失ってしまっているような人々が増えている。それを支える活動だ。磯村健太郎の『ルポ仏教,貧困・自殺に挑む』(磯村,2011)はよい導き手となる。
磯村の著書でも大きく取り上げられている,仏教者による自死自殺予防・自死遺族支援の活動を見ていこう。まず,取り上げたいのは,秋田県藤里町の「心といのちを考える会」の袴田俊英住職の活動だ。自殺が多い県として知られる秋田県の藤里町は人口3,600人ほど(2014年)の山村であるが,1989年からの10年間で31人,1999年からの10年間で25人の自殺者が出ていた。この数字ではあまり減っていないようだが,2004年からの5年間では7人と少なくなっている(藤里町・秋田大学医学部健康増進医学分野,2009)。
これについては,2002年から2004年に藤里町が取り組んだ「こころの健康づくり・自殺予防活動のモデル地区」プロジェクトが効果をもったと考えられている。この企てに保健師や社会福祉協議会とともに熱心に関わったのが,「心といのちを考える会」である。2000年2月に老夫婦の心中事件があったのが一つのきっかけとなって(『熊本日日新聞』2005年12月14日),有志21人によって同年10月に発足したが,その代表となったのが曹洞宗の袴田俊英住職だ。
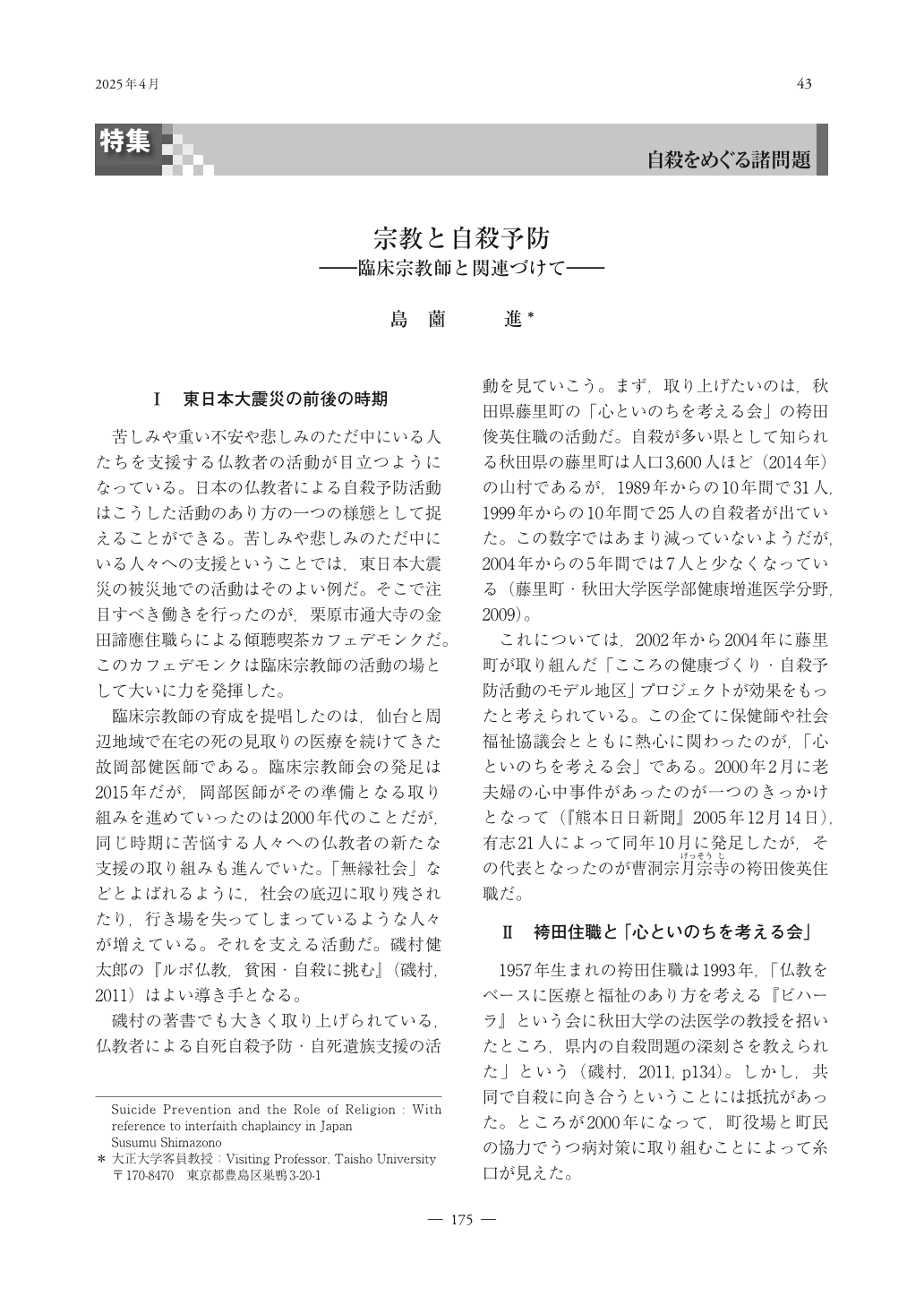
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


