- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I 始まりは被害者の訴え
民間による被害者支援は,飲酒運転によって家族を亡くしたある遺族の強い訴えが専門家を動かし,大学内に「犯罪被害相談室」を開設したところから始まった。その遺族は犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム(1991年)に聴衆として参加し,パネリストが「日本では被害者の声として(支援の)ニーズが出てこない」としたことを受け,ニーズが出てこないのではなく,被害者は孤立し我慢を強いられているのだとフロアから発言し,「どんな協力も惜しみませんから,(略)一歩だけでも踏み出してください」と精神的支援の必要性を訴えたのだった(「犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム(平成3年)における大久保惠美子さんの発言(要約)」)(警察庁,2024)。
1995年以降,各地で被害者支援団体が相次いで設立され,警察において「犯罪被害者対策要綱」が設置され,都道府県警察に被害者支援室が開設され始めたのもこの頃である(奥村,2019)。今では,都道府県に1カ所(北海道のみ2カ所)の被害者支援センター(以下,センター)があり,心の内を安心して話せる「電話相談」,訓練を受けた犯罪被害相談員が行う「面接相談」,警察や裁判所への付き添いや日常生活の手助けをする「直接的支援」などを提供している(センターによって支援内容は異なる)。48のセンターは全国被害者支援ネットワーク(NNVS)に加盟し,被害に遭った際,どこに住んでいても必要な支援を受けられることを目指し,さまざまな活動を展開している。また,47センターが都道府県公安委員会より「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受け,被害直後から(被害者の了承の下)警察との連携が強化したことも特徴的である(公益社団法人全国被害者支援ネットワーク,n.d.a)。
民間の被害者支援センター誕生のきっかけが,「一歩だけでも踏み出して」という被害者の声であったことの意味は大きい。足を踏み出すよう求められたのは,被害者の困難な状況に気づけなかった専門家であった。被害者から指摘されて支援の必要性に気づいた専門家が被害者と作ったのが始まりである。この意味において,センターは開設前からトラウマインフォームドケア(TIC)を求められ,私たちがやってきたこと,やろうとしていることは,TICを知る前からTICだった。それでは,どのような点がTICといえるのか,支援者養成の仕組みから見ていきたい。
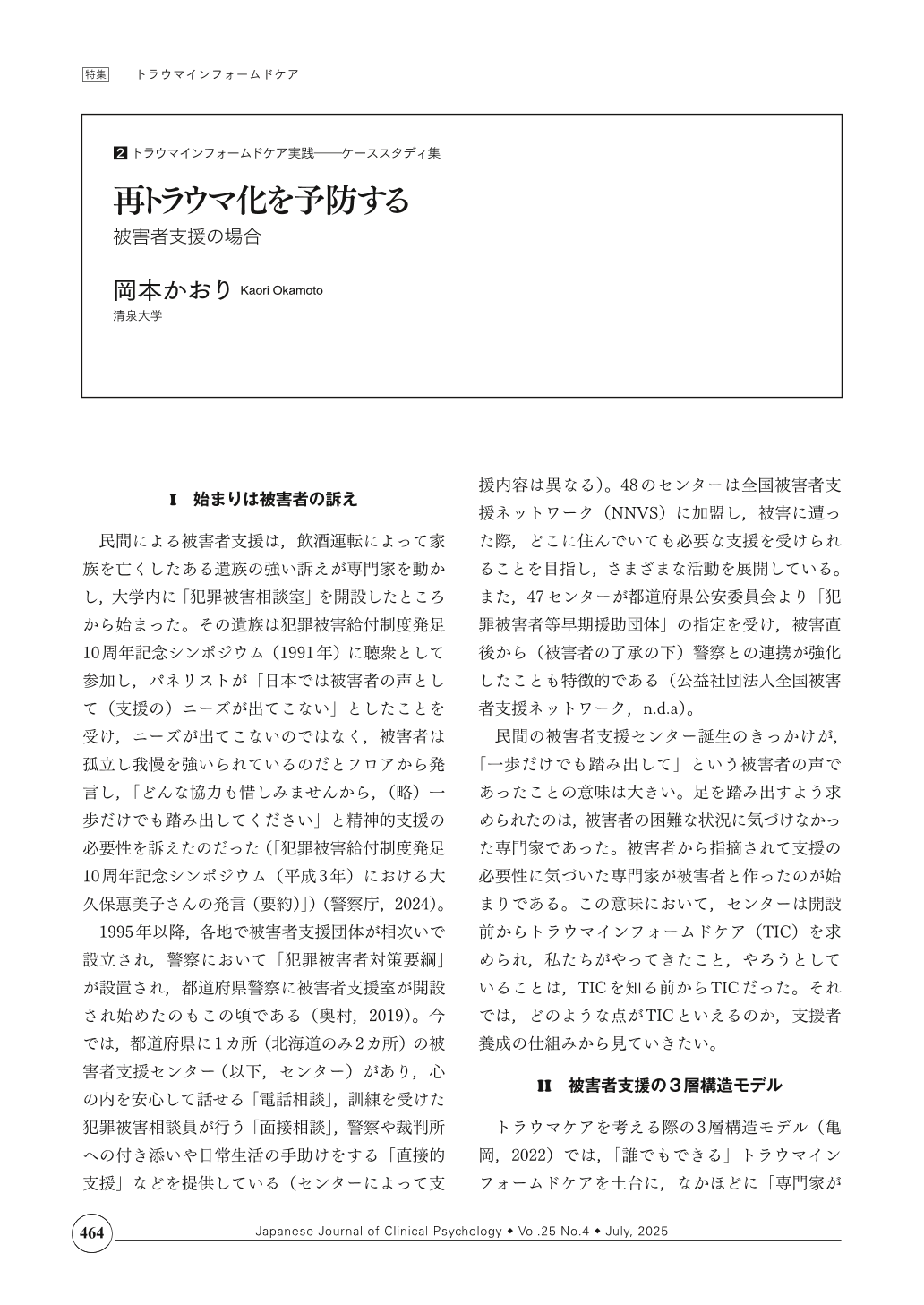
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


