- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
欧米では,非行少年に高い割合でトラウマ体験や心的外傷後ストレス障害(PTSD)症状が見られるというデータが蓄積されており,幼少期のトラウマ体験がその後の非行・犯罪ならびに司法手続きへの関与の重要なリスク要因となる可能性が示されている(Ford et al., 2006)。また,矯正施設内における再トラウマによる負の連鎖も認識されており,近年では,米国司法省が,犯罪行動を有する少年や前線で働く職員に与えるネガティブなトラウマの影響を減らすため,少年司法手続きにトラウマインフォームドケア(TIC)を導入することを呼びかけている。
「問題行動」とされてきたものをトラウマの視点で理解することで,指導や叱責とは異なるアプローチが可能となり,矯正施設内の暴力や処遇困難例,職員の制止による少年の再トラウマ化と職員の離職率を減らすことに役立つと考えられている。日本国内では,欧米ほどではないものの,2000年以降,非行少年のトラウマ体験に関するデータは蓄積されつつあり,一般人口と比べて高い傾向が示されている(法務省法務総合研究所,2024;羽間,2018)。
TICに基づくケース対応においては,幼少期の逆境体験が発達全般に及ぼす影響について理解を深め,本人の症状や行動をトラウマの視点から適切に捉えることによって,再トラウマ化を防ぐ姿勢が重要となる。国内の非行・犯罪臨床においても,これまでのアセスメントに加えて,トラウマ体験とその影響に目を向け,それらを踏まえた支援や介入の工夫が今後いっそう求められるだろう。以下では,非行・犯罪行動への心理的アプローチの変遷とともに,トラウマ研究の視点がどのように取り入れられてきたのかを概観する。
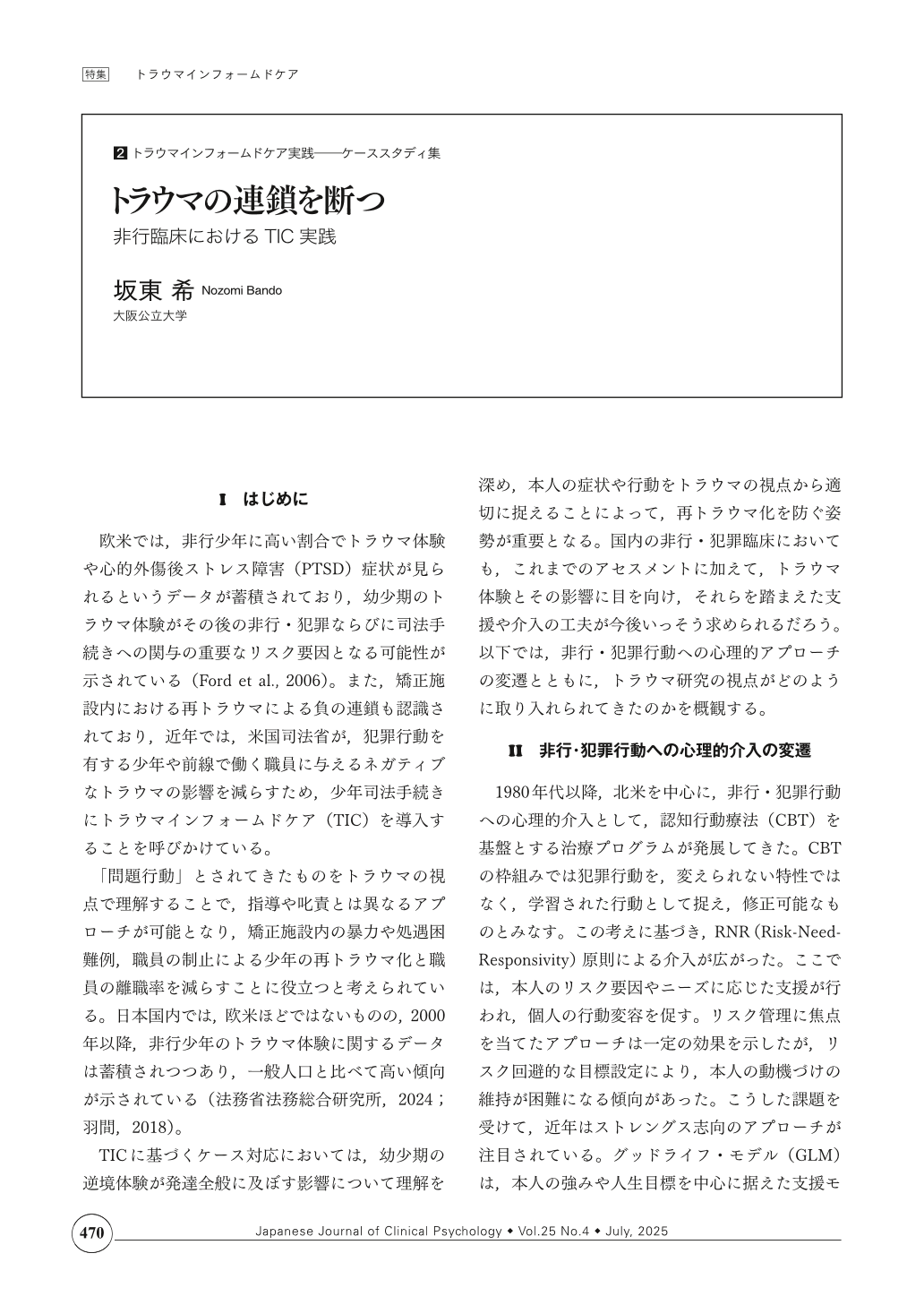
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


