Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 補装具費支給制度の歴史は?
1930年代の戦傷軍人への義肢支給制度化を原型とし,1947年の児童福祉法,1949年の身体障害者福祉法により法的制度として確立された.1950年代には品質管理と技術向上を目的に国立義肢製作所が設立され,1960年代には車椅子や補聴器等,対象品目が拡大された.1981年の国際障害者年を契機に,障害者の社会参加支援の理念が広まり,補装具の役割が再定義された.1993年には技術革新に対応する性能基準が導入され,2006年の障害者自立支援法施行により市町村が実施主体となり,利用者の自己負担は原則1割となった.2013年には難病患者が対象に加わり,2021年には視線入力装置等ICT機器も支給対象となった.
Q2 今回の改正で何が変わったか
2025年度の制度改正において,「座位保持装置」と称されていた補装具は「姿勢保持装置」に統一され,新たに車載用の種目が新設された.完成用部品については,833件から350件へと大幅に削減され,あわせて価格変更91件,名称変更15件,新設8件が実施された.さらに,一部特例制度が整備され,構成要素が1つであっても基準内補装具としての支給が可能となった.クッションに関しては,形状別(平面形状型・モールド型)に応じた価格算定方法へと改正され,修理項目には肘当て交換やブレーキ交換等が追加された.加えて,オーダーメイド製作に関する取扱いが明確化され,算定対象外部品についても明記された.
Q3 臨床現場への影響は?
2024・2025年度の補装具告示改正により,姿勢保持装置の名称統一や種目分類の新設,完成用部品の大幅整理が行われ,臨床現場では処方・申請・連携体制の見直しが求められている.特に部品削除により従来の運用が困難となり,厚生労働省は特例制度を導入したが,自治体判断に委ねられるため地域間格差が懸念されている.
Q4 間違いやすい点,知っていると便利な点は?
2024・2025年度の補装具費支給制度告示改正により,種目名称変更や完成用部品の削除,修理項目の新設等が行われ,処方ミスや申請誤りが生じやすくなっている.一方,「特例制度」の活用や補装具製作要素基準表の参照,多職種連携による申請精度向上は,制度運用を円滑にする有効な手段である.制度理解と情報共有が,現場対応力の鍵となる.
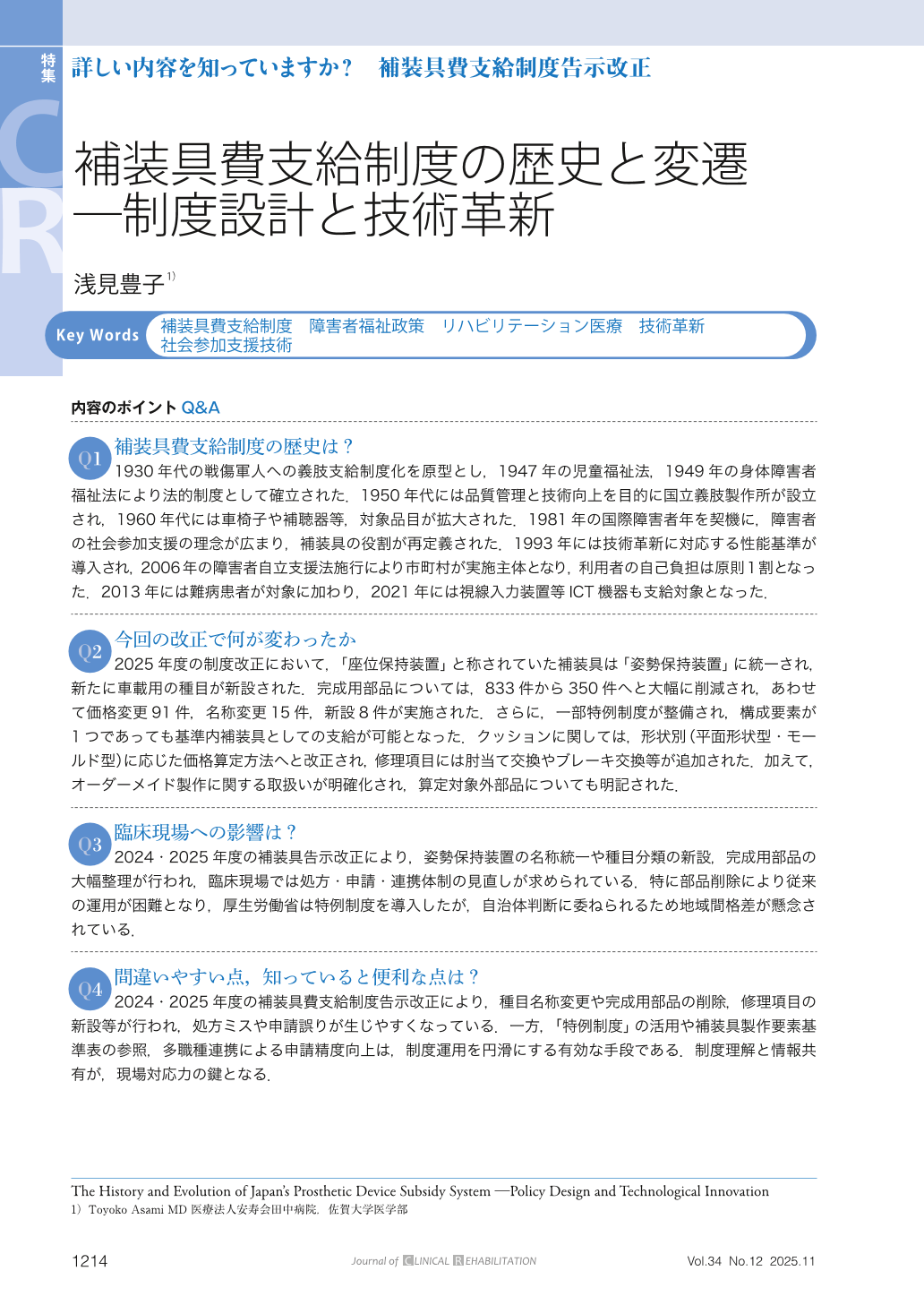
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


