特集 おさえておきたい! 胎児・新生児の超音波検査
新生児の超音波検査:頭頸部
頭部の正常形態
呉本 尚樹
1
,
有光 威志
1
KUREMOTO Naoki
1
,
ARIMITSU Takeshi
1
1慶應義塾大学医学部小児科
pp.1229-1231
発行日 2025年10月10日
Published Date 2025/10/10
DOI https://doi.org/10.24479/peri.0000002323
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
新生児に対する脳エコーは,非侵襲的で安価かつ簡便な検査法として,頭蓋内病変のスクリーニングに用いることができる1)。一方で,髄鞘化の評価は困難であり,囊胞性疾患以外の白質病変など,一部の異常は見逃される可能性がある2)。そのため,脳エコーで重度の異常を認めた場合や白質病変のリスクが高い場合には,MRIの実施を考慮する必要がある3)。通常,新生児の脳エコーでは5〜10 MHzのセクタ型またはコンベックス型トランスデューサが用いられる4)。表在構造の評価には,周波数の高いリニア型トランスデューサが推奨されており,観察対象の深さに応じてトランスデューサの形態や周波数を使い分ける5)。大泉門を音響窓として用いることが多いが,それ以外にも複数の音響窓が存在する2)。後側頭泉門(乳突泉門)は,大泉門からのアプローチで最も描出されにくい領域である後頭蓋窩の評価に優れ,小脳や第四脳室,静脈洞の評価に有用である。脳エコーは,冠状断像と矢状断像を組み合わせて観察することで,三次元的に評価することが可能である(図1)6)。各断面像を正確に評価するには,トランスデューサの選択や角度調整がきわめて重要である。また,代表的な断面像を静止画で記録することは大切だが,連続的に断面像を観察し,検査中の画像を動画で記録することが有用である7)。動画で記録することは検査時間の短縮にもつながる8)。なお,標準化された検査手順や検査時期に関して国際的に統一された基準は存在しない9)。
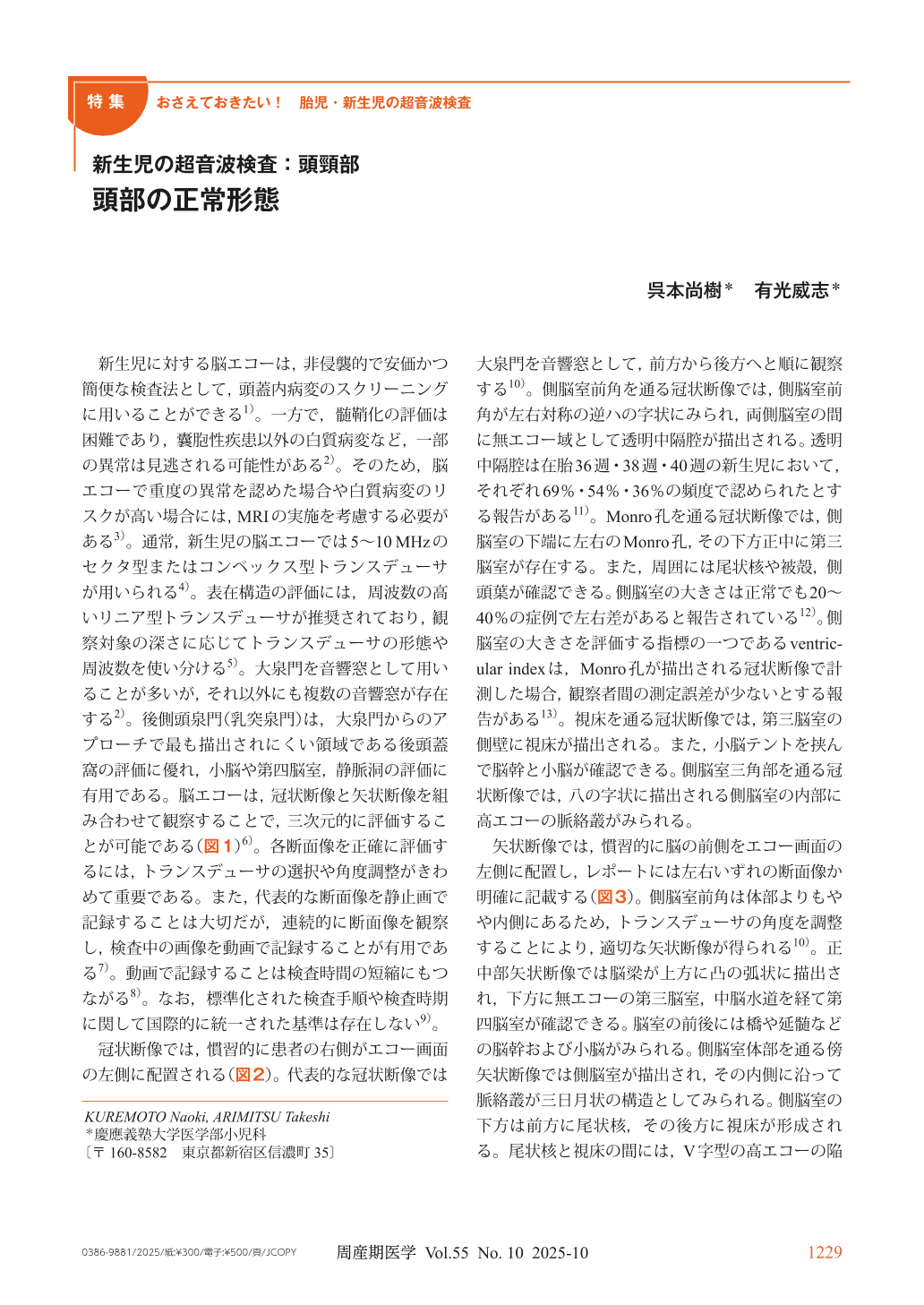
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


