特集 周産期メンタルヘルス:最新事情
各論:新生児編
児を亡くした家族へのグリーフケア
永田 雅子
1
NAGATA Masako
1
1名古屋大学心の発達支援研究実践センター
pp.889-892
発行日 2025年7月10日
Published Date 2025/7/10
DOI https://doi.org/10.24479/peri.0000002230
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
新生児死亡率や乳幼児死亡率は50年前と比べて80分の1までに低下してきてはいるが,2022年でも1,356人の子どもが生後1年以内に亡くなっており,昔も今も周産期は生と死が近接をしている時期であるということは変わりがない。子どもが生まれてくることを諦める場合であっても,生まれて間もない時期に子どもを亡くす場合であっても,親は現実の子どもを失うとともに,子どもがいたかもしれない生活そのものも失うという二重の喪失を体験することになる。通常であれば,誰か身近な人が亡くなった場合,通夜,お葬式をはじめ,儀式や日常の生活のなかでその人を悼んだり,その人を知っている人の思い出を何度も共有したりすることで,少しずつ事実を受け入れ,自分の心のなかに亡くなった人を改めて位置づけし直していく。しかし,妊娠中,また出産直後に自分の子どもを亡くした場合,その子どものことを知っている人は生活する場ではほとんどいない。また,おなかのなかで亡くなったり,出産直後に亡くなったりした場合,その死は突然であることが少なくなく,予期していない別れを受け入れなければならない。そして,わが子と限られた時間しか一緒に過ごすことができないことが多く,きちんとお別れをすることが難しいこともある。病院を出てしまえば,そこには子どもがまるでいなかったような生活が待っており,そのギャップに苦しむ人は少なくない。生まれてきた自分の子どもと会ったこともない人と,ただ唯一の存在であるその子どもについて語り合うことは難しく,誰かと悲しみや思いを共有したいと思ってもその機会は限られていて,より悲しみが遷延してしまうことも起こりうる。
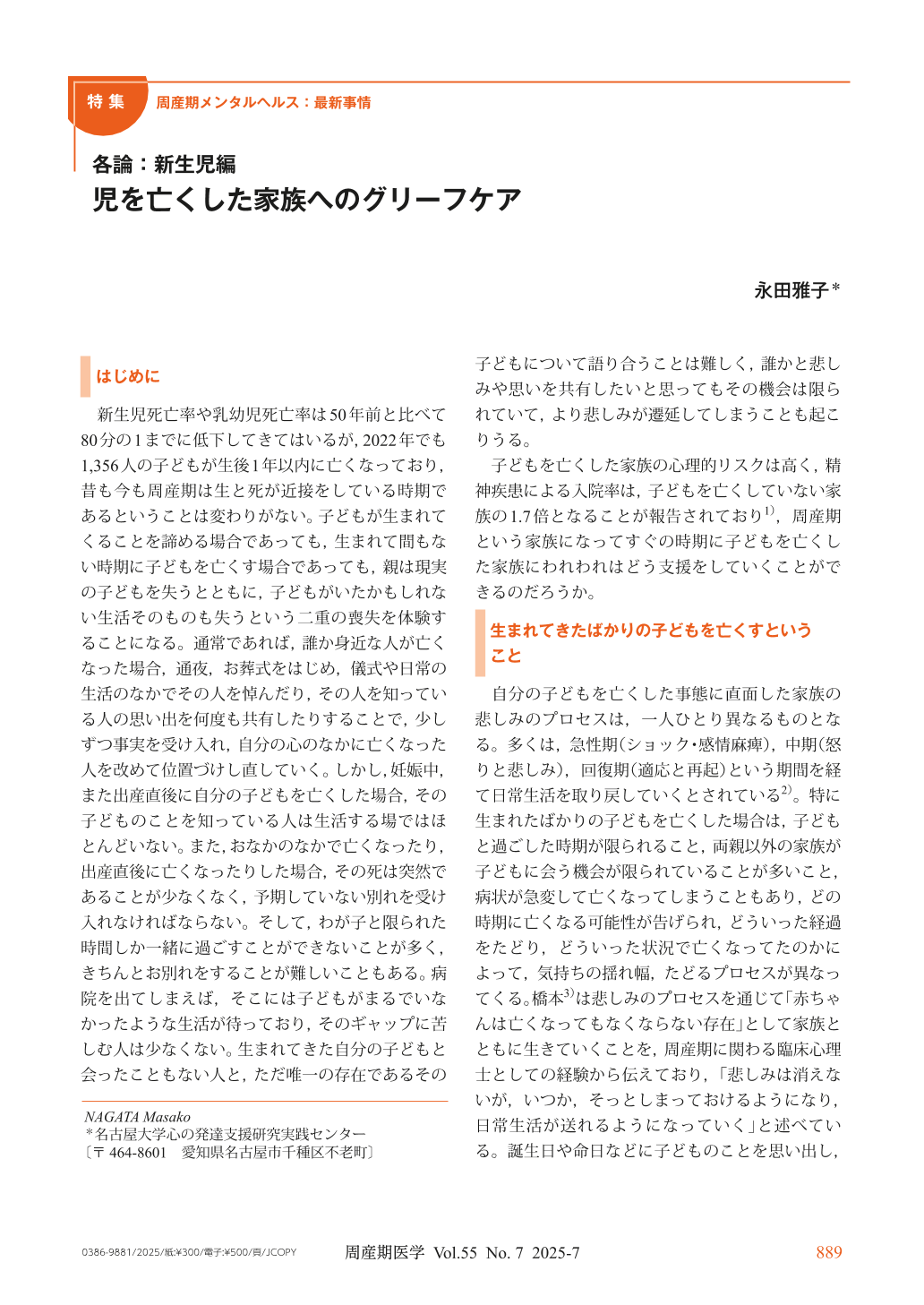
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


