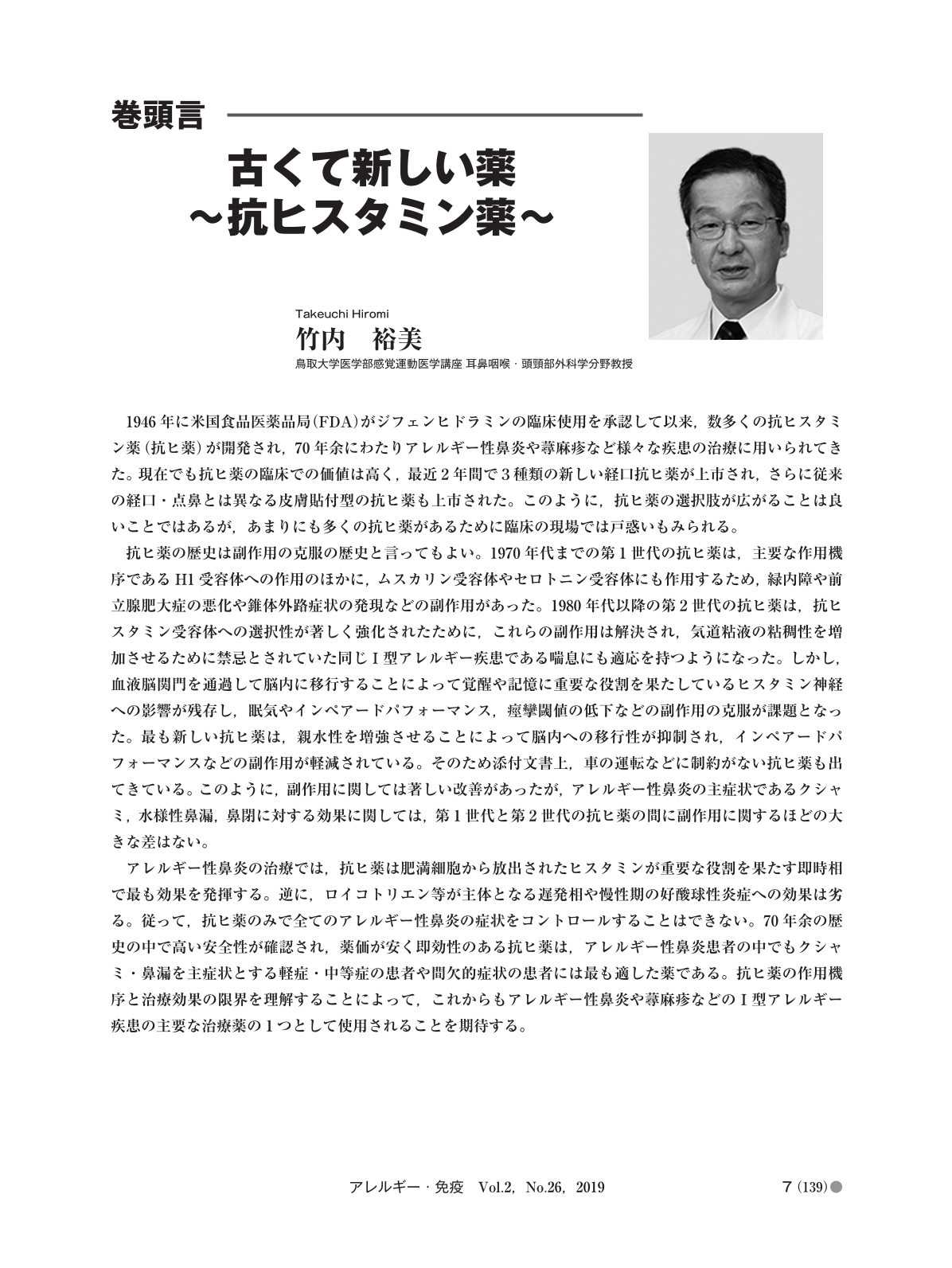- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
1946年に米国食品医薬品局(FDA)がジフェンヒドラミンの臨床使用を承認して以来,数多くの抗ヒスタミン薬(抗ヒ薬)が開発され,70年余にわたりアレルギー性鼻炎や蕁麻疹など様々な疾患の治療に用いられてきた。現在でも抗ヒ薬の臨床での価値は高く,最近2年間で3種類の新しい経口抗ヒ薬が上市され,さらに従来の経口・点鼻とは異なる皮膚貼付型の抗ヒ薬も上市された。このように,抗ヒ薬の選択肢が広がることは良いことではあるが,あまりにも多くの抗ヒ薬があるために臨床の現場では戸惑いもみられる。 抗ヒ薬の歴史は副作用の克服の歴史と言ってもよい。1970年代までの第1世代の抗ヒ薬は,主要な作用機序であるH1受容体への作用のほかに,ムスカリン受容体やセロトニン受容体にも作用するため,緑内障や前立腺肥大症の悪化や錐体外路症状の発現などの副作用があった。1980年代以降の第2世代の抗ヒ薬は,抗ヒスタミン受容体への選択性が著しく強化されたために,これらの副作用は解決され,気道粘液の粘稠性を増加させるために禁忌とされていた同じⅠ型アレルギー疾患である喘息にも適応を持つようになった。しかし,血液脳関門を通過して脳内に移行することによって覚醒や記憶に重要な役割を果たしているヒスタミン神経への影響が残存し,眠気やインペアードパフォーマンス,痙攣閾値の低下などの副作用の克服が課題となった。最も新しい抗ヒ薬は,親水性を増強させることによって脳内への移行性が抑制され,インペアードパフォーマンスなどの副作用が軽減されている。そのため添付文書上,車の運転などに制約がない抗ヒ薬も出てきている。このように,副作用に関しては著しい改善があったが,アレルギー性鼻炎の主症状であるクシャミ,水様性鼻漏,鼻閉に対する効果に関しては,第1世代と第2世代の抗ヒ薬の間に副作用に関するほどの大きな差はない。 アレルギー性鼻炎の治療では,抗ヒ薬は肥満細胞から放出されたヒスタミンが重要な役割を果たす即時相で最も効果を発揮する。逆に,ロイコトリエン等が主体となる遅発相や慢性期の好酸球性炎症への効果は劣る。従って,抗ヒ薬のみで全てのアレルギー性鼻炎の症状をコントロールすることはできない。70年余の歴史の中で高い安全性が確認され,薬価が安く即効性のある抗ヒ薬は,アレルギー性鼻炎患者の中でもクシャミ・鼻漏を主症状とする軽症・中等症の患者や間欠的症状の患者には最も適した薬である。抗ヒ薬の作用機序と治療効果の限界を理解することによって,これからもアレルギー性鼻炎や蕁麻疹などのⅠ型アレルギー疾患の主要な治療薬の1つとして使用されることを期待する。