- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
がん診療の現場では,各がん種の治療方針に関する診療ガイドラインから,支持療法やケアに関するガイドラインまで,幅広いガイドラインが作成されています.看護師は診療ガイドラインにはあまり馴染みがないかもしれませんが,個々の患者の治療方針を決定するための指針として医療チーム内で共有したり,エビデンスに基づいた看護実践を行うために関連するガイドラインを参考にした経験がある方は多いのではないでしょうか.
診療ガイドラインとは,「健康に関する重要な課題について,医療利用者と提供者の意思決定を支援するために,システマティックレビューによりエビデンス総体を評価し,益と害のバランスを勘案して,最適と考えられる推奨を提示する文書」と定義されています(Minds診療ガイドライン作成マニュアル編集委員会,2021).診療ガイドラインの真の目的は,患者と家族,医療者との意思決定を支援することにあり,患者-医療者間,また医療チーム間でのコミュニケーションツールとしての役割も期待されています.
その一方で,医療者がガイドラインの推奨を盲信し,その作成背景や推奨される条件を十分に理解せず,準拠することを優先してしまうと,shared decision making(SDM)や,個々の患者に適した看護実践をサポートするツールにはなりえません.がん臨床に携わる看護師も,関連するガイドラインの目的や内容を正しく理解し,幅広く活用することが求められますが,実際には看護師にとってむずかしさを感じることが多いのが現実です.
本特集では,まず総論として診療ガイドラインとは何か,一般的なマニュアルとの違いやその成り立ち,推奨を決定するための総意形成のプロセスをわかりやすく解説します.そのうえで,診療ガイドラインを患者の治療方針の決定の話し合いにおいてどのように活用しているか,その実際と限界について紹介します.また,診療ガイドラインとは異なる患者の意思決定プロセスに関するガイドラインについて,その意義と活用,さらに,看護実践に関するガイドラインを開発する重要性について解説します.患者の立場からはガイドライン作成への患者参画の重要性や,診療ガイドラインに基づいた治療方針決定における患者・医療者間のコミュニケーション課題について解説しています.そして,最後の実践編では,近年発表されたがん看護に役立つガイドラインを取り上げ,臨床でのがん看護実践における活用例を紹介します.
本企画がガイドラインを身近に感じ,エビデンスに基づいた知識を基にした意思決定の支援やがん看護の実践に役立つことを期待します.
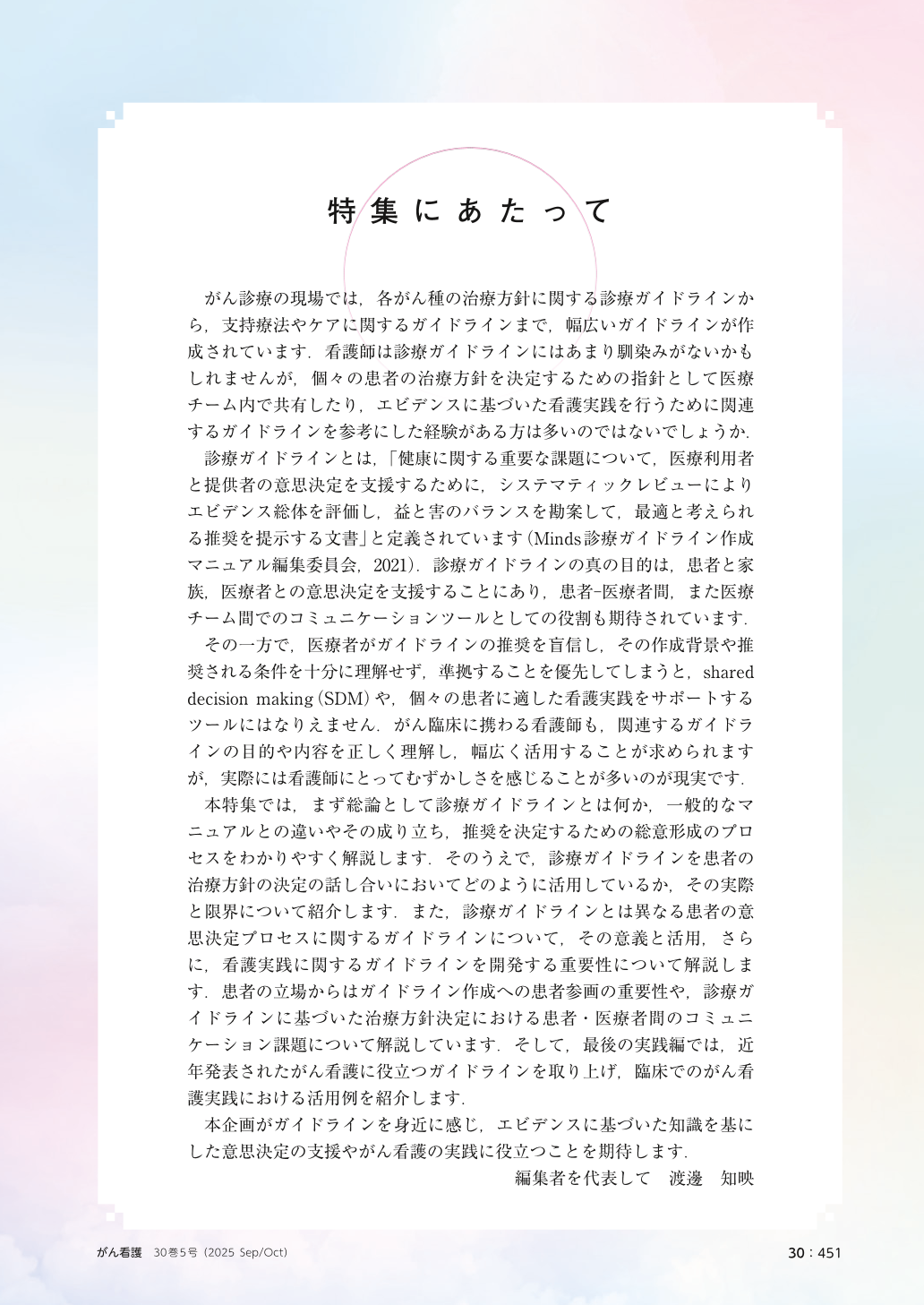
© Nankodo Co., Ltd., 2025


