特集 薬物治療の質向上
Part 2 薬物治療を適切に個別化するための基本知識
【コラム②】肝疾患や肥満患者での薬剤投与—投与量は通常量と同じでよいのか?
浜田 幸宏
1
Yukihiro HAMADA
1
1高知大学医学部附属病院 薬剤部
pp.308-313
発行日 2025年3月1日
Published Date 2025/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.218804090120020308
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
肝臓の重要な役割の1つとして,異物に対する解毒作用がある。薬物自体を異物として考えるのであれば,その解毒をするのが肝臓である。解毒を薬物の代謝・排泄として置き換えると,肝臓自体に障害があれば,当然,代謝・排泄の遅延が薬物の蓄積につながり,有害事象の発現の可能性が高くなると容易に想像できる。しかしながら,腎臓とは異なり,肝臓では急性期の場合,肝血流量はほとんど変化しない。肝硬変などの慢性期の場合には,代謝機能の低下,すなわち肝クリアランスの低下が起こるため,その際に薬物の減量が必要となる。
ただし,一般的には肝臓の代謝能力の変化を定量的に把握することは困難と考えられている。例えば,一般的な肝機能検査であるAST*1,ALT*2の上昇は肝障害があることを示唆するが,必ずしも肝臓そのものの機能を反映しているとは限らない。そのため,これらを薬物代謝能力の指標として用いてよいかはケースバイケースである。肝硬変のような重度の障害を受けている場合でも,ASTやALTなどが見かけ上,正常の値を示すことは臨床でもよく経験することである。
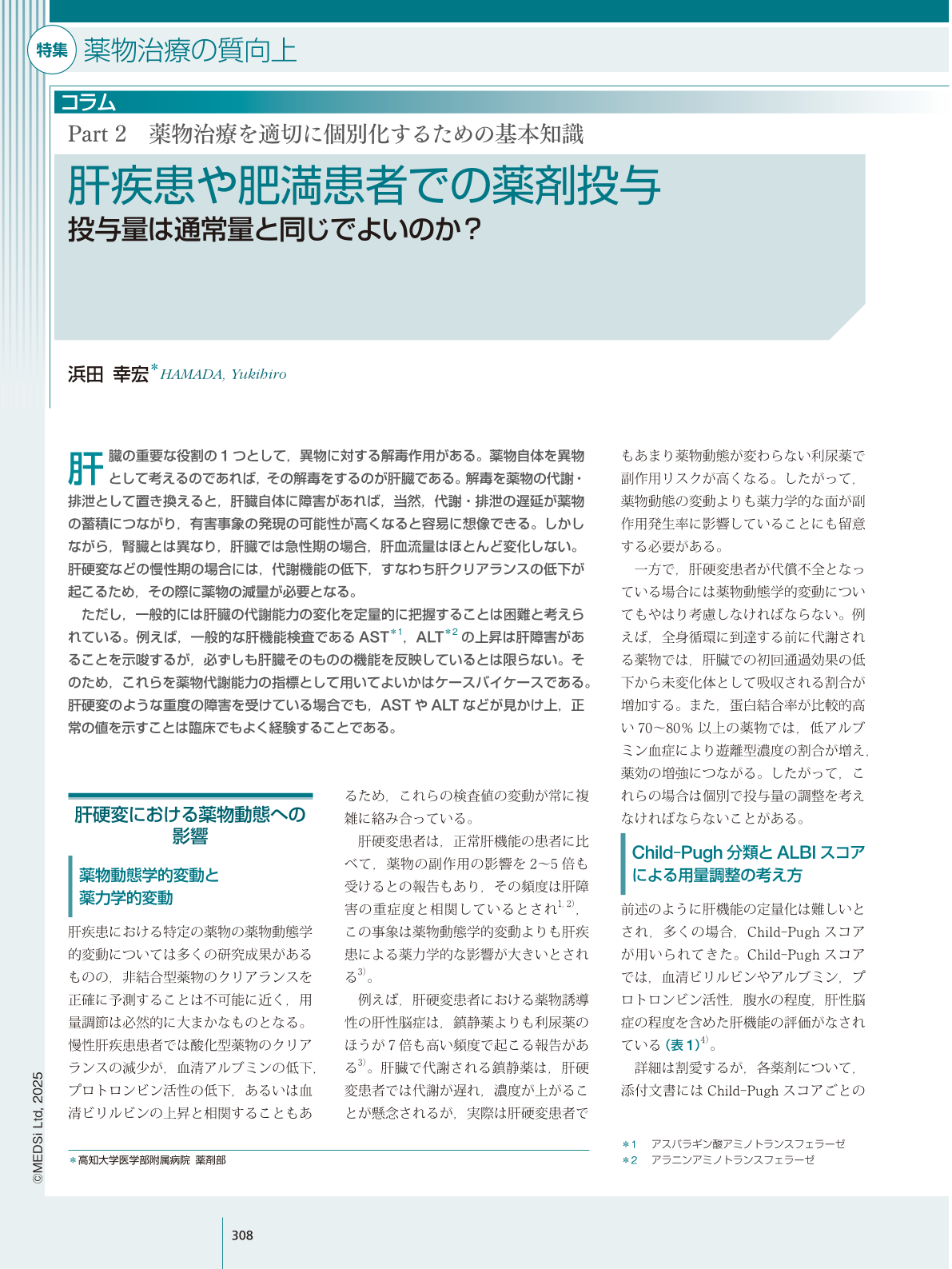
Copyright © 2025, MEDICAL SCIENCES INTERNATIONAL, LTD. All rights reserved.


