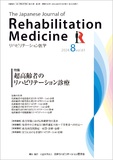Japanese
English
- 販売していません
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
わが国では,道路交通法第103条で免許の取消し・停止の病気を定めており,警察庁からは,「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準(運用基準)」1)が出され,対応が明記されている.運用基準の脳卒中の項目には,慢性化した運動麻痺,視覚障害及び聴覚障害は「身体の障害」,見当識障害,記憶障害,判断障害,注意障害は「認知症」に係る規定等に従うと記載されている.「身体の障害」の規定を表12)に示す.「認知症」の規定では,アルツハイマー型,血管性,前頭側頭型,レビー小体型の4つの認知症は免許取消しと明記されているが,対応しにくいのは「その他の認知症」の項目で,脳卒中による高次脳機能障害は脳腫瘍や頭部外傷後遺症とともに,「6カ月以内に回復する見込み」などの診断をすることになる.しかし,その「回復」に関する判断基準は不明確である.また,法的な認知症(道路交通法第90条,介護保険法第5条の2に規定)とは「日常生活に支障があるほど認知機能が低下した状態」であるが,脳卒中患者は社会生活に支障はあるが日常生活は問題ないことも多く,法的には認知症ではないが運転再開は危険な患者も存在する.したがって,多くの医療機関では,運転に関与する認知機能を机上評価や運転シミュレーター(driving simulator:DS)を用いて把握し,さらに自動車教習所で実車教習を受ける流れで,運転適性を判断している.日本リハビリテーション医学会では脳卒中・脳外傷者の自動車運転に関する指導指針3)を作成している他,日本高次脳機能障害学会では神経心理学的検査法の適応と判断4)を公開しており参考可能である.筆者が利用している福岡県安全運転医療連絡協議会で推奨する神経心理学的検査を表25)に示す.
本稿では,脳卒中患者に合併・併発しやすい症状を挙げ,運転に関する対応を運用基準の内容を含め解説する.また,筆者が経験した症例を提示し,半盲患者の対応に関して考察する.
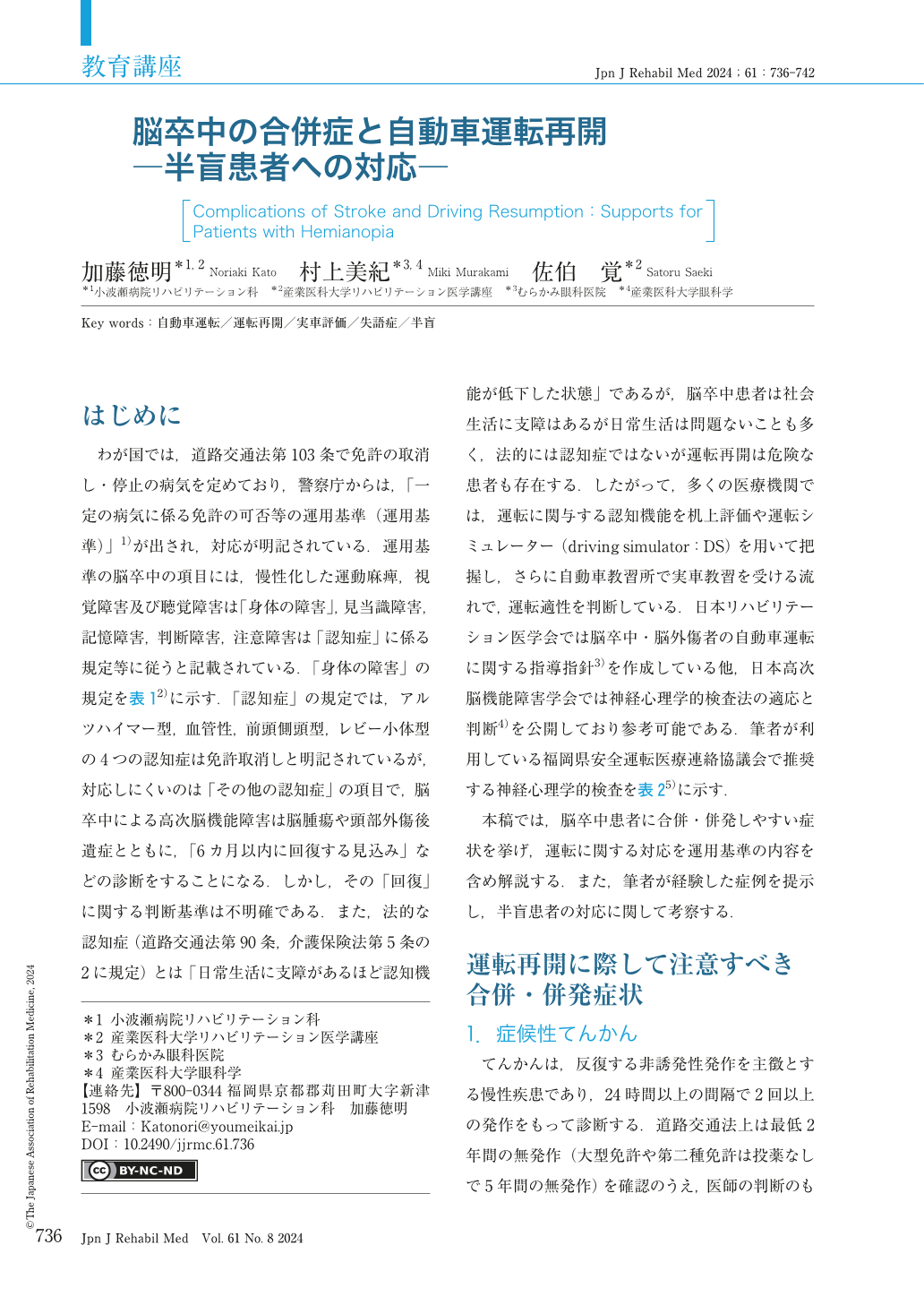
Copyright © 2024, The Japanese Association of Rehabilitation Medicine. All rights reserved.