- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
研究から得られた知見が臨床現場での実践のエビデンスとなり,よりよいケアにつながっていくことは,多くの看護学の研究者が願っていることかと思います。このような「研究で知見を生み出し,社会に還元する」ことの必要性は十分に理解されているものの,まさに“言うは易く行うは難し”です。今回,2号連続の特集にて紹介する実装研究(Implementation Research)(Brownson, Colditz, & Proctor, 2018)は,この道のりを進んでいくための道標となる学術分野です。
筆者(友滝)が初めて「実装」という言葉を意識するにようになったのは,看護系大学の教員になったばかりで,エビデンスに基づく実践について学び直していた頃に遡ります。当時,「医師のEvidence-based Medicine(EBM)と看護師のEvidence-based Nursing(EBN)は何が違うのか? 区別する必要があるのか? Evidence-based Practice(EBP)でよいのでは?」「なぜ『EBP』ではなく,『EBPの実装』とあえて表現するのだろう?」という疑問をもっていました。実際に,「エビデンスに基づく〇〇」や「実装」にまつわる用語も多様で様々な文脈で使われるため,用語の混乱について指摘されています(McKibbon et al., 2010)。そこで,まずこれらの用語について,本稿での考え方を整理します。
エビデンスに基づく実践について,Sackettは,「利用可能な最良のエビデンスを,臨床家の専門技能・患者個別の状況や価値観と統合すること」がEBMであると述べました(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996)。本稿ではこの定義に則り,医療者のエビデンスに基づく実践の総称として「EBP」を用います。
次に,EBPの構成要素の1つであるエビデンスについて考えてみます。臨床上の疑問によってエビデンスの確からしさが様々な中で,EBPの“evidence”となる「利用可能な最良のエビデンス」を見極めていきます。一方で,実際の臨床では,エビデンスの強弱のみで適用するかを決定するわけではありません。弱いエビデンスであっても,そのことを踏まえて(批判的に吟味した上で),実践に統合されていきます。このように様々なエビデンスがありますが,その中でも,「健康に関するアウトカムに対して有効性があるということが実証されているケアや治療」もあります。このようなケアや治療を「エビデンスに基づく介入(Evidence-based Intervention:EBI)」とし,EBIを臨床現場で取り入れるのが,実装(Implementation)というプロセスです註1。そこで,本稿ではこれ以降,「エビデンスに基づく実践」という包括的な概念を意味するときは「EBP」を用い,特に有効性が示されている介入の実装に関して述べるときは「EBI」を用います。
ここで,看護の実践場面を考えてみたいと思います。看護の実践は,様々な人を介して,複雑な・多面的なアプローチを用い,患者・家族・医療者間の関係性や相互作用がある中でケアを行うという側面を持ち合わせています。これは看護師にとっては日常的なことですが,このような複雑で多面的な側面は,ときに,エビデンスに基づいた方法の採用や定着が進まない背景にもなりえます。「効果が期待できるエビデンスのある方法があっても,現場では採用されない」,あるいは「効果が期待できないというエビデンスのある方法があっても,現場ではやめられない」といった状況です。このような状況下では,「エビデンスがあるなら,取り入れればよい/エビデンスがないなら,やめればよい」と単純化できません。また看護師は,個人の裁量で個々が実践するよりも,複数人で/チームで/組織としてケアに取り組む場面が多い専門職です。そのため,「エビデンスに基づいて,いま行っているケアを変えていこう」といった行動をとろうとするときには,組織的な観点がより一層求められています。このような背景から,EBIを実際に取り入れる「実装」に関心が高まっています。
そこで特集の〈前編〉となる本号では,看護師の実践場面を想定した「実装」に焦点を当てて,実装のモデルやフレームワークを専門家の皆様にご紹介いただきます。本稿ではその導入として,EBIの実装がなぜ必要なのか,何が実装を妨げているのか,実装を進めていくためにはどのようなプロセスをたどるのかを概説します。
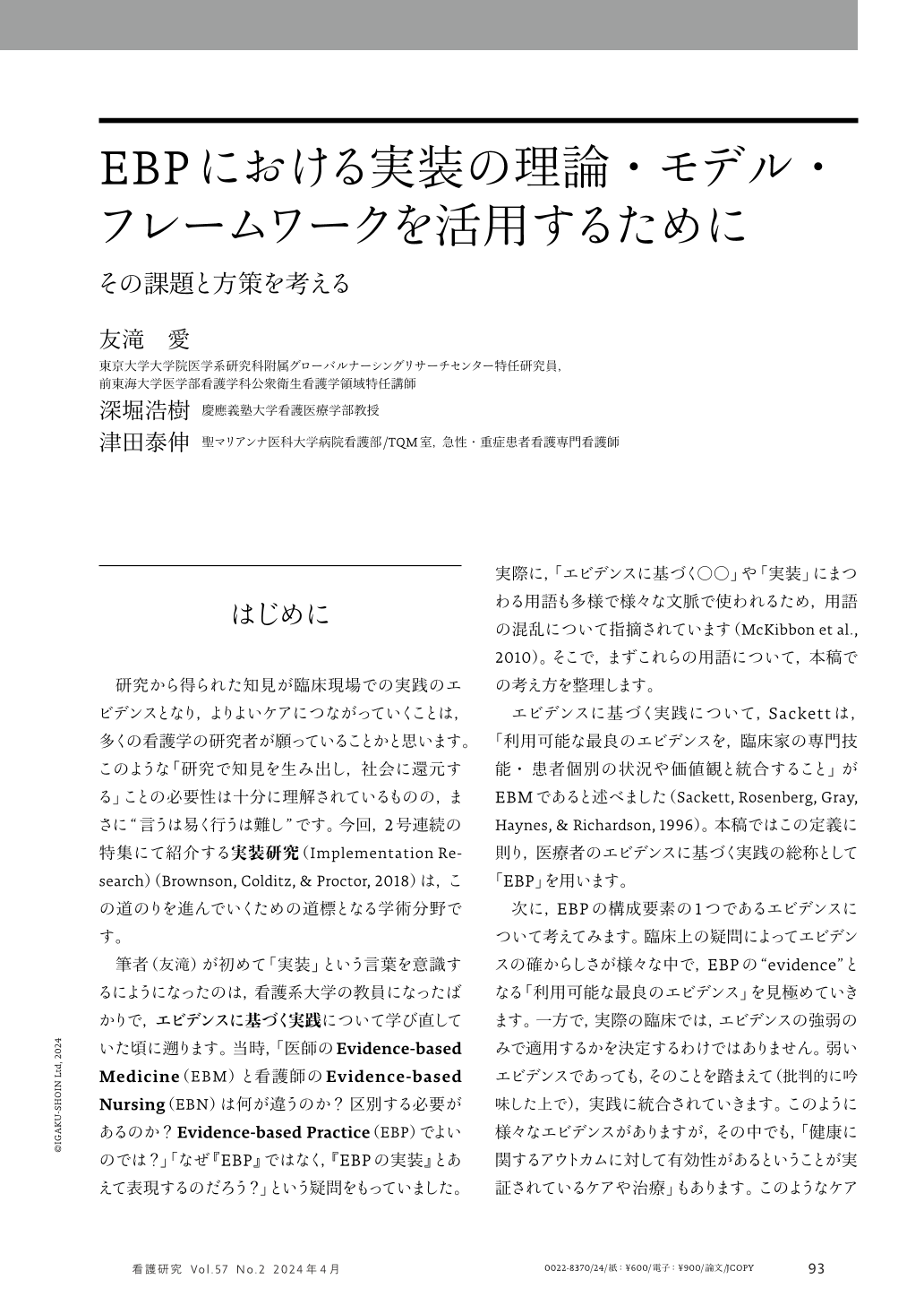
Copyright © 2024, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


