連載 家族社会学・4【最終回】
家族とプラクティス
山根 常男
1
1大阪市立大家政学部社会福祉学科
pp.311-317
発行日 1969年10月15日
Published Date 1969/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1681200155
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
家族解体
おおざっぱにいって,家族の解体現象は資本主義の発展とともに顕在化してきたといえる。かくして19世紀後半にはいると,家族と経済体系の矛盾から生ずる家族の解体現象に,はじめて科学的関心が払われるようになった。この結果あらわれた最初の顕著な業績として,ルプレイの「ヨーロッパの労働者」(1855年),ベーベル(F. A. Bebel)の「婦人論」(1879年),エンゲルス(F. Engels)の「家族・私有財産・国家の起源」(1884年)などをあげることができるであろう。もっとも前者と後二者とでは発想法に基本的な相違があった。すなわち前者は家族の独立変数としての面を強調して,現代の支配的な家族を不安定(unstable)なものとし,従来の直系的家族(famille-souche)をより望ましいものと考える後ろ向きの姿勢を示したのに対し,後二者はともに家族が社会の従属変数である面を強調し,結婚や家族の不幸は,革命による経済体系の飛躍的発展によってのみ解決されるという前向きの姿勢を示したのである。しかしいずれにせよこの種の研究は社会の歴史的変化と現実の家族制度との矛盾を分析・解釈したもので,それは第2章で論じた家族の制度的変化の領域に含まれるものである。ゆえにこれをしいて家族解体の研究として位置づけるならば,それは制度論的家族解体論と称することができるであろう。
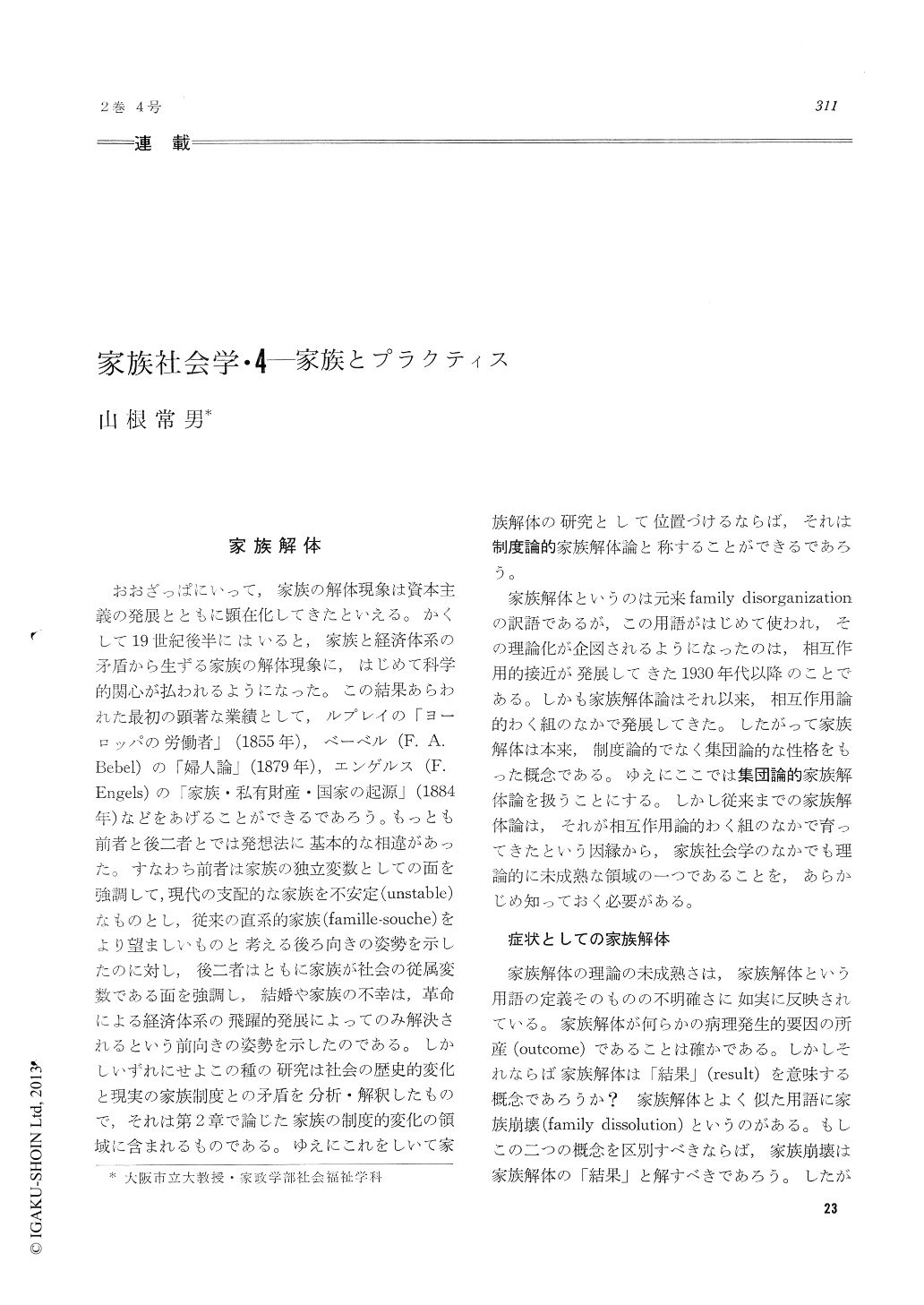
Copyright © 1969, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


