増刊号特集 1.博士論文を書くということ─あのときの問いといまの問い
博士号の取得までとその後―看護学研究者のよりよい育成環境づくりをめざして
山本 則子
1
1東京大学大学院医学系研究科
pp.284-288
発行日 2014年7月15日
Published Date 2014/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1681100917
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1994年暮れに博士論文審査を終了してから,20年になる。博士論文の研究で立てた問いから現在までの研究内容を振り返り,あわせて米国で見聞きした研究者の育成過程を紹介して,今後の看護学研究者の育成のあり方について検討する一助としたい。
博士論文の問いから現在の問いまで
現場感覚からの問い
私にとって博士課程での研究は,臨床時代,修士時代からの心残りを解消する意味合いが強かった。修士課程にいた頃から,特例許可老人病院(現在の医療療養病床)や訪問看護での現場経験から,高齢者の家族への支援に関心があった。社会では高齢者の家族介護がようやく注目され始めたところで,研究の多くは介護負担に注目していたが,自分の臨床経験では介護負担は介護者の経験の一部に過ぎず,焦点の当て方として不十分という気がしていた。修士課程に在席していたときの大学院の先輩が紹介してくれたグラウンデッド・セオリー法には「これを『科学』と呼べるのか」と強く反発したことを覚えている。その一方で,介護経験について測定できそうな唯一の尺度は介護負担感尺度で,それには違和感があり,納得のいかないまま修士課程を終えた。
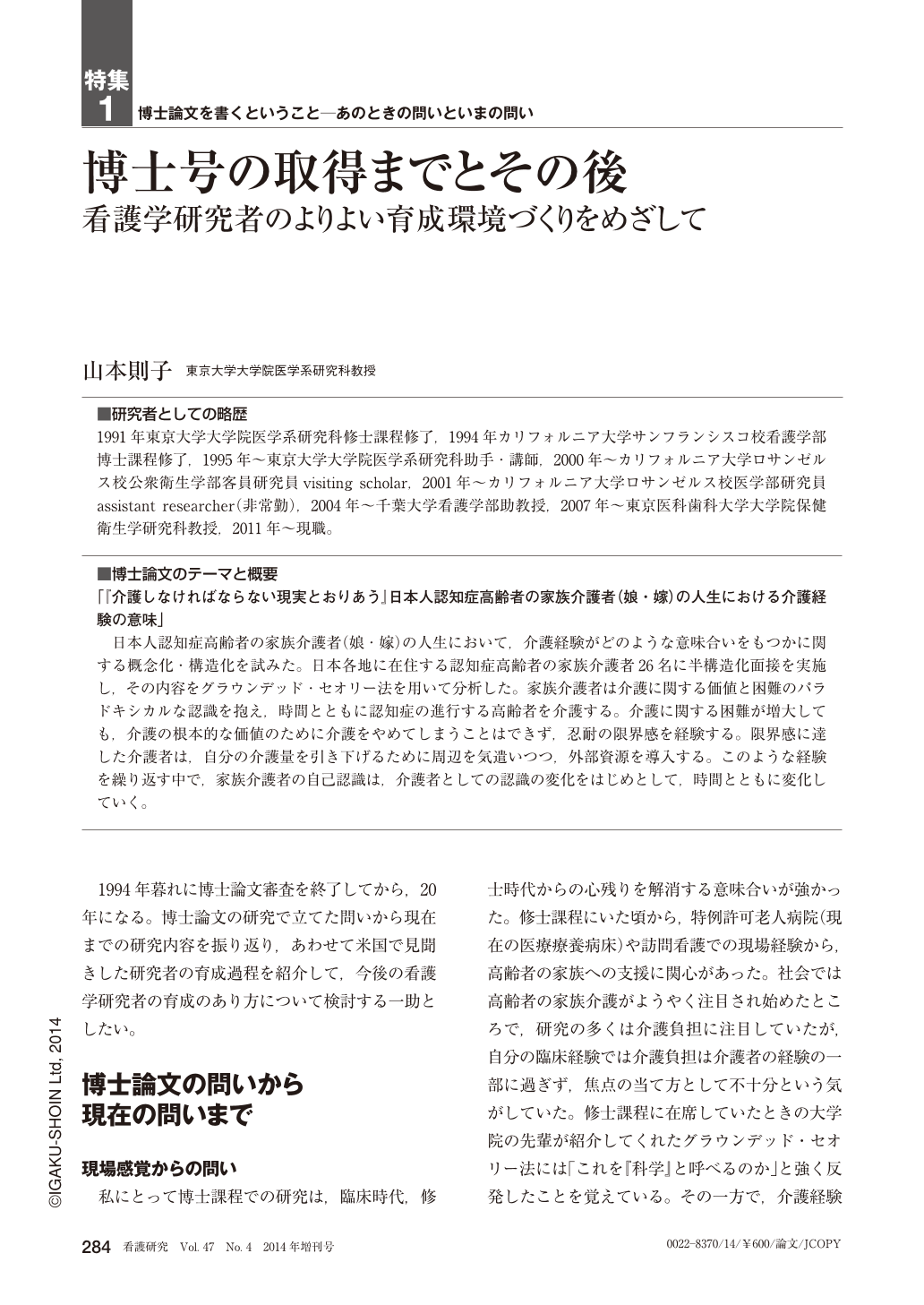
Copyright © 2014, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


