- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1990年代の終わり頃から、「聞く/聴く」註1ことを主題とする書籍が複数出版されてきました。その端緒になったのが『「聴く」ことの力』でしょう。哲学者の鷲田清一は本書において、「〈聴く〉というのは、なにもしないで耳を傾けるという単純に受動的な行為」ではなく、語り手にとっては「ことばを受けとめてもらったという、たしかな出来事」であるとし、聴くという行為の持つ「力」について臨床哲学の視点から思索を行っています1)。2000年代に入ってからも、エッセイストの阿川佐和子さんが2012年に書いた『聞く力』2)は、100万部を超えるベストセラーとなりましたし、最近でも、ケイト・マーフィの『LISTEN』3)や、東畑開人の『聞く技術 聞いてもらう技術』4)など、関連書籍の出版が続いています。
このことからもわかるように、現代社会においては、多くの人が聴くことに大きな関心を寄せているわけですが、それは医療や看護の領域においても同様です。医師であれ看護師であれ、医療者は今や、患者やその家族の話をいかにしっかりと聴くことができるかが問われています。そうした中で、医療者像にも変化の兆しがみられます。すなわち、「患者の話を聴かない医療者」から「患者の話を聴く医療者」への変化です。これまで患者が医療者に対して抱く不満に、「話を聴いてもらえない」というものがありました5) 註2。しかし最近では、徐々にではありますが、「患者の話を聴く医療者」というイメージが浸透しつつあるように感じます。こうした変化は患者にとって望ましいことのように思われますが、そこでの「患者の話を聴く医療者」というものが、高度な「コミュニケーション能力」や繊細な「傾聴の技法」を身につけた医療者として(のみ)イメージされているとすれば、一定の留保が必要かもしれません。今回は「ナラティヴ(narrative)」をキーワードに、「物語の聴き手としての医療者」について考えてみたいと思います。
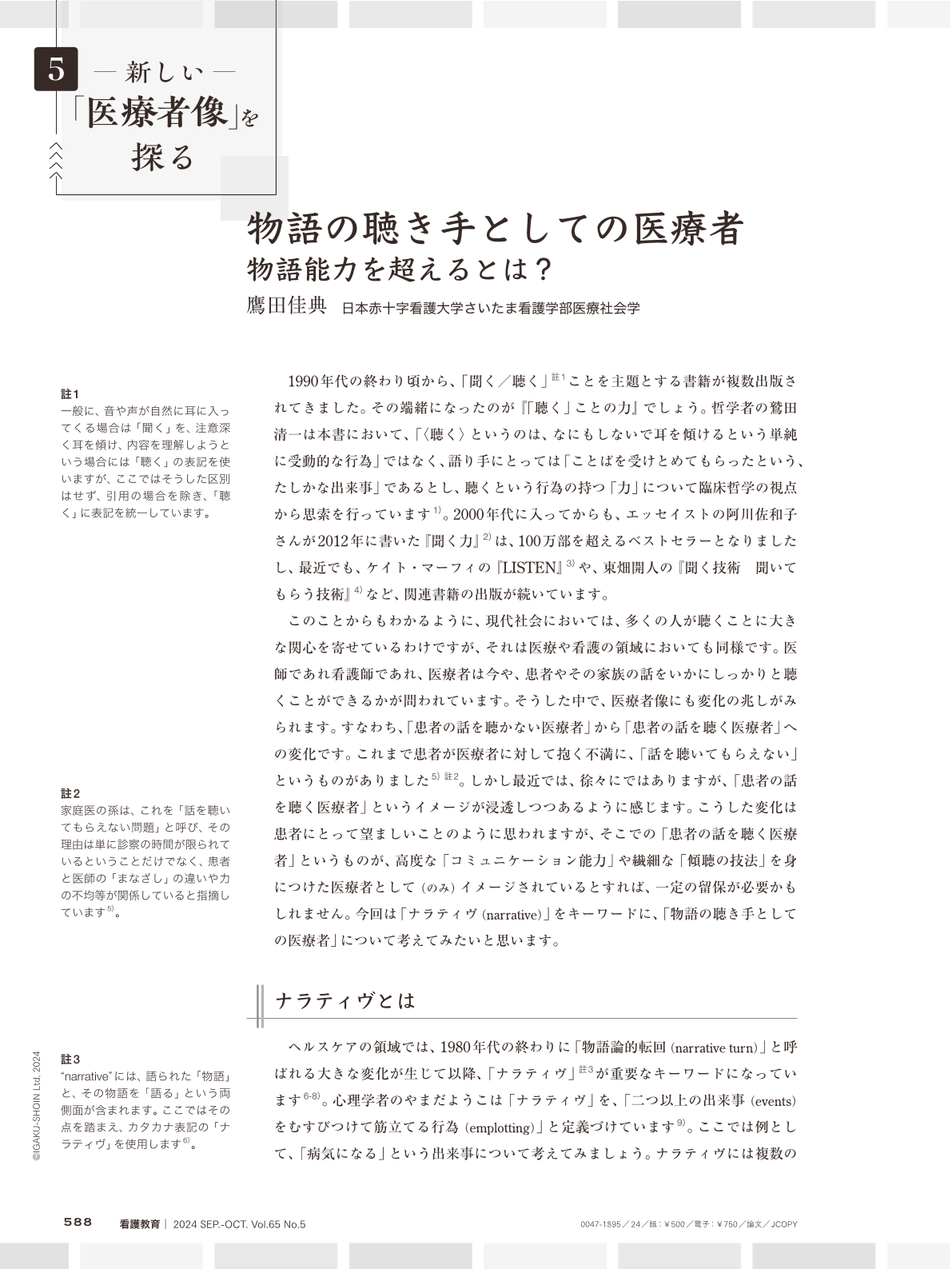
Copyright © 2024, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


