講座
食思の訴え
川島 震一
1
1川島胃腸病院
pp.6-9
発行日 1955年5月15日
Published Date 1955/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661909823
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
人間は口から食物を取つて之を消化吸收し肺臓から吸收された酸素で還元酸化して生じた熱エネルギーで色々の生理現像を行う。食欲と云うものは之の生活機能保持新陳代謝並びに活動の源泉として必要に応じて体内に特定の食物を取り入れ様とする積極的感覚であります。消化器上部より大脳への空腹反射,血液体液の変化が自律神経中枢迷走神経,交感神経のある間脳延髄を介して消化器殊に胃の運動並びに分泌に変化を起し夫れが直接の刺戟となつて総合せられた結果大脳に食欲と弐う感覚を起すものである。即ち其の感覚発生に全身的欲求によるものと局所感覚よりするものとがあるのである。
空腹感の反対は満腹感で概ねこの差が食欲に支配的役割をするのであるが,この他に各人の味覚臭覚視覚聴覚盗覚等の経験と殊に記憶が深い関聯を持つて作用しているのである。従って其等の鈍敏の差個々の教養,家柄,土地柄の伝統習慣に深い関係があり,周囲前後の情緒的精神状態が強く支配するのである。健康で空腹であれば食事に関係した各種の音を聞いても物を見ても食物の臭を嗅ぐ事によつても唾液胃液の分泌Appetit Juice(食欲汁)が起り胃の運動が元進して摂食消化の準備が行われる。食欲は生命の欲求であり又健康のシンボルでもある。
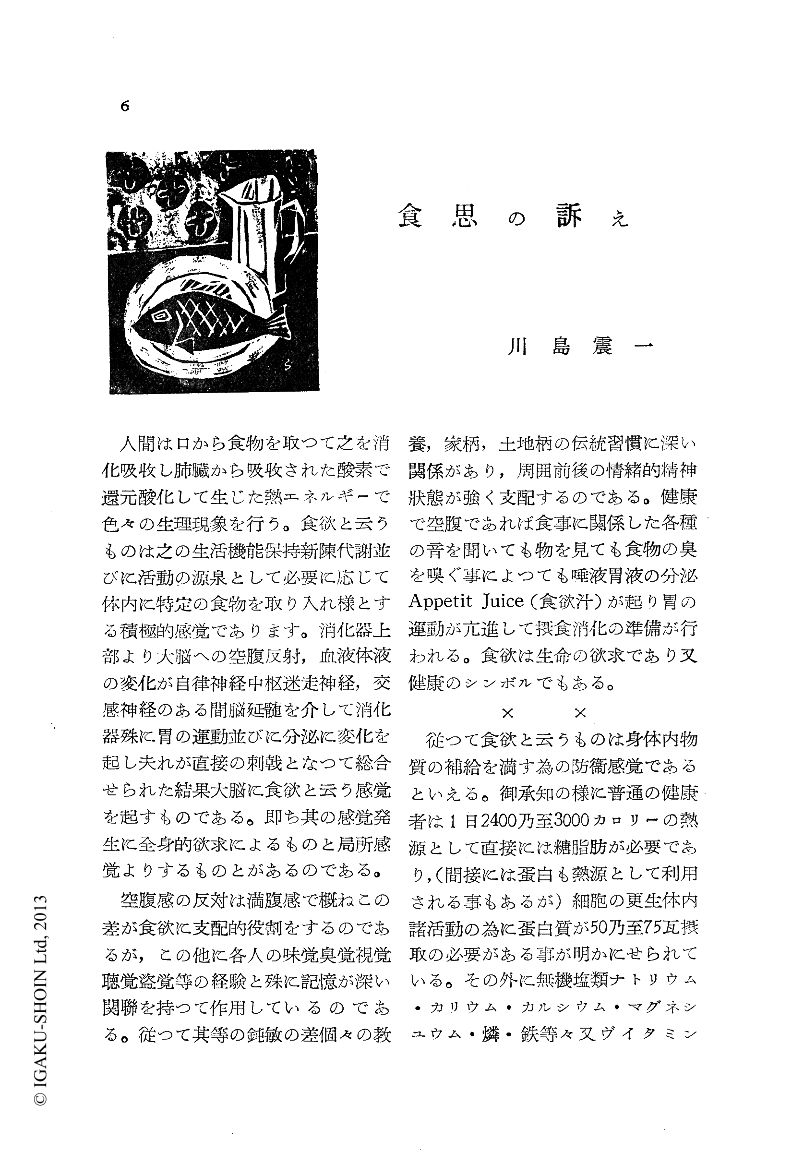
Copyright © 1955, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


