研究
DNA被覆赤血球凝集反応による抗核抗体検出について—螢光抗体法との比較および甲状腺疾患における出現頻度
幸地 良勝
1
,
新井 加余子
1
,
奥間 啓一
1
,
網野 信行
1
1阪大病院中検
pp.179-181
発行日 1976年2月15日
Published Date 1976/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542909279
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
抗核抗体測定は自己免疫疾患,なかでも全身臓器に障害のみられるSLEの診断治療上の重要な指標の一つとなっている.対応する細胞核抗原も核タンパク,DNA,核可溶性抗原,ピストンおよび核小体タンパクなどの成分に分けられ検索がされているが1),これらのうちDNAに対する抗体はSLEの病像と最も深い関連があるものとして注目されている2).血中抗核抗体の検出法には従来より種々の方法が考案されているが,現在日常臨床検査としてはLE細胞現象,Coonsの間接螢光抗体法が最もよく普及している.核抗原は臓器特異性がなく,したがって抗核抗体測定も一般には全身臓器に障害のみられる自己免疫疾患につき行われているが,逆に慢性甲状腺炎などの臓器特異性のある自己免疫疾患での出現頻度に興味がもたれる.今回,私たちは受身赤血球凝集反応を用いた抗DNA抗体検出法と従来よりの螢光抗体法とを比較検討した.更に両測定法を用いて臓器特異性自己免疫疾患も含めた各種甲状腺疾患における抗核抗体の出現頻度を調べ,抗甲状腺自己抗体との関連を検討した.
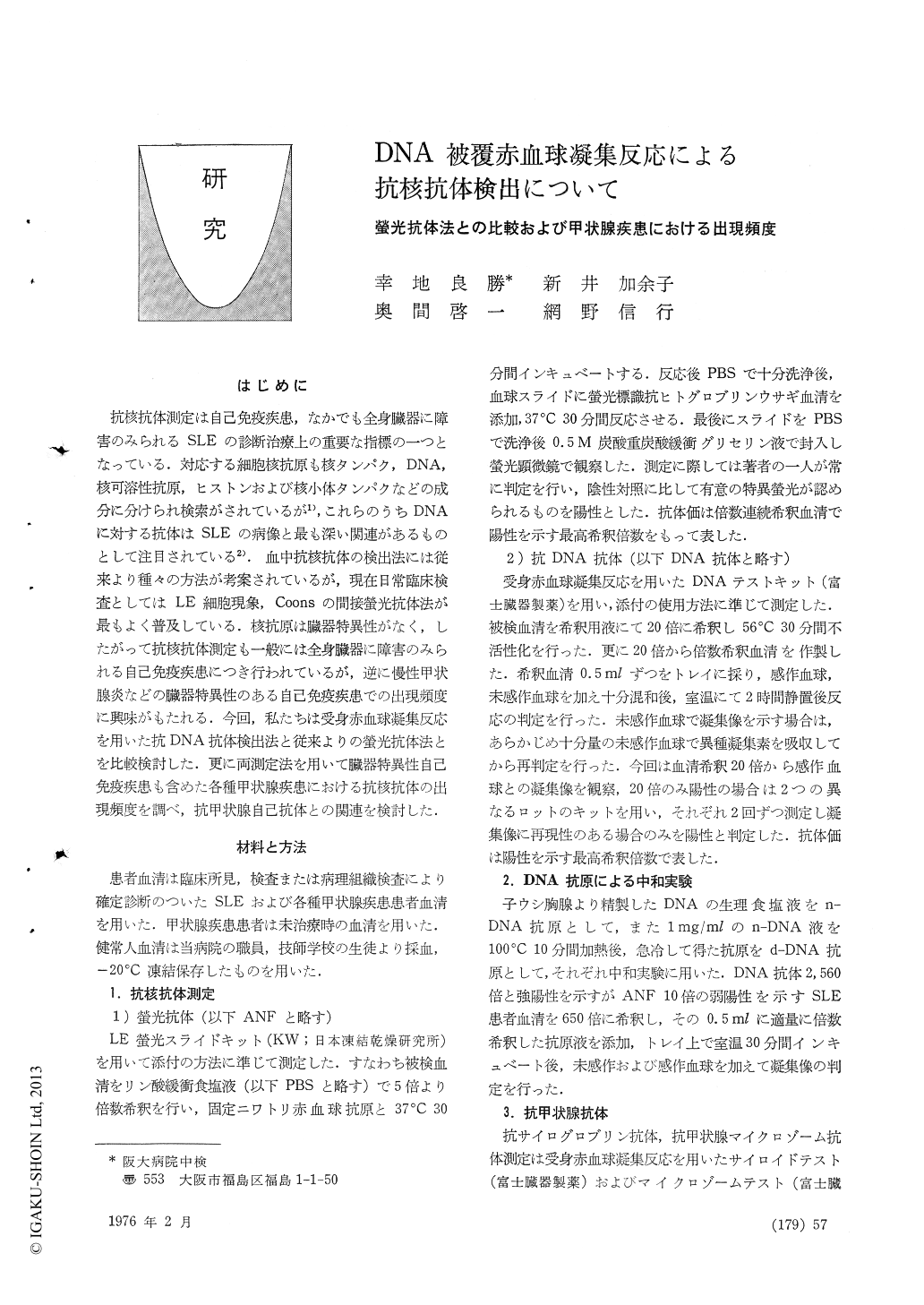
Copyright © 1976, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


