『医学常識』
ガンのvirus説
豐川 行平
1
1東京大学衛生学
pp.171-173
発行日 1957年6月15日
Published Date 1957/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542905347
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
ガンは一体どうしてできるのだうろか。これは誰もがもつ疑問だろう。1882年ドイツのCohnheimはその病理学総論講義にガン成立に対し迷芽説という考えを発表している。それによると,個体発生の途中で異常が起って,一見正常と見える組織や臓器の間に未分化の細胞がまぎれこんでいて,それがある時期にガンの形で発育してくるというのである。事実,人体や動物体の組織をよく調べてみると,そういう迷入した細胞の塊りを発見できることがある。Cohnheimの考えは組織畸形を出発点としているが,これに対し,正常な組織細胞が何かの原因でガン細胞にかわり,それがガンとして発育するという考えがある。では一体どちらの考え方が正しいかという問題になるが,まず前者の迷芽説には2,3の欠点がある。1つは,発ガン物質による実験成績と矛盾する点である。発ガン物質を作用させると,どこにでもガンが発生する。もしCohnheimの考え方であれば,どこにも迷芽があるということでなければ説明できないわけで,これは考えにくいことだからである。もう1つは迷入した細胞はそのままではガンにならない。それがガンとして発育するためには何かの原因が作用しなければならないわけだが,そういう原因を考えるなら,あえて迷入細胞というものを考えなくてもよいではないかという点である。現在では,Cohnheimのいう迷入細胞からもガンができることもあるかもしれないが,大部分は正常細胞か何かの原因でガン紬胞にかわって,それがガンとして発育するのだろうと考えられている。では,正常細胞をガン化させるものは何か。
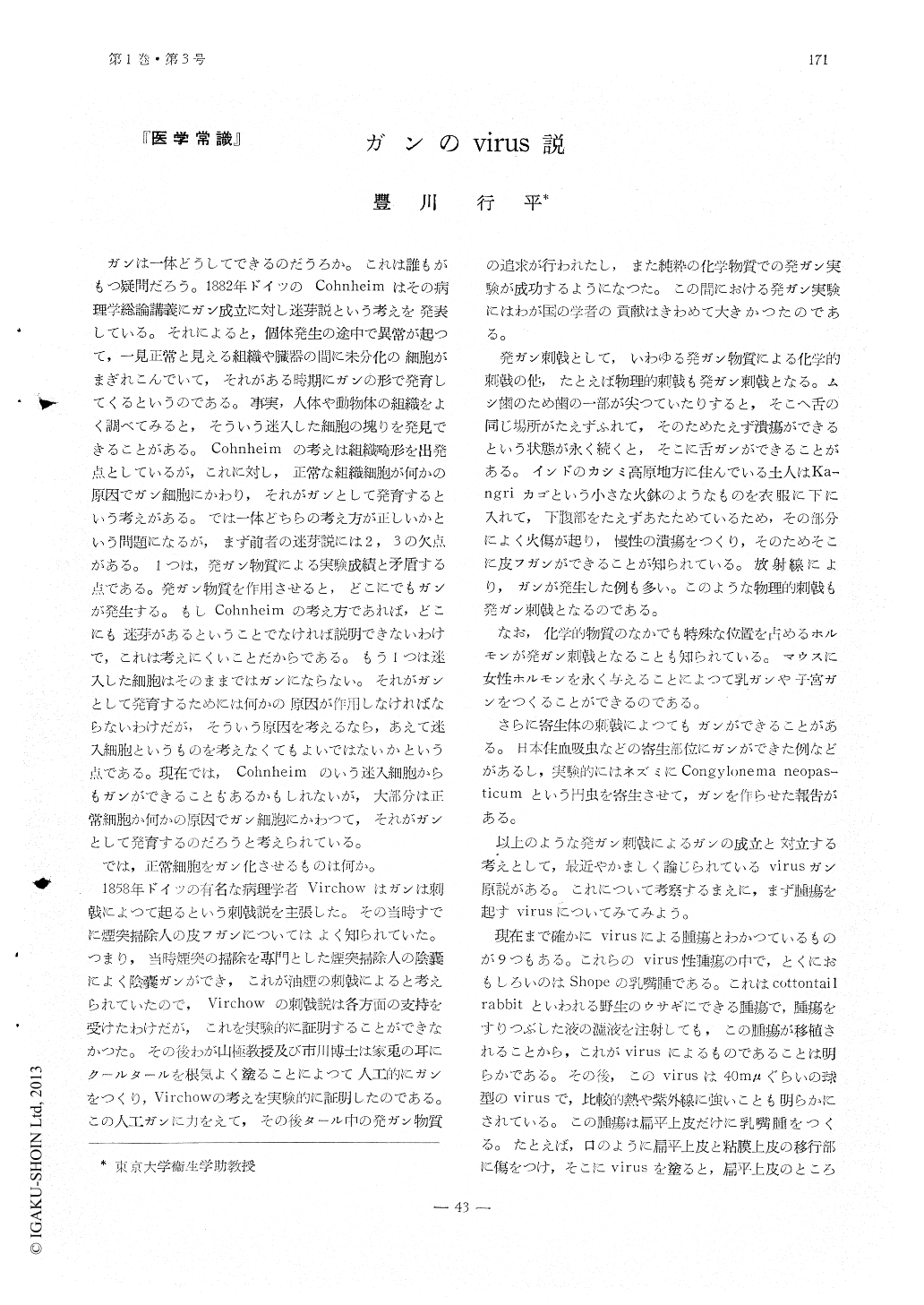
Copyright © 1957, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


