- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
リンパ節に対する穿刺吸引細胞診はGuthrie(1921)によって始められたとされる。これが1950年代になって北欧を中心に急速に普及した(Soe-derstrom,Franzen,Carduzo)。本邦では1970年前後に,甲状腺で鳥屋,前立腺で竹内らにより導入され,順次,他臓器に適応が拡大された。最近では体表近くのみではなく深部臓器に対しても,X線テレビ透視,超音波エコー(US),CT,MRI,その他の各種造影法の助けをかりて安全に施行されている。
一方,頭頸部領域においても画像診断の進歩はめざましく,頸部リンパ節の性状を評価する上にも欠かせないものとなっている。これは同時に頸部リンパ節を検出するsensitivityを飛躍的に向上させた。しかしながら,US,CT,MRIに関する限り,良性のものと転移性のリンパ節を鑑別することは原則的に不可能である。したがって,sensitivityが向上する一方では,転移性疾患などの診断におけるspecificityが低下する運命にある。すなわち画像診断では,偽陽性,偽陰性の率が高い点が問題である。たとえば,触診では25%前後の偽陽性率が報告されているが,CTにおいても偽陽性率は20%前後,偽陰性率は30%もあるとされている1)。ここに画像診断に組織診断,なかでも簡便に行える穿刺吸引細胞診(FNA)を併施する大きな意義があるといえる。しかしながら頭頸部領域においてもFNAが困難な場合もあり,細胞学的診断のみでは足りない場合もあり,また播種の危険性も完全には否定できないのが現状である。ちなみに著者は15年ほど前に,シルバーマン針による甲状腺の組織診断を積極的に行っていた時期があるが,この間に2例の筋肉内播腫を経験している。FNAでは穿刺針のゲージが細いので安全であるとされているが,著者としては後述する通り,未だ全幅の信頼をおききれない現状である。頭頸部領域におけるFNA,特に頸部リンパ節腫瘤に対しての役割と問題点を,最近2年間の自験例の検討も併せ述べる。
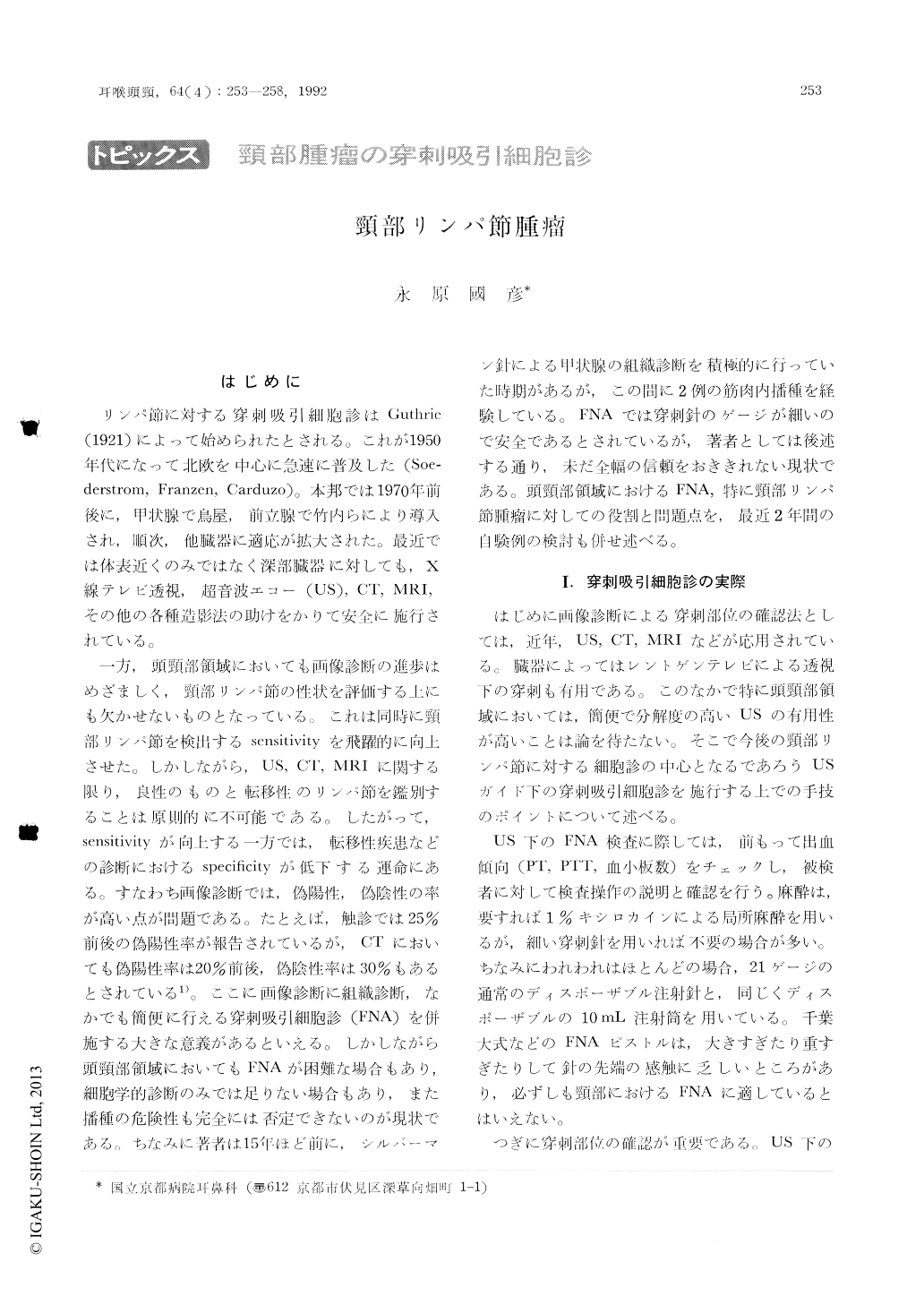
Copyright © 1992, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


