- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
一般臨床医が手を出したがらない眼科手術の1つが緑内障の濾過手術である。理由はいくつかあって,もともと視機能が改善する手術でないこと,術後が面倒なこと,気難しい患者さんが少なくないことなど人によって意見はさまざまだが,「マニュアル化しにくい細やかな術後管理が必要であり,主治医班のチーム医療としての質が結果を左右するから」というのが大きな理由の1つである。例えば,濾過胞の充血が強くなってきた,圧迫したら前房が浅くなるようだ,昨日まで低眼圧だったのに今日は眼圧が上がっている,など術眼が刻々と発するサインを見逃さず,主治医班の一人ひとりが同じように危機感を持てないと,治療のタイミングを逸してしまう。その結果,「手術終了時は理想的と思っていたら,もう術前の眼圧レベルになってしまった……」となる訳である。数年ごとに自分の施設の治療成績を出して他施設の報告と比べ,どこが劣るのか,何が足りないのかをセルフ・アセスメントすること,そして他施設の専門医と交流をもって日々新しい情報を入れていくことが,チーム医療の質を維持,向上させる唯一の方法である。ところが,治療成績というのが曲者で,「術後1か月での眼圧が15mmHg以下」という基準で評価すれば,うまく濾過量を調節できる術者が手術すれば術後成績に差が出ないかも知れないが,もし「1年後に12mmHg以下」という基準で区切るとすれば,入院中は低眼圧スレスレの低空飛行で管理するくらいでないと,ハードルをクリアするのは相当に難しい。
この数年の間に,プロスタグランジン製剤が登場し,選択的レーザー線維柱帯形成術(selective laser trabeculoplasty)など新しい治療機器が開発され,緑内障治療全体における観血的治療の守備範囲は少し狭まった感がある。さらに,濾過胞感染などの晩期合併症に対する関心が高まっている今日では,いかなる症例が濾過手術でなく,流出路再建術でカバーできるのか模索されている。したがって,ほんとうに濾過手術が必要な症例にわれわれが求めるのは,21mmHgを切ることではなく,12mmHg以下あるいは一桁といった,より低い目標眼圧をねらうことである。本稿では,そのような意味で濾過手術のスタンダードとなりつつある,マイトマイシンC(MMC)併用tight-suture trabeculectomy(術後レーザー切糸術併用)1,2)について,術後早期(主に入院中),術後中期(1年以内,主に3か月以内),術後後期(術後数年)に分けて,代表的な術後合併症に対する管理の要点と効果の判定についてまとめる。
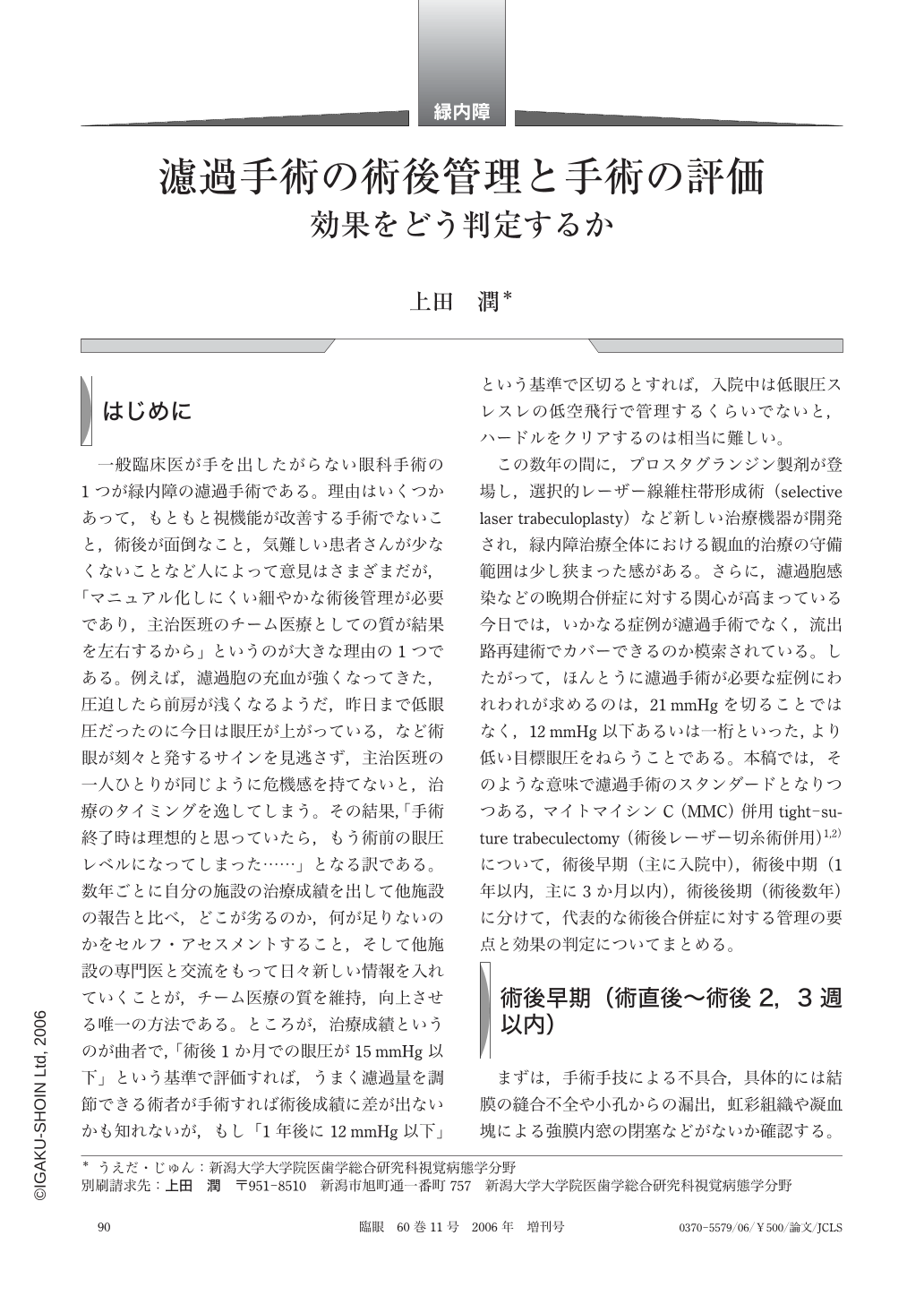
Copyright © 2006, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


