今月の臨床 早期子宮頸癌--今日の焦点
組織診の要点と問題点
山辺 徹
1
Tooru Yamabe
1
1長崎大学医学部産婦人科教室
pp.63-67
発行日 1968年1月10日
Published Date 1968/1/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409203828
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
従来,病理学者が早期癌として取扱つてきたものは,Borst以来提示された癌の条件—すなわち,間質への癌細胞の破壊性浸潤—がみとめられるものでなければならなかつた。したがつて本質的には進行癌と同様の組織像を呈するものであり,ただ浸潤の程度が僅少であるにすぎなかつた。しかしながら,これまで見落されていたさらに初期の癌,つまるところ,いまだ上皮内に癌細胞が限局して増殖し,間質内浸潤を開始する前の時期があるはずであると考えられるようになつた。このような状態が上皮内癌と呼ばれる病変であり,今日では子宮頸部における早期癌研究の焦点が上皮内癌に集中されてきつつある。このことは病理学的な興味のみでなく,臨床的に上皮内癌の治療法が一般に子宮単純全剔術で十分であり,したがつて岡林式広汎性全剔術後にみられるような後遺症を考慮する必要がないためでもある。
上皮内癌の定義は一応確立されているかのようであるが,上皮内癌が記載されてより半世紀を経た今日なおその本態,組織発生あるいは判定基準について未解決の問題が多く残されている。しかしながら,その基準と見解がたとえ統一されたとしても,検鏡に際して所見の判読が人によつてある程度差のあることが上皮内癌の組織診断における最大の問題点であると考えられるが,これは形態学としての宿命であるかもしれない。
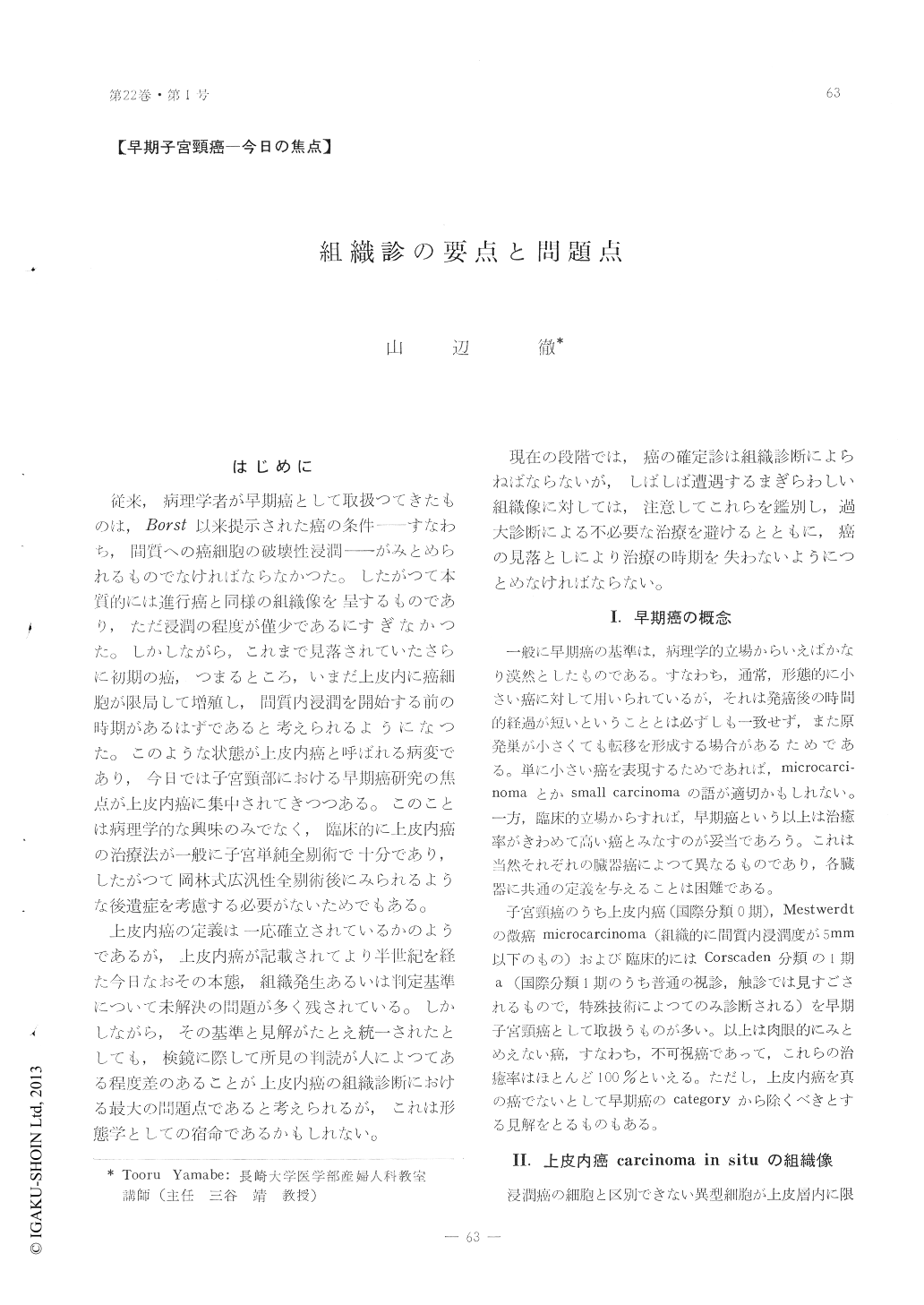
Copyright © 1968, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


