特集 新生児の臨床検査
出血性素因について
吉岡 慶一郎
1
Keiichiro Yoshioka
1
1奈良医科大学小児科教室
pp.867-873
発行日 1966年11月10日
Published Date 1966/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409203582
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
新生児期,ことに未熟児においては生後数日間しばしばメレナ,吐血,臍出血,頭蓋内出血,肺出血等の各種出血傾向を示し,そのうち肺出血,頭蓋内出血は直接新生児死亡の原因となる重篤な疾患である。先天性出血性素質や二次的原因によらないこれら一群の出血性疾患は新生児出血症,He—morrhagic disease of the newborn (Townsend),Morbus haemorrhagicus neonatorum (Salo—monsen)と呼ばれ,その出血傾向の成因は単一ではないが,主役を演ずるのは新生児期のプロトロンビンを始め,各種の凝固因子の低下による生理的凝固障害であり,これに分娩時の外力,anoxiaに基因するうつ血,毛細血管障害等が加わつて発生すると考えられる1)。一方血友病,無フィブリノゲン血症等の先天性出血性素質が新生児期に発症し,臍帯出血,メレナ等の出現することがある。この場合,新生児期の凝固障害の他に該当する単独因子の欠乏がある。また新生児血小板減少症,あるいは続発性の血小板減少症,凝固障害もある。これら各種の出血はその成因により治療法,予後を異にするので,その病態を知るために凝固能,血小板能等の検索が必要であり,特に凝固能に関しては個々の凝固因子を定量測定することが望ましい。しかしながら一方新生児は採血困難であり,確実に材料を得られないことが多い。
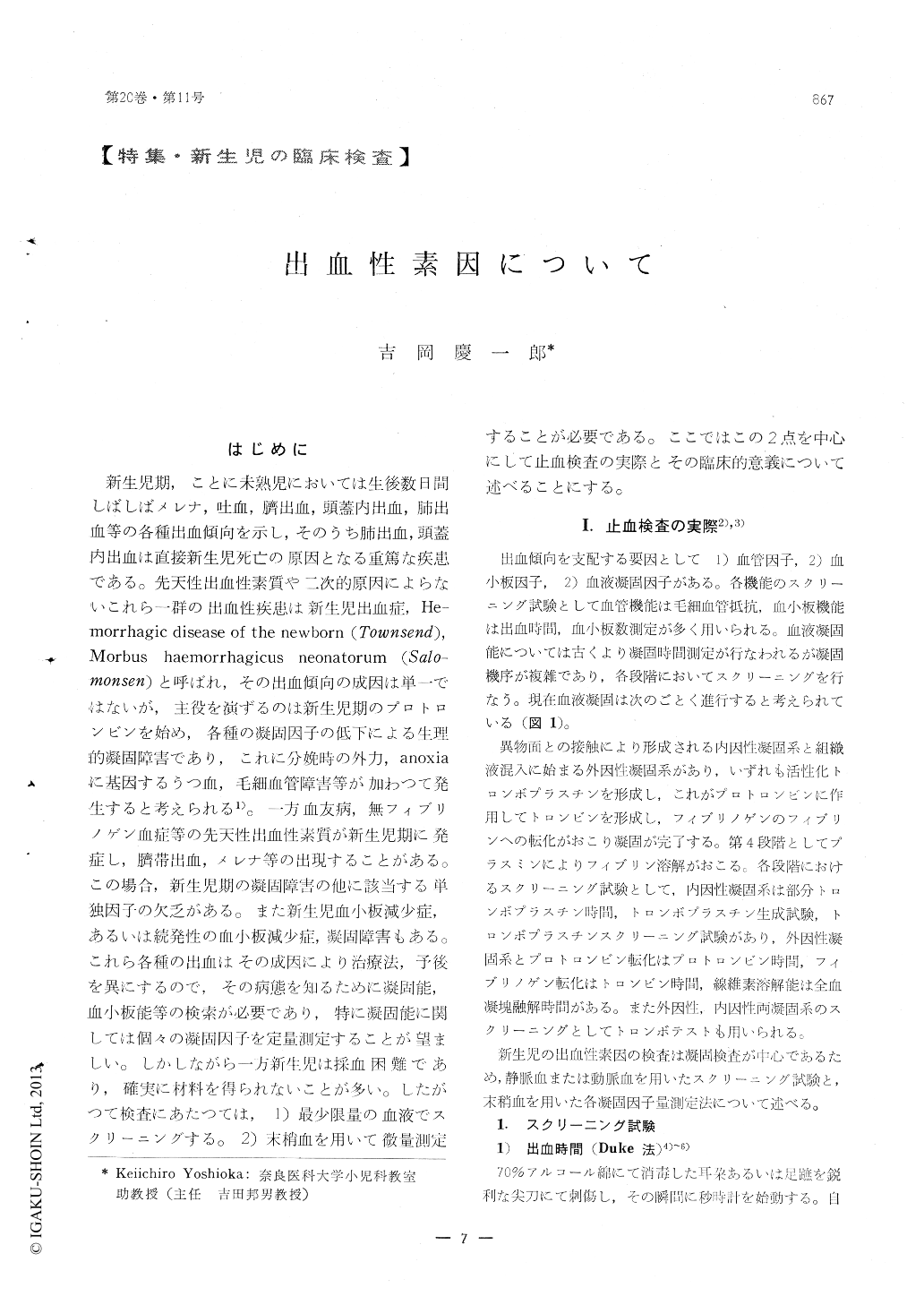
Copyright © 1966, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


