- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに1)
ピル(経口避妊薬)は,1960年に米国で初めて市場に出るが,当時は避妊効果発現機構や副作用の詳細が現在ほど明らかではなく,排卵抑制を確実にし,服用中の破綻出血や無月経の出現をなくすために,性ステロイド剤(エストロゲン+黄体ホルモン剤)の含量の多いものが用いられた.その結果,2/3は悪心,嘔吐の副作用のため中断した.また副作用が明らかとなり,強力な新しい合成ステロイド剤が開発され,1964年には含量の少ないピルが作られた(中用量ピル).エストロゲンとしてメストラノールはエチニルエストラジオール(EE2)へ代謝され作用し,黄体ホルモン剤にはノルエチンドロンに代謝され作用するものもあり,これらの代謝に個人差(効果差)が生じる.また,エストロゲンや黄体ホルモン剤は血栓性塞栓症のリスクがあるため,日本では1996年以降,エストロゲンとしてEE2,黄体ホルモン剤としてプロトタイプや新規開発したものを用い,含量を減らし,1~3相性の排卵抑制や月経出現を確実にした低用量ピルが市場に出た.
ピルは,エストロゲンは含量を相対的に多くすると子宮内膜を増殖させ月経過多にするため,用量を少なくし,黄体ホルモン剤(抗エストロゲン剤)の作用を相対的優位にするように作られている.そのため,エストロゲン作用(細胞増殖)に対しては抑制的であり,残りは黄体ホルモン剤の作用とその構造に由来するアンドロゲン作用(微量)が出現する可能性がある.そのため,エストロゲンにより増殖性の強い子宮内膜,多くの因子により細胞増殖・分化をコントロールされる乳腺や肝細胞・子宮頸部腺上皮・下垂体前葉,そのほかに子宮筋や子宮頸部扁平上皮,またピルによる排卵抑制が起こる卵巣があり,エストロゲンや黄体ホルモンのレセプター機序の存在とも関係し,ピルの癌への作用が異なる.
ピルに使用されるステロイド剤,特にエストロゲンは癌のイニシエイターでなく,プロモーターと考えられ,あるとするなら,腫瘍効果は使用期間と関係し,用量依存性である.
ピルは40年以上使用され,前方視的,後方視的に疫学調査が腫瘍発生との関係においてなされてきた.生殖期初期にピルを服用した高齢女性はまだいないので,調査は60歳以下の女性に限られることになる.日本でのピル服用者は少なく,避妊のためのピル服用者は対象の数%に過ぎず,十分な疫学調査が行われず,ピル使用頻度の高い諸外国の調査の総説2)を参考にせざるを得ない現状がある.
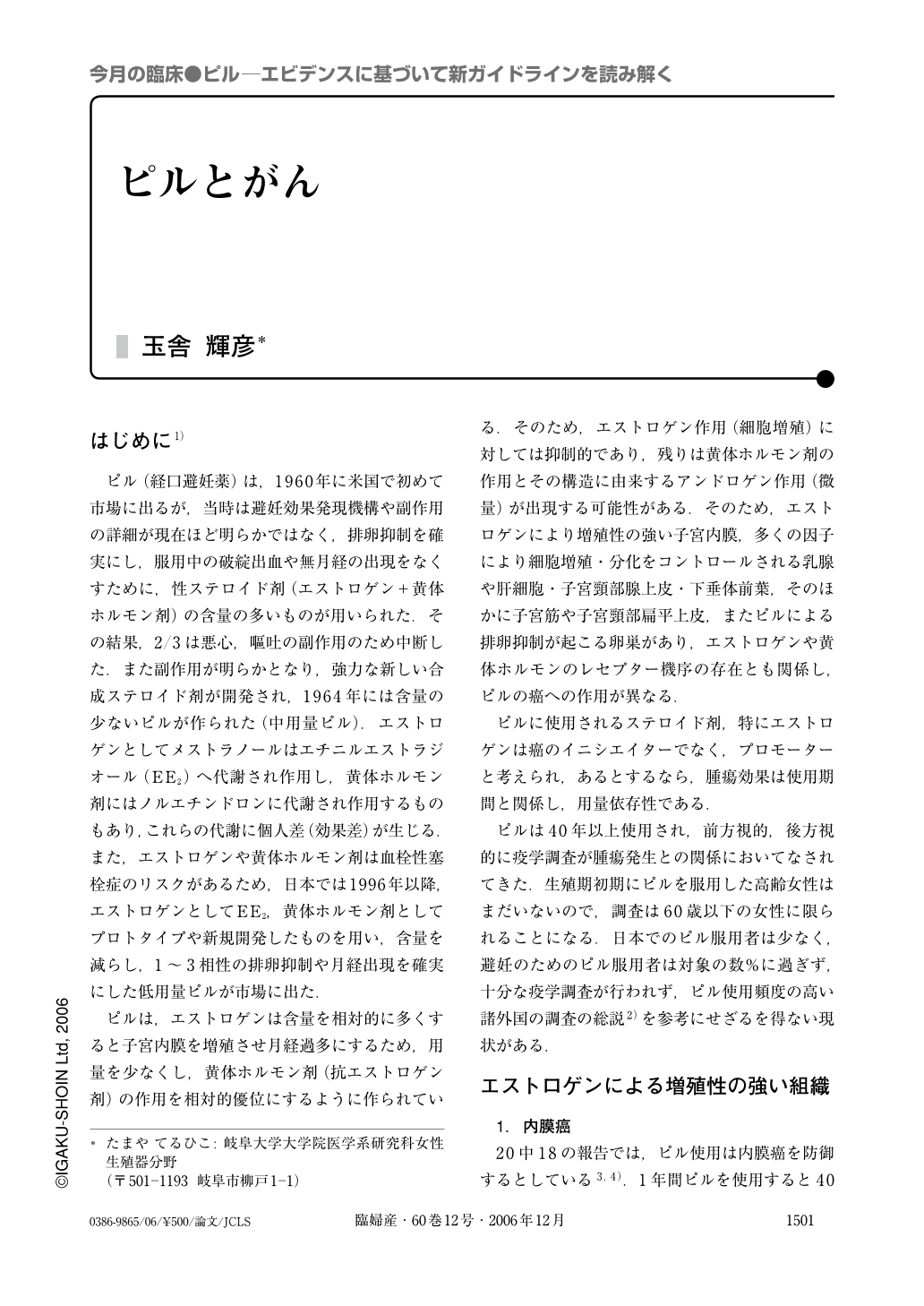
Copyright © 2006, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


