Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.はじめに
パーキンソン病の主症状は①振戦,②筋固縮,③無動,④姿勢・歩行障害の4つである。以前は振戦,筋固縮,無動を3大症候とよんでいたが,近年治療に対する反応や研究から,姿勢障害を独立した症状と考えるようになった。これらの主症状はすべて運動症状である。そして①パーキンソン病は頻度が多く,病期の各進展段階における患者を数多く検索出来ること,②黒質線条体ドパミン系の比較的限局した病変が多くの症状の原因と考えられ,ドパミン作動薬によりこの系の機能レベルを可逆的に変え得ること,③知能低下が少ないために,ある程度複雑な検査が施行出来ること,などヒトの生理学的実験研究を行う上で適当な条件がそろっていることから,疾患固有の病態を解明するのみでなく,正常の基底核機能を解明するための良い対象として多方面から研究が重ねられてきた。
近代的な計測法を用いたパーキンソン病の運動異常の研究は,まず動作緩徐に関して随意運動を対象に多く行われてきた。一方1980年代に入り,認知機能や概念の切り換え能力など本病の知的機能が注目されるようになり,前頭葉機能あるいは皮質下性痴呆の観点から,神経心理学的知見が重ねられている。
ヒトの行動,あるいは限局した時間内の運動は,すべて外的刺激や内的な動機に基づく運動としてとらえられる。そのような立場に立てば,通常行われるヒトの運動の実験がおおまかに刺激の認知と反応から成り立つものであることを考え,その全過程を考慮して実験をすすめることは当然必要なことであろう。パーキンソン病の運動の研究は,初期の段階では運動の出力の障害のみに注目されてすすめられたが,近年は刺激の認知や処理の過程も実験に組み込まれるようになった。その結果刺激の認知に影響する各種の要因も研究の対象となり,現在は運動と知的機能をあわせてパーキンソン病の脳機能異常と症状を理解すべき段階に立ち至っている。簡単に考えてみても,注意や努力の保持など前頭葉機能にかかわる精神状態は運動の発現に当然影響するであろうし,過去のいくつかの運動実験の結果にそれらは反映されている。
現在までに重ねられた知見は我々がまだ基底核や前頭葉の機能の理解のとば口に立ったのみであることを示しているが,それらのうち主なものを今後の研究の方向を念頭において要約したい。なおパーキンソン病の主症状のうち振戦については1960〜70年代に多くの知見が重ねられ(Desmedt,1978参照),姿勢・歩行異常については古くGerstmannとSchilder (1926)が提唱した,歩行失行との関連を含めて興味深いテーマであり近年いくつかの知見も重ねられているが(Martin,1967;田幸と柳沢,1988;上野,1989),本稿の枠を越えるのでここではふれないのでそれぞれの文献を参照していただきたい。
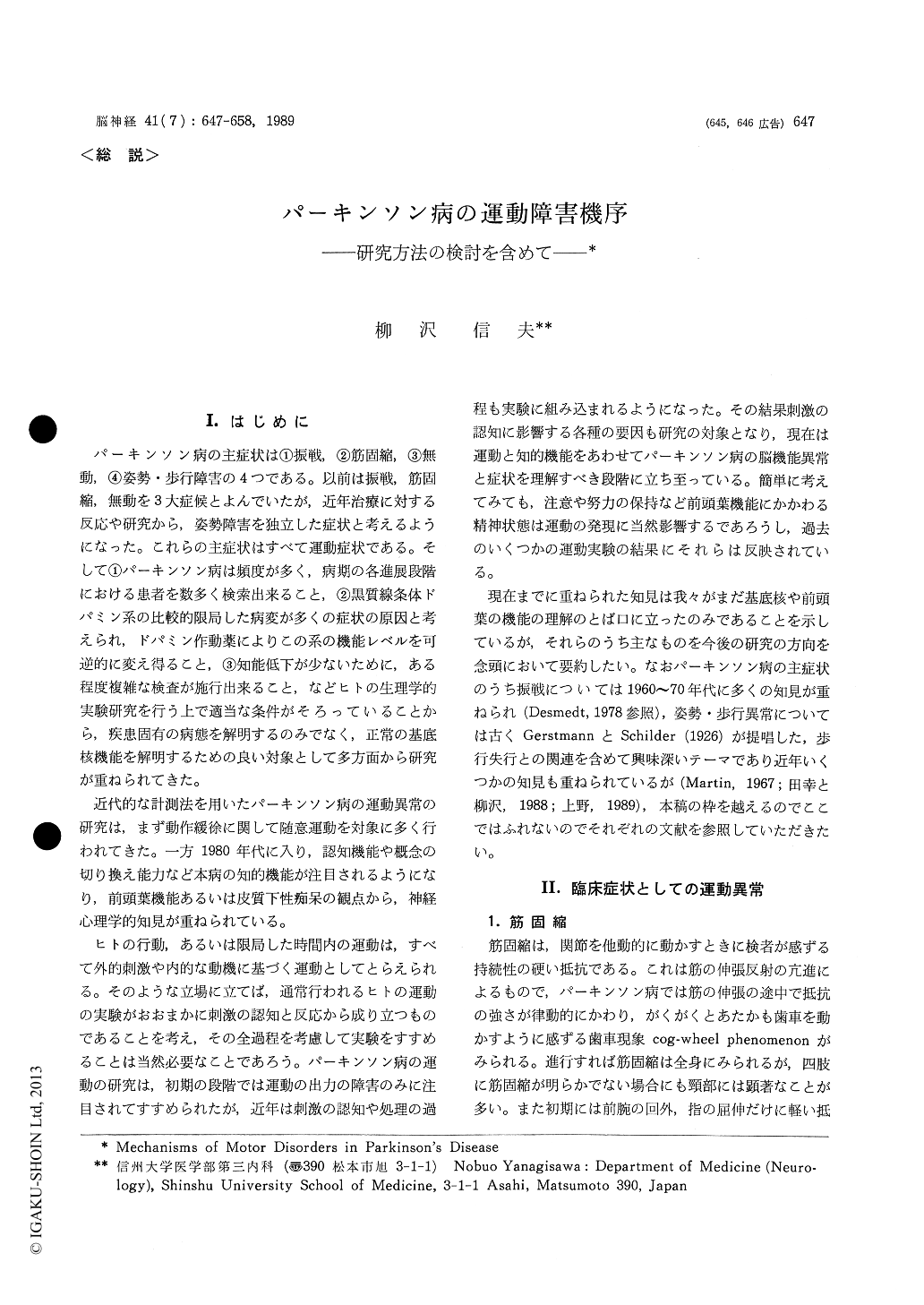
Copyright © 1989, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


