Japanese
English
展望
内因性精神病の生化学(2)
The Biochemistry of Endogenous Psychoses (2)
大月 三郎
1
,
秋山 一文
1
Saburo Otsuki
1
,
Kazufumi Akiyama
1
1岡山大学医学部神経精神医学教室
1Department of Neuropsychiatry, Okayama University Medical School
pp.616-625
発行日 1988年6月15日
Published Date 1988/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405204529
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
Ⅲ.躁うつ病
1.躁うつ病の生化学的研究の動向
躁うつ病のカテコラミン仮説,セロトニン仮説の基になったのは,抗うつ薬の薬理作用であろう。今日では,三環系抗うつ薬に代表される抗うつ薬の治療効果はその主な急性薬理作用であるモノアミンの再取り込み阻害では説明できないと考えられている。その主な理由として,①抗うつ薬の投与開始から臨床効果発現までに2,3週間要すること,②モノアミンの再取り込みを阻害するcocaineは抗うつ効果がないこと,③臨床効果のある抗うつ薬でモノアミン再取り込み阻害能を有しないものがあることなどがあげられる。抗うつ薬の抗うつ効果の作用機序の研究焦点はモノアミン受容体機能に関するものに移っている。
躁うつ病の病態にかかわる生化学的変化についても,単純なモノアミンの増減だけを問題にする研究方向は体液研究の成果の不一致などより既に限界であり,受容体の感受性の変化を取り上げていく動向にある。研究手段もかつての体液中のモノアミン及びその代謝産物の測定から,血小板の受容体や神経内分泌学的試験(Dexamethasone suppression test(DST),TRH Test),中枢受容体に選択的な薬物負荷後に神経内分泌的反応を測定することにより間接的に中枢受容体の感受性をとらえようとする方法などに変わりつつある。冒頭にも触れたように,このような臨床的研究を行う際に注意しなければいけないことは疾患の生物学的異種性である。躁うつ病では,単極型うつ病と双極型うつ病との間で遺伝負因,初発年齢,治療への反応性に相違があるといわれ,生化学的変化もそれぞれの型に対応するものを区別していく必要がある。
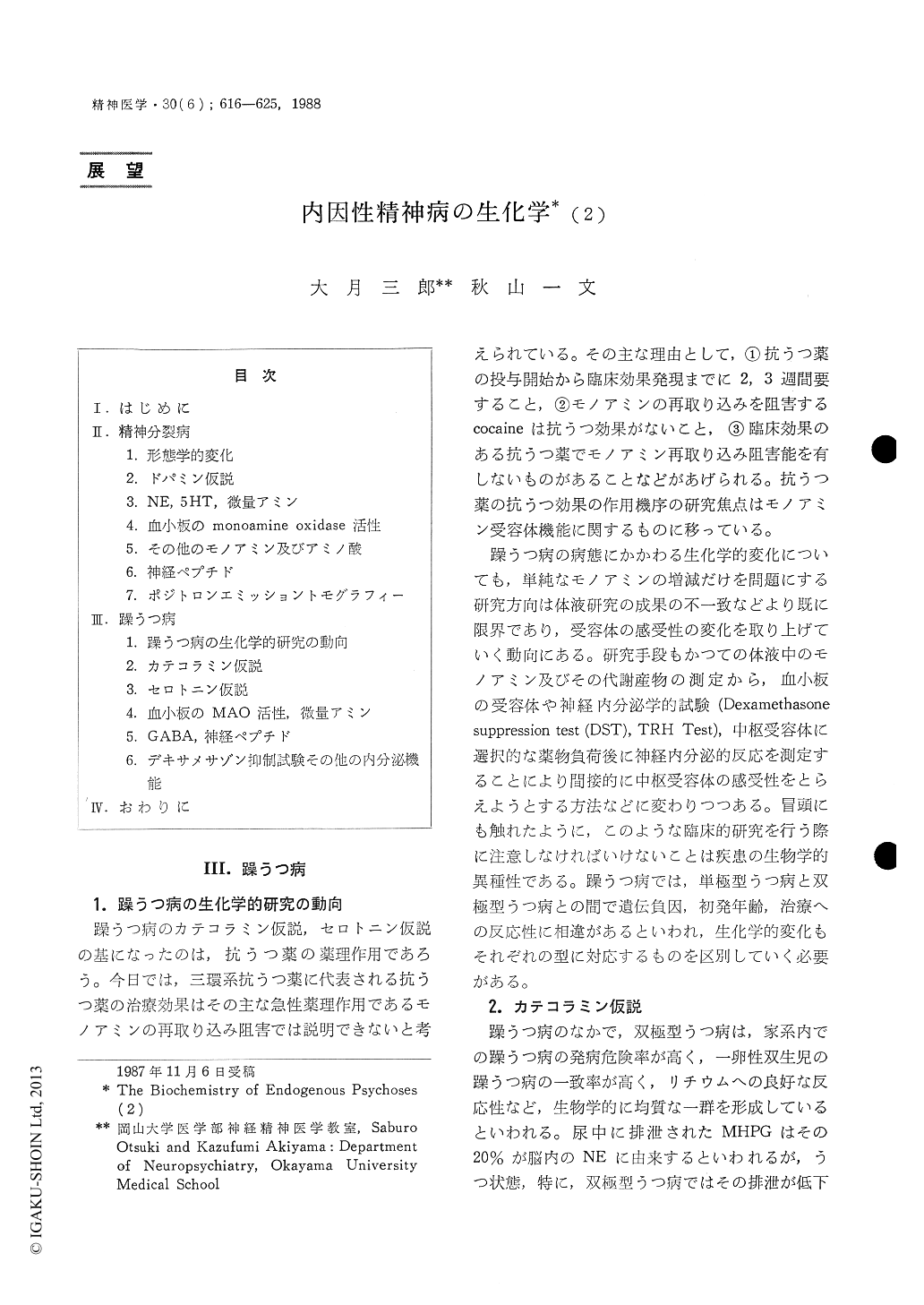
Copyright © 1988, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


