Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
かつて日本のお家芸とまで言われたマラソンであるが,ケニアやエチオピアなどアフリカ勢の台頭で日本人のメダル獲得が脅かされる現状となっている.その要因については評論家の方々に譲るが,国内の競技人口の減少がその要因ではないことは容易に理解できる.2008年4月から特定健康診査(いわゆるメタボ健診)が開始され,国民のメタボリック症候群に対する関心が高まっている.スポーツは減量や健康維持の手段として用いられ,ランニングやウォーキングは特別な道具を必要とせず,シューズさえあれば始められるために愛好者が多い.実際,筆者の医学部時代の同級生がマラソン大会に参加したという連絡をくれることがあり,市民ランナーの増加を感じる.また,各地で開催されているマラソン大会には日頃の練習成果を発揮しようと,多くの市民ランナーが参加している.美ジョガーと呼ばれる女性ランナーも出現し,そのファッションに対する注目も集まっている.また,様々な携帯端末を使って,走行距離を自動計測して管理することができるようにもなっている.その一方で,練習中の市民ランナーのマナー違反も指摘されており,社会問題の一つになっている.
現在,日本国内で行われているマラソン大会,ロードレースは,1年間に2,000を超えている.大会参加に際しての健康状態の管理は各自に任されているため,医師の判断を仰がずに参加していることもありうる.事実,筆者が以前勤務していた病院の外来で,重症の狭心症患者から「この前の東京マラソンも完走できましたから元気ですよ」という言葉を耳にし,大変驚いた経験もある.参加者が多くなればなるほど,レース中の心肺停止例も発生することがある.
2004年7月1日より一般市民でも自動体外式除細動器AEDを使用することができるようになった.日本国内のマラソン大会において心肺停止状態の人にAEDを使用して救命されたのは,2005年2月の「第12回泉州マラソン」が最初である.AEDによる救命事例については,最近ではマスコミなどでもあまり報道されなくなっており,その情報入手は困難となっている.ロードレースにおける心肺停止例に関して日本陸上競技連盟(日本陸連)には事故報告書という形式で報告されていたが,傷病者の既往歴や転帰についての情報は記載されておらず,またそれらの情報を集積するシステムも構築されてはいなかった.
本稿では,ロードレース中の突然死の現状,日本陸連の突然死防止への取り組み,日本最大のマラソン大会である東京マラソンの救護体制や同大会での心肺停止例を紹介し,ロードレースにおける心肺停止例に対する日本陸連医事委員会の調査について概説する.そして最後にロードレースにおける心肺停止の特徴について検討する.
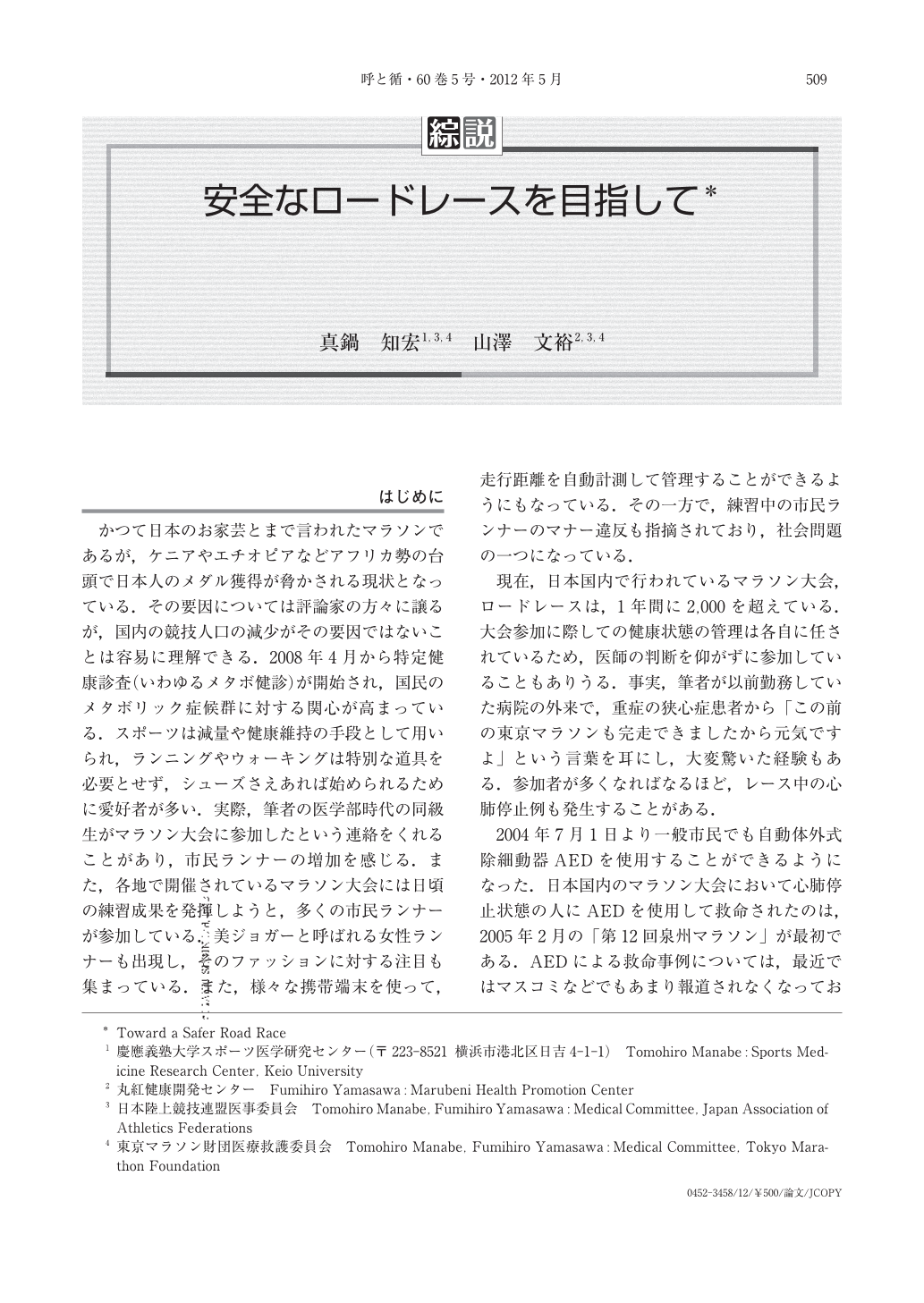
Copyright © 2012, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


