Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
心臓移植後の拒絶反応には,T細胞主体の細胞性拒絶反応とB細胞主体の抗体関連型拒絶反応(antibody-mediated rejection;AMR)がある.また,心臓移植後には冠動脈内膜肥厚の進展が一定の割合で認められ,移植後2年以上経過した患者にとって主たる死亡原因ないし再移植を必要とする原因となっている1).移植後冠動脈病変の発生要因には動脈硬化促進危険因子のみならず免疫学的機序も関与するため,従来から慢性拒絶反応と称されてきた.
心臓移植後の拒絶反応の診断方法はいまだ心筋生検による病理組織診断がゴールドスタンダードである.非侵襲的診断法の開発への努力はかねてから行われており,近年では末梢血ゲノム解析による手法が多施設共同研究として行われた〔Multicenter Cardiac Allograft Rejection Gene Expression Observation(CARGO) study〕2).しかし,各種報告されている生検に代わる非侵襲的診断法の信頼性については今後の報告を待つ必要がある.
細胞性拒絶反応に関しては,国際心肺移植学会の定めるgrading systemに照らして診断が行われる3).1992年に定められた基準3)は,臨床現場での治療必要性を考慮し,より簡便化することで施設間での相違を軽減しデーターベース作成を簡易にする目的で2005 年に改変された(表1)4).多くの施設では1992年基準でのGrade3a以上のみ(2005年基準Grade2R以上)を治療対象とする.しかし,次に述べるAMRの可能性を否定できない場合や組織上の細胞性拒絶反応の所見がなくとも患者が心不全症状を有する場合や,心エコーにて心筋浮腫や拡張障害などの変化を呈する場合などは拒絶反応としての治療を行うことが多い.
AMRに関しては,従来病理組織診断は困難とされ,抗ドナー抗体値の陽転化や血行動態変化などの臨床所見を主体として治療を開始する場合が多かった.当初,AMRはhumoral rejectionと呼ばれ,1992年には「リンパ球浸潤等細胞浸潤の所見を認めない血管炎ないし重篤な浮腫,あるいは免疫蛍光測定法での陽性所見」とされ,2004年に初めて病理診断基準が検討されAMR0,ないしAMR1として有無を付記することが提唱され,2006年にはその病理診断基準が明文化された(表2)5).
表2に示すごとく,本基準は①移植心の急性機能不全の所見を前提とし,②H-E染色による内皮細胞の腫大・傷害・脱落ないしは毛細血管内のマクロファージの充満所見のいずれかが必要で,③免疫病理学的所見として毛細血管壁への免疫グロブリンないし補体の沈着あるいは毛細血管内へのCD68陽性が必要で,④HLA抗体や他のドナー抗体の血清学的証拠を補助とするものであった.
しかし,近年,各種臓器移植領域においてAMRへの注目に伴い,移植後早期のみならず慢性期AMRの及ぼすグラフト機能・予後への影響に対する取り組みが盛んに行われ,免疫組織学的進歩・蛍光抗体法の進歩も相まって,さらに本基準を臨床現場に即したものに改訂・再検討しようとの動きが高まってきた.
本稿では,2004年の上記病理診断基準提唱より5年を経て,2009年8月カナダ・バンフにて開催された第10回国際移植病理学会にて検討された項目を中心に,当院にて経験した心臓移植後にAMRを来した患者の病理診断につき解説する.
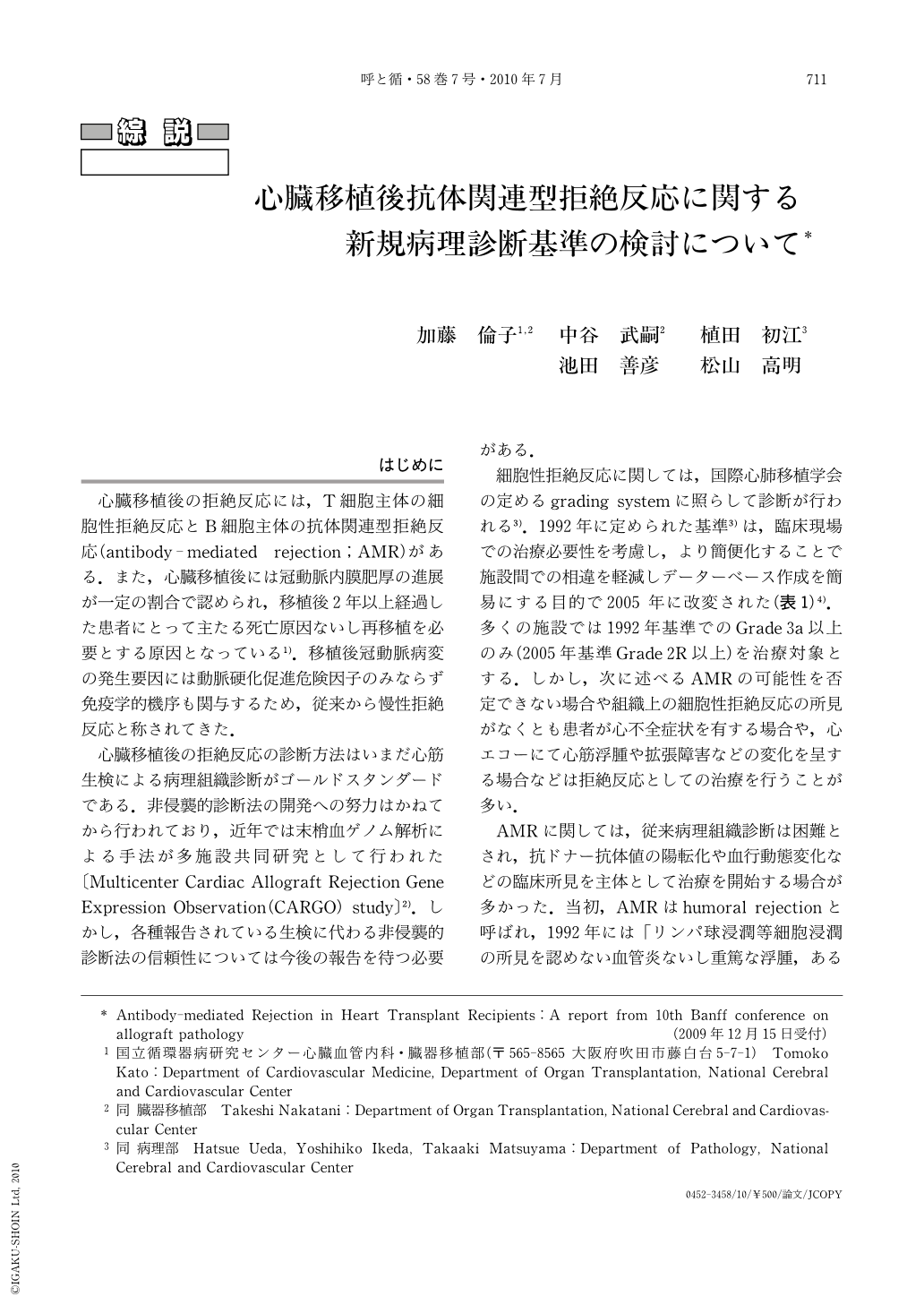
Copyright © 2010, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


