特集 出生前診断
出生前診断をどうとらえるか
玉井 邦夫
1,2
1公益財団法人日本ダウン症協会
2大正大学人間学部臨床心理学科
pp.172-175
発行日 2014年3月15日
Published Date 2014/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401102966
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
2012年8月に突然にも感じられる形で新聞報道が行われた新型出生前診断(無侵襲的出生前遺伝学的検査non-invasive prenatal testing;NIPT)は,13,18,21トリソミーを検出対象としていたことから,筆者が代表理事を務める公益財団法人日本ダウン症協会(Japan Down Syndrome Society;JDS)は「当事者」として否応なく論議に巻き込まれることになった.出生前診断/検査が,確定診断に至るものの母体と胎児への侵襲性が高い技術から,判定が確率に留まるものの侵襲性の低いものに「進歩」していくという流れはそれまでにも一貫していた技術の変遷動向であり,NIPTもその流れに位置づけられる.
JDSは,母体血由来で胎児の遺伝学的情報を取得する技術が登場すること自体については,報道の1年以上前から日本産科婦人科学会などの主催するシンポジウムなどでの情報から把握していたが,NIPTをめぐる議論の推移はメディアによる報道のあり方に大きく影響されることで,JDSにとっては「騒動」とでも呼ばざるを得ないような様相を呈した.
筆者はあくまでもJDSという団体の人間であり,医療従事者でも遺伝学研究者でもない.しかしながら,30年以上にわたって臨床心理士として虐待やDV(domestic violence)といった,ある意味では人間の「生死」に及ぶ事象に取り組んできたという事情もある.本稿では,当事者団体という立場と,生業である臨床心理学という立場から,NIPTをめぐる議論について考えるところを述べさせていただくことにする.
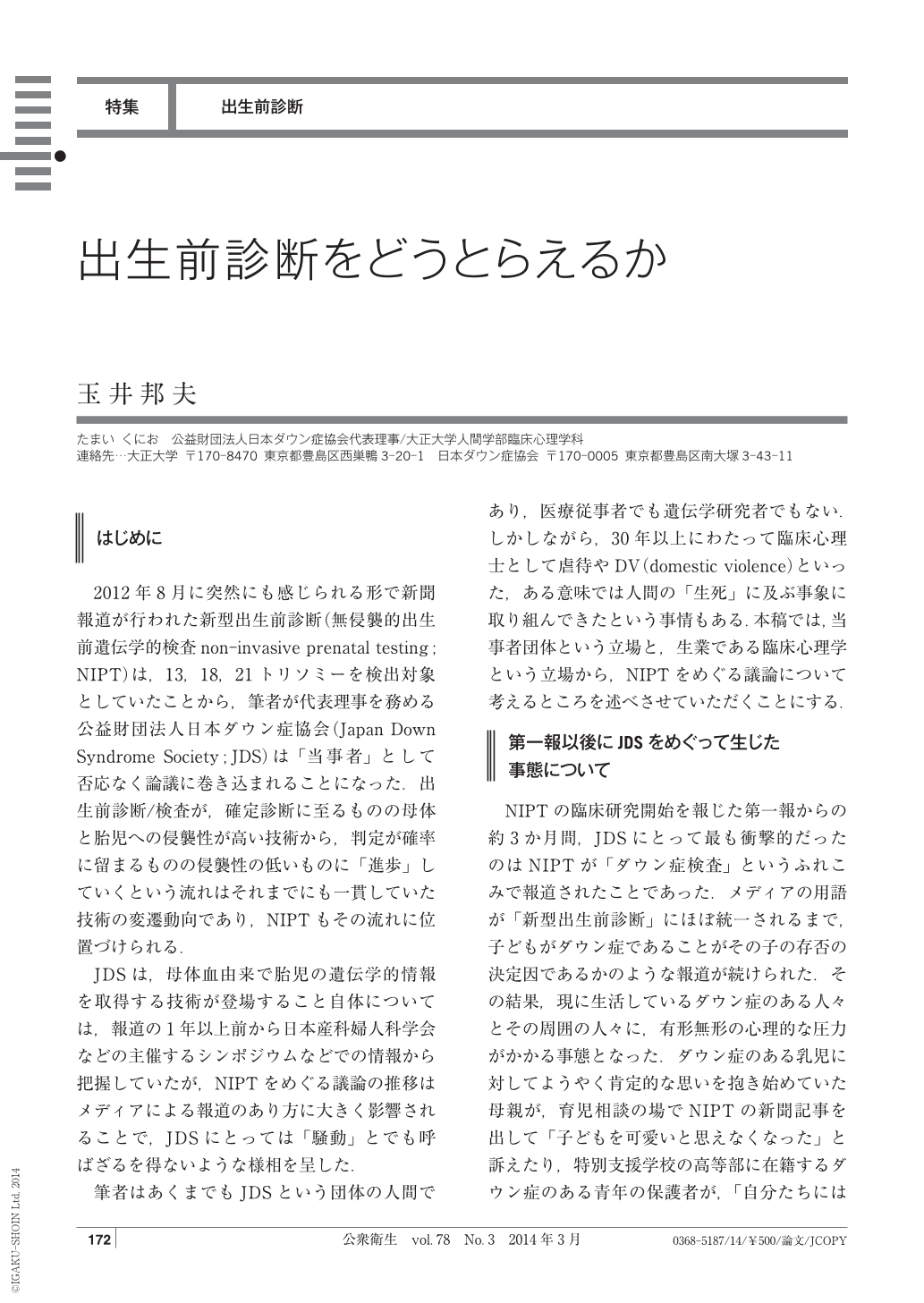
Copyright © 2014, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


