特集 胎児医療を知る 出生前診断の“その後”と助産師の役割
日本の胎児医療のこれまでとこれから
左合 治彦
1,2,3
1医療法人財団順和会山王バースセンター
2国際医療福祉大学産婦人科
3国立研究開発法人国立成育医療研究センター
pp.12-17
発行日 2025年2月25日
Published Date 2025/2/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.134781680790010012
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
胎児医療をよく理解することは助産を行ううえでも重要である。胎児医療とは胎児診断と胎児治療からなる。胎児治療は児が生まれる前の子宮内で行う治療で,子宮内の胎児を診断する出生前診断技術の進歩により可能となった。胎児の疾患が診断できるようになり,fetus as a patient(患者としての胎児)やthe unborn patient(生まれる前の患者)の考え方が生まれ,胎児治療が始まった。多くの胎児の疾患は出生後の治療で十分管理されるが,一部の疾患は出生後の治療では手遅れとなるため胎児治療が行われる。いくつかの胎児治療法は標準的治療法として行われるようになるとともに,新しい胎児治療法の臨床応用も試みられている。日本の胎児治療のこれまでの歩みと今後について述べる。
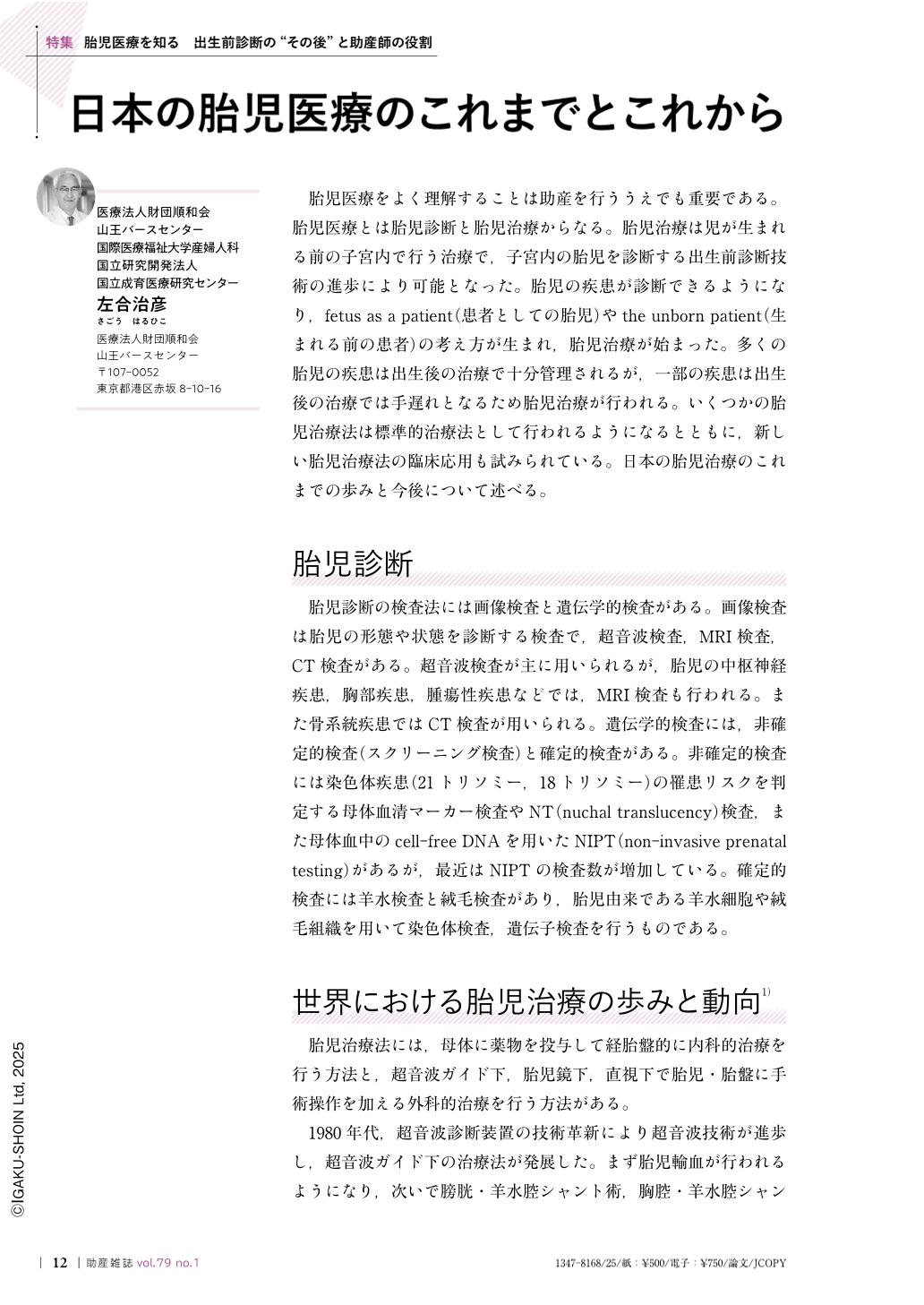
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


