- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
放課後児童健全育成事業(以下,学童保育)は,「児童福祉法」第6条の3第2項に基づき,“小学校に修学している児童であって,その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに,授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて,その健全な育成を図る事業”と定義されている.
近年,学童保育のニーズは高まり,利用児童は急増し,2024年(令和6年)5月1日現在の利用者数は全国で151万人となっている1).また,児童が小学校を利用する時間(年1,244時間)よりも学童保育を利用する時間(年1,680時間)が長いと報告2)されている.そして,学童保育では自閉スペクトラム症(autism spectrum disorder:ASD)や注意欠如/多動症(attention-deficit/hyperactivity disorder:ADHD)といった発達障害のある児童や特別な配慮が必要な児童も増加しているといわれており,小林らの2015年の調査3)では,岡山県内の学童保育124施設の在籍児童総数は5,487名であり,障害のある児童数は476名で,在籍児童総数に対する障害のある児童の比率は8.68%であり,そのうちASDやADHD等の発達障害のある児童の比率は7.05%であった.そのような学童保育は教室が狭く,利用児童は多い.そして,物品の多さや雑然とした配置からASDやADHDの子どもたちが過ごしにくい環境となっており,ADHDの子が突然走り出したり,ASDの子がルールを理解できずに混乱したりすることを指摘したうえで,それらの児童の行動に指導員は即座に適切な対応が求められる等,学童保育の指導員は発達障害の児童への対応に自信がもてず苦慮していると報告している3).
そのような状況の中で,2017年(平成29年)より岡山県では岡山県学童保育連絡協議会と岡山県作業療法士会が協力し,学童保育に作業療法士が訪問しコンサルテーションを行うモデル事業(以下,OTコンサル事業)が開始された4).その後のコロナ禍で学童保育へ作業療法士が直接訪問することは下火になったが,Zoom等のオンラインでOTコンサル事業が継続され,コロナ禍が収束した現在は,オンライン,現地の両面から多くの自治体で実施されている.
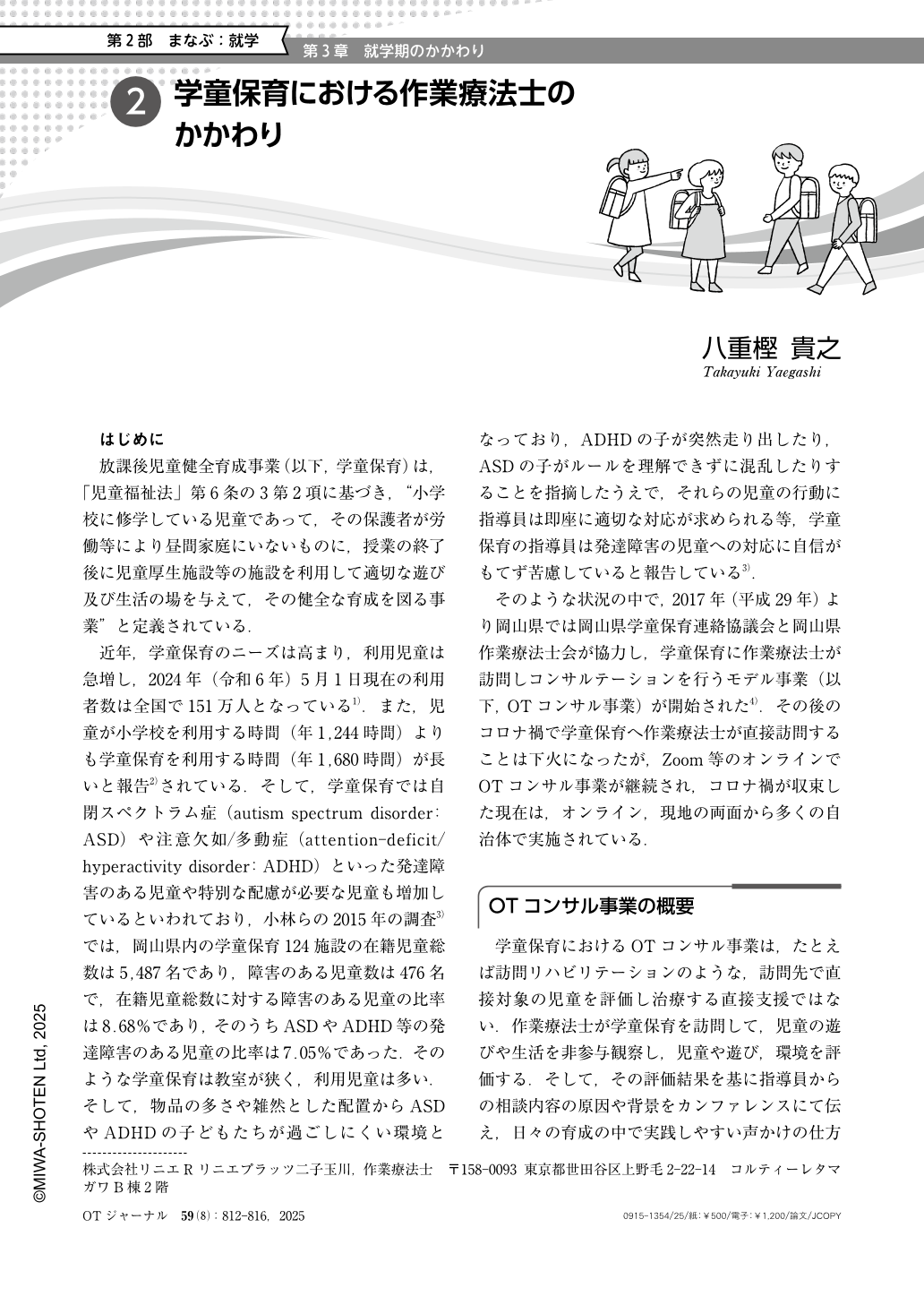
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


