特集 健康生成の考え方とサルトグラフィ
〈column〉
ギフテッド研究に差し込むサルトグラフィの光—親の会の立場から
樋口 優子
1
,
冨吉 恵子
1
1一般社団法人ギフテッド応援隊
pp.1494-1496
発行日 2025年11月15日
Published Date 2025/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.048812810670111494
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
筆者の7歳の娘は「無限小数って,無限に数が続くんだよ!」とクラスメイトに熱く語り,ポカンとしているクラスメイトの表情に気がつかない様子だった。興味の対象が他の子どもと比べてあまりにも異質で,親として戸惑わずにはいられなかった。しばらくして,娘は学校に行き渋るようになった。ある日の深夜,暗い寝室で壁を見つめている子どもに驚いて声をかけると,振り返った顔は涙に濡れていて「私はなんのために生きているのかな。なぜ生まれてきたんだろう。消えてしまいたい」と呟いた。困惑してしまった私は「せめて仲間を見つけてあげよう」という思いで,ギフテッドの親の会であるギフテッド応援隊に入会した。以前受けた心理検査では高い知能指数(IQ)数値を出してはいたが「ギフテッド」という呼称には抵抗感があった。しかし,親の会活動をするうちに娘と同じような子どもたちと出会い,保護者同士で育児の困難さを共有するうちに「ギフテッドとしかカテゴライズしようのない子どもたちが多くいて,支援の狭間にいるとしか言いようのない環境に置かれている」という確信を深めるようになった。
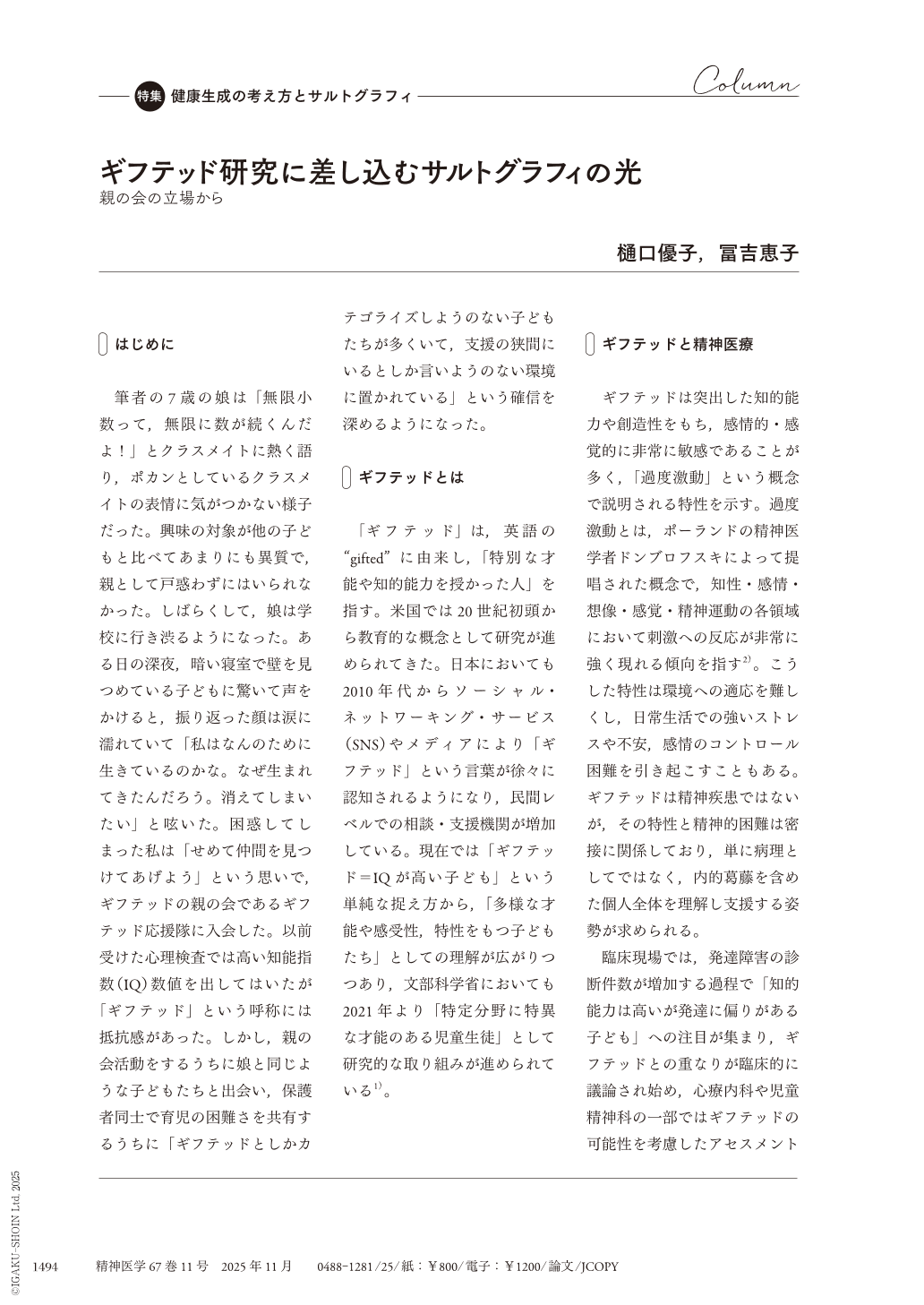
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


