Japanese
English
特集 健康生成の考え方とサルトグラフィ
漱石『坑夫』を健康生成的に読む
Rereading Sōseki's “The Miner” from the Viewpoint of Salutogenesis
田中 伸一郎
1
Shinichiro Tanaka
1
1東京藝術大学保健管理センター
1Health Care Service Center, Tokyo University of the Arts, Tokyo, Japan
キーワード:
健康生成の考え方
,
salutogenesis
,
夏目漱石
,
Natsume Sōseki
,
『坑夫』
,
“The Miner”
,
サルトグラフィ
,
salutography
,
ポリヴェーガル理論
,
the polyvagal theory
Keyword:
健康生成の考え方
,
salutogenesis
,
夏目漱石
,
Natsume Sōseki
,
『坑夫』
,
“The Miner”
,
サルトグラフィ
,
salutography
,
ポリヴェーガル理論
,
the polyvagal theory
pp.1467-1472
発行日 2025年11月15日
Published Date 2025/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.048812810670111467
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
抄録
本研究では,夏目漱石が精神疾患・精神障害を発症していなかったと考え,漱石とその小説の登場人物を健康生成(salutogenesis)の視点から考察する「漱石サルトグラフィ」を行った。対象となる小説『坑夫』の主人公は,自殺未遂者であり,自殺願望がくすぶったまま鉱山に辿り着いた。主人公が坑内巡りで体験したのは,梯子の下での「死を転じて活に帰す経験」と梯子の途中での「活上より死に入る作用」というある特殊な身体反応,すなわち,ポリヴェーガル理論でいうところの<防衛反応・生存戦略>としての身体反応であった。これらの反応ののち,主人公は現実的思考を展開させ,死を先延ばしにすること=生き延びることを何とか選択できたのであった。以上のように,本作品を健康生成的に読みなおすことで,現代のメンタルヘルス・サービスにおける自殺未遂者のサポートに貢献できるヒントが見つかるのではなかろうか。
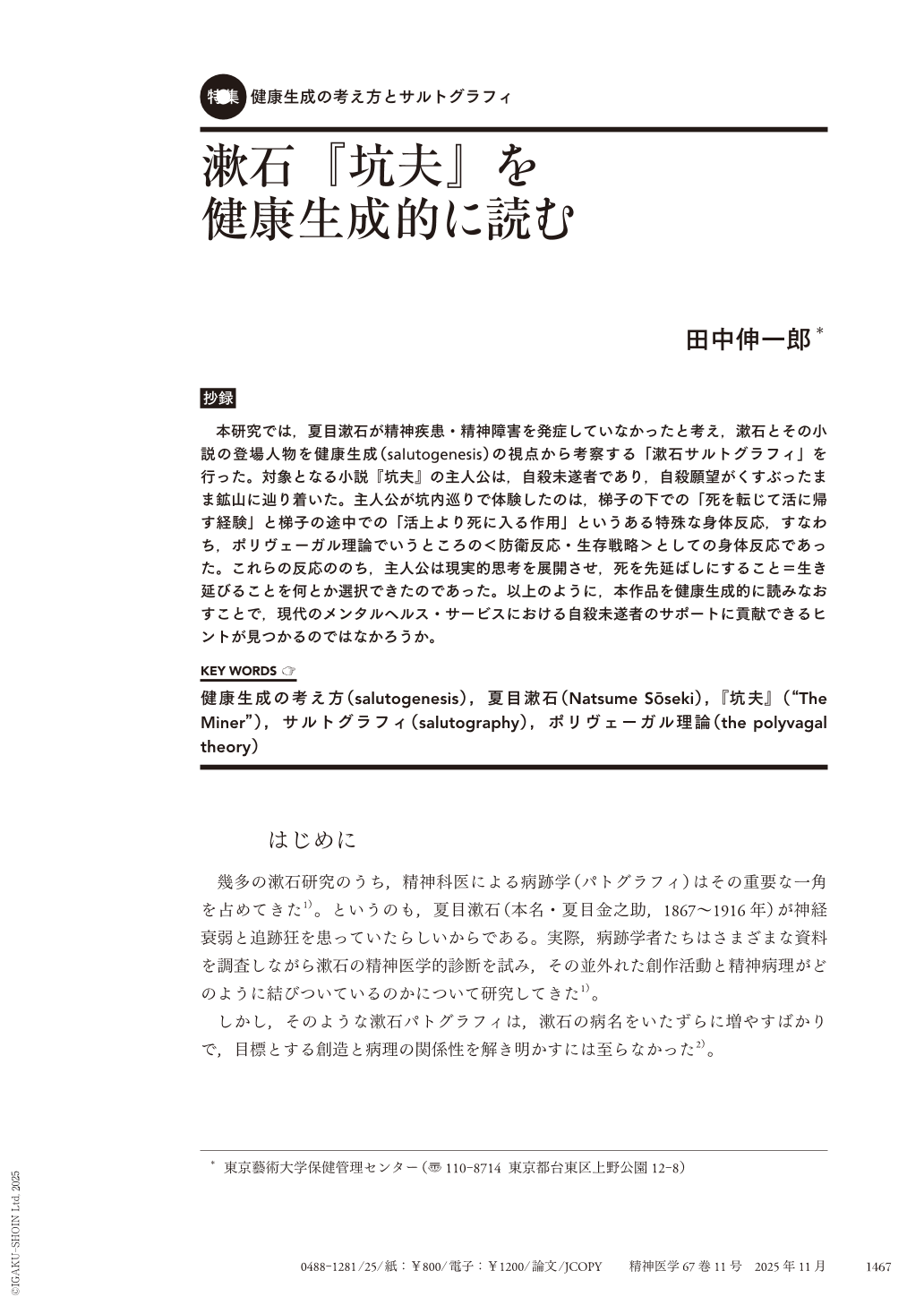
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


