- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
局所脳損傷例の症候学的検討によって,言語,視覚認知・視空間認知,記憶,前頭葉機能などの高次脳機能の機能局在に関する知識が集積されてきた。このような研究の対象となった患者は,当初は閉塞した血管の支配領域に限局した機能低下が生じる脳血管障害例,特に「綺麗な症例」と呼ばれる,障害部位が狭く,かつ特定の臨床症状を呈する患者の知見が重視された。その後,脳感染症例,頭部外傷例などの知見が集積され,また多数例による検討も進められた。脳機能局在の解明研究には,同様の障害部位を有し,かつ同様の症状を呈する症例が多数存在する疾患を対象とすることが望ましいため,その後,アルツハイマー病,レビー小体型認知症,前頭側頭葉変性症などの変性疾患を対象とする研究が進んだ。特に,レビー小体型認知症は幻視や誤認妄想,前頭側頭葉変性症は脱抑制や常同行動という精神症状や行動障害を呈するため,認知障害のみならず,精神症状や行動障害の発現メカニズムの解明にも寄与することとなった。また近年,臨床神経心理学の近縁の研究分野として認知神経科学分野の発展がめざましく,fMRIなどを用いた神経ネットワーク研究からの知見も集積されてきた。
一方で,統合失調症,解離症などの非器質性精神疾患例は幻覚,妄想,解離などの多彩な臨床症候を呈する。そして多くの精神疾患においては臨床症候が複雑なこともあり,高次脳機能の知識,神経ネットワークの知識を直ちに日常診療に役立てるには至っていない。しかし近年,非器質性精神疾患の一部の症候に対して,高次脳機能の知見をふまえた考察がなされるようになってきた。また,器質性脳損傷を有する患者はさまざまな生活上の困難に遭遇するため,二次的な精神症状を呈しやすい。このような患者の診療,治療においては,高次脳機能に関する知識をもつことが必要で,これによって患者からの信頼が増し,的を射た心理的サポートが可能になる。そして治療効果も高まる。
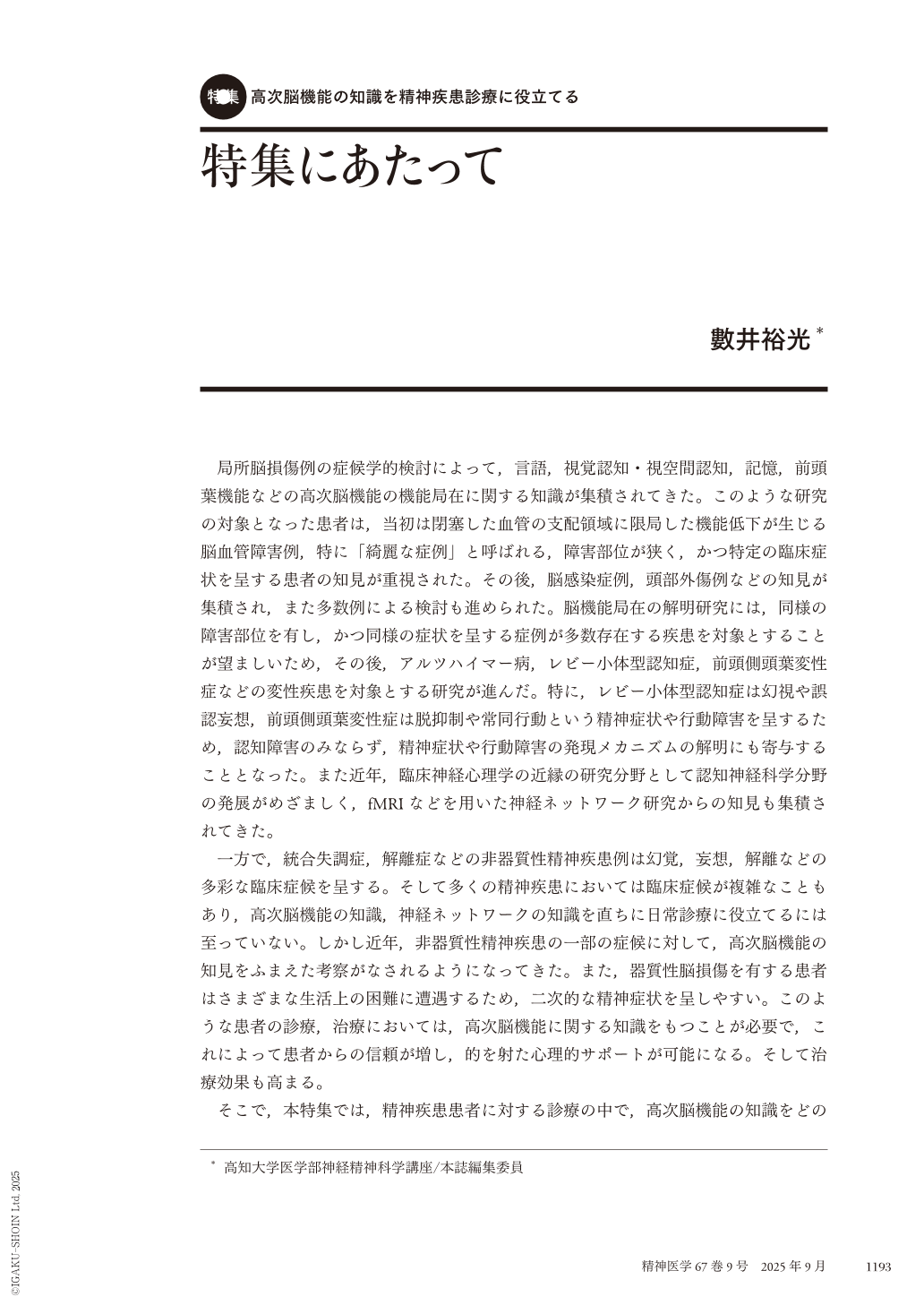
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


