今月の!検査室への質問に答えます・29【最終回】
抗核抗体の染色パターンは海外で新しい分類になっていると聞きますが,日本の状況はいかがでしょうか?
越智 小枝
1
1東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座
pp.1308-1313
発行日 2025年11月15日
Published Date 2025/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.048514200690111308
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
抗核抗体とは
抗核抗体(anti-nuclear antibody:ANA)は自己免疫性疾患の診断には欠かすことのできない検査です.実は「抗核抗体」と呼ばれるもののなかには細胞質の成分に反応するものもあります.このため抗核抗体ではなく抗細胞抗体(anticell antibody)と呼ばれるべき,という方もいらっしゃいますが,ここでは便宜上「抗核抗体」と呼びます.
抗核抗体が他の自己抗体と異なる点は,その量だけでなく細胞内の抗原の分布パターンが診療に重要であることです.このため,ELISA(enzyme-linked immunosorbent assay)のような定量的検査ではなく,間接蛍光抗体法(indirect immunofluorescence assay:IIF)を用いた半定量的検査が抗核抗体のゴールドスタンダードとされています.臨床検査を行う人は,HEp-2細胞と患者の血清を反応させて染色し,その染色型を正確に読み取れる必要があるということです.しかし半定量的検査はどうしても施設ごとにバラつきが出ます.世界では,抗核抗体の染色および判定を標準化しようという活動が続けられています.
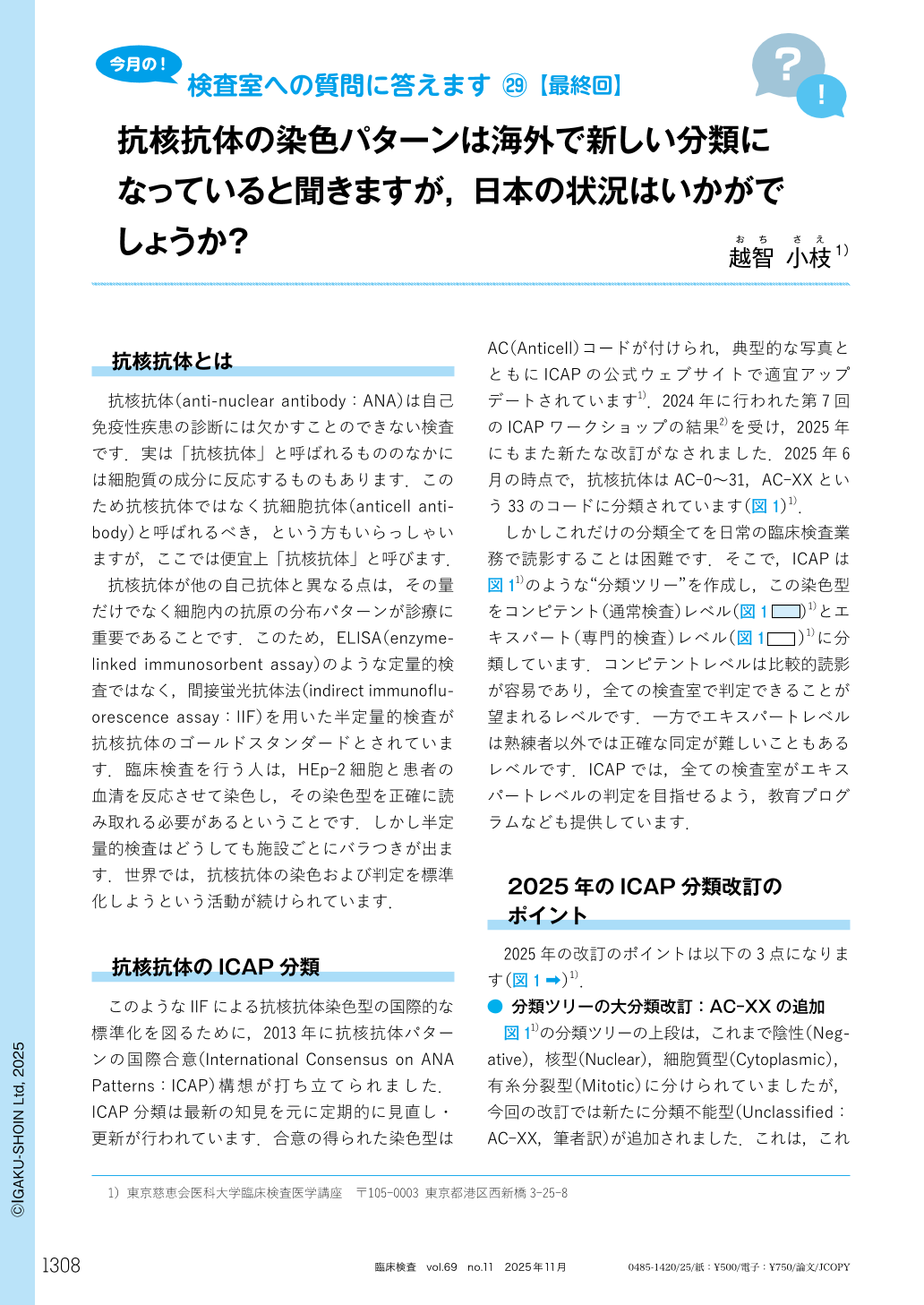
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


