Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
脳性ナトリウム利尿ペプチド(brain natriuretic peptide:BNP)/BNP前駆体N端フラグメント(N-terminal pro-BNP:NT-proBNP)や心筋トロポニンなどのバイオマーカーは,すでに保険収載されており,心不全の診断や慢性期管理において,日常診療で頻繁に使用されている.本稿では,全身疾患としての心不全を血液検査からどのように把握するか,また検査結果をどのように包括的心臓リハビリテーションに活かすかについて解説する.
2003年にSilverbergら1)がCardio-Renal Anemia Syndrome(CRAS)という概念を提唱した.これにより,心臓病,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD),貧血が互いに影響し合って悪循環を形成することが明らかになった1)(図1).さらに近年,心・腎・代謝症候群〔cardiovascular-kidney-metabolic(CKM) syndrome〕やcardio-renal anemia iron deficiency syndrome(CRAIDS)といった多臓器や他疾患との連関,すなわち「全身疾患としての心不全」が注目されている(図2).
その他にも,膠質浸透圧を保ち,フロセミドを効果的に作用させるためには栄養状態の指標の一つであるアルブミンの存在が欠かせない.さらに前負荷の指標として,うっ血性肝障害を反映する肝機能検査も重要である.血栓塞栓症の診断に有用なD-dimerは心房細動の患者で上昇することがあり,参考になる.ナトリウムやカリウムをはじめとする電解質の評価と調節も心不全管理には欠かせない.
これらの血液検査は一次予防から三次予防,すなわち包括的心臓リハビリテーションに至るまで継続的なモニタリングに欠かせない.以下では,血液検査を中心に据え,心不全の病状把握と多様な臓器間連関について述べる.一方で,血液検査に頼り過ぎると誤った対応を招くことがあり,その限界についても十分に理解しておく必要がある.
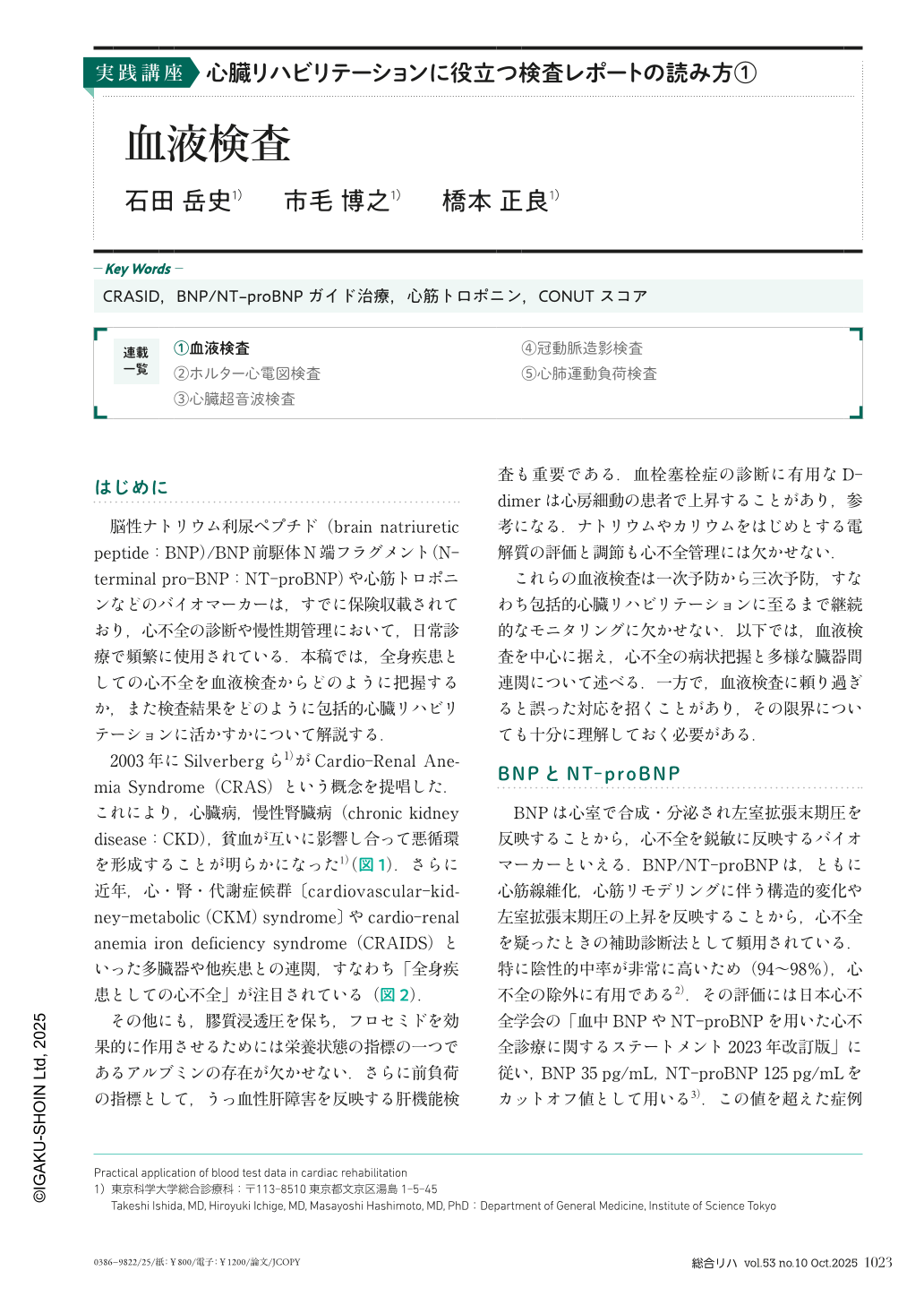
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


