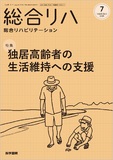Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
日本では少子高齢化が進むと同時に高齢者の単独世帯も増加している.2022年の国民生活基礎調査1)によると「単独世帯」は全体の34.0%を占め,2001年と比較して1.7倍に増加している.単独世帯のうち46.2%は65歳以上の高齢者が占めており,2001年の2.7倍となっている.また,近年は未婚化が進み,「50歳時の未婚率」は男性が28.3%,女性が17.8%と年々上昇している.近い将来,独居であるだけでなく,子どもや甥・姪などの近親者がいない,いても支援が受けられない,いわゆる「身寄りのない(少ない)高齢者(以下,身寄りのない高齢者)」が増加していくことが推測される.
独居高齢者は,家族と同居している高齢者と比べて,うつ,孤立,貧困の割合が高いなど「要援護」状態の人が多いことや2),認知症の発症リスクが高いことが報告されている3).また,健康や生活管理の難しさや急病時の発見の遅れも指摘されている4).さらに,身寄りのない高齢者の場合は,入院手続きや手術に伴う身元保証問題,入院中の居宅の管理,死後の所有物の整理など多様な問題を生じることが報告されている5).
一方,高齢者を支援する専門職をみると,高齢者の総合相談を担う地域包括支援センターでは,独居高齢者を担当することについて69.8%の職員が精神的な負担の大きさを感じていた.また,要介護高齢者のケアマネジメントを担う介護支援専門員(ケアマネジャー)の61.4%が,独居高齢者の意思確認が不十分なまま生活の方向性を代理で決定せざるを得なかった経験をもっていた6).
高齢者が人生の終焉を迎える準備として意思を表明しておくことは,人生のラストステージをよりよく生き,よい死を迎えるために望ましいことであり,独居や身寄りのない高齢者にとっては重要な課題である.本稿では,独居高齢者の在宅生活の現状と課題,意思決定支援の重要性について筆者(石井)が述べた後,2022年度に実施した調査の共同研究者である中井氏から,地域包括支援センターのスタッフとケアマネジャーを対象とした独居高齢者の意思決定支援をめぐる調査の結果について述べていただく.
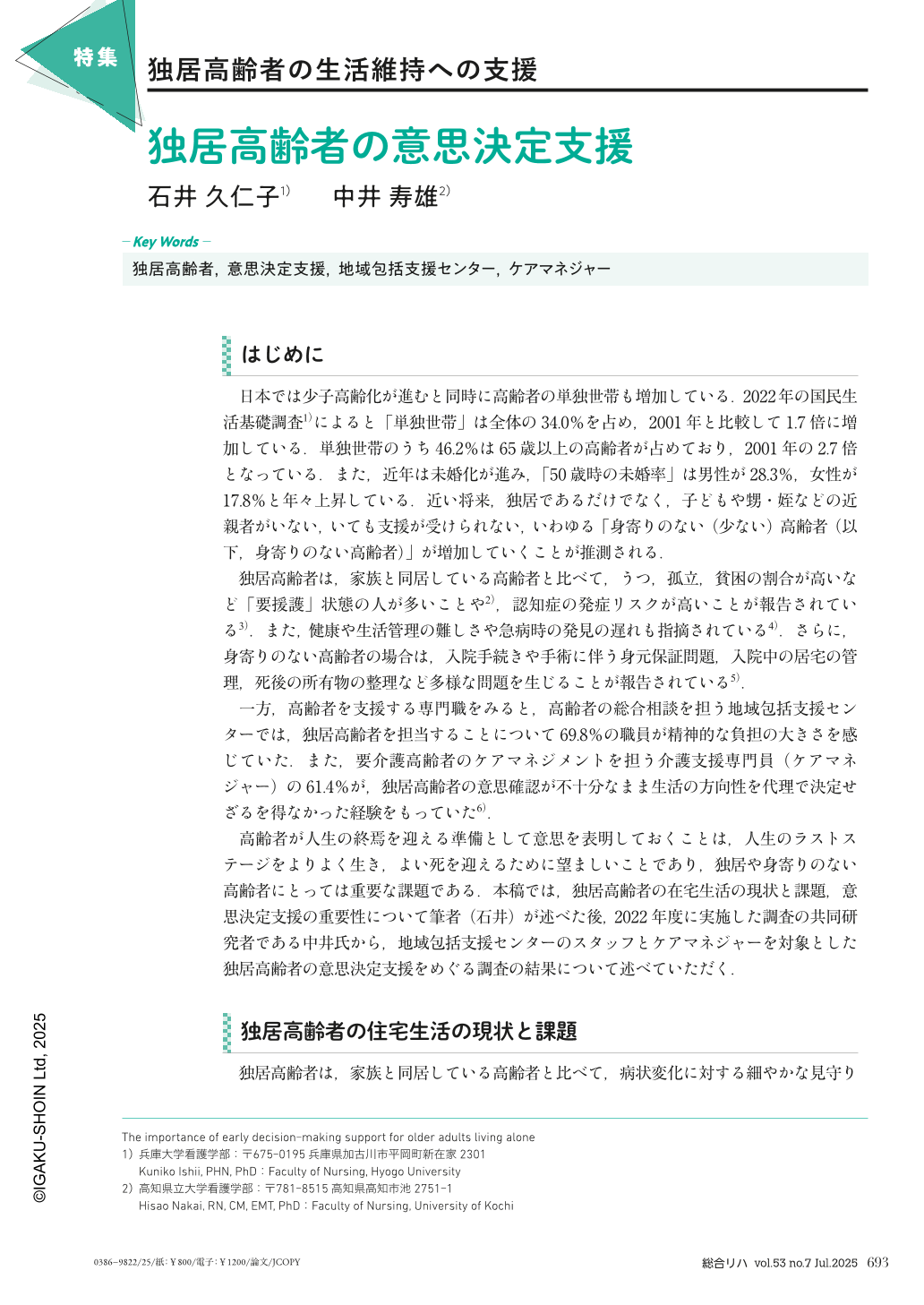
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.