増大号 極める!呼吸機能検査 患者を診る力が成功のカギ
はじめに
清水 康平
1
1東邦大学医療センター大森病院臨床生理機能検査部
pp.91
発行日 2025年2月1日
Published Date 2025/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.030126110530020091
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
呼吸機能検査は患者努力に依存する検査であるため,患者の検査理解度や患者状態によって検査結果が変わってしまいます.しかし,これは患者側“だけ”の問題ではなく,同一患者であっても検査者の声掛けによってデータもしくは臨床的判断までもが変わることを多く経験します.また,臨床では%肺活量や1秒率など数字で表されるパラメーターが,スパイログラムやフローボリューム曲線から読み解く情報より判断しやすく,数値が重視されている傾向があります.そのため,患者状態や検査結果の信頼性などを読み取ることができるスパイログラムやフローボリューム曲線は見過ごされることが多く,検査現場で“患者を診ている”検査技師が検査結果に対して適切なコメントを付けることが大事なポイントになります.そのため,呼吸機能検査に携わる検査技師には機器の操作や検査,病態の知識に加え,患者心理などを踏まえた患者対応や検査結果以外の患者状態,つまり“患者を診る力”も必要なスキルとして求められています.
検査の標準化は検査技師の標準化が必須であり,患者対応やアーチファクトを見抜く力が重要です.しかしながら,多くの患者は呼吸器症状を持っており,また,持っている疾患の症状によって“万全な状態”で検査を行えるわけではなく,検査当日のベストデータを取ることになります.そのため,アーチファクトなのか患者状態の影響なのかを判断することが難しく,時としてアーチファクトを誤認していることも経験します.
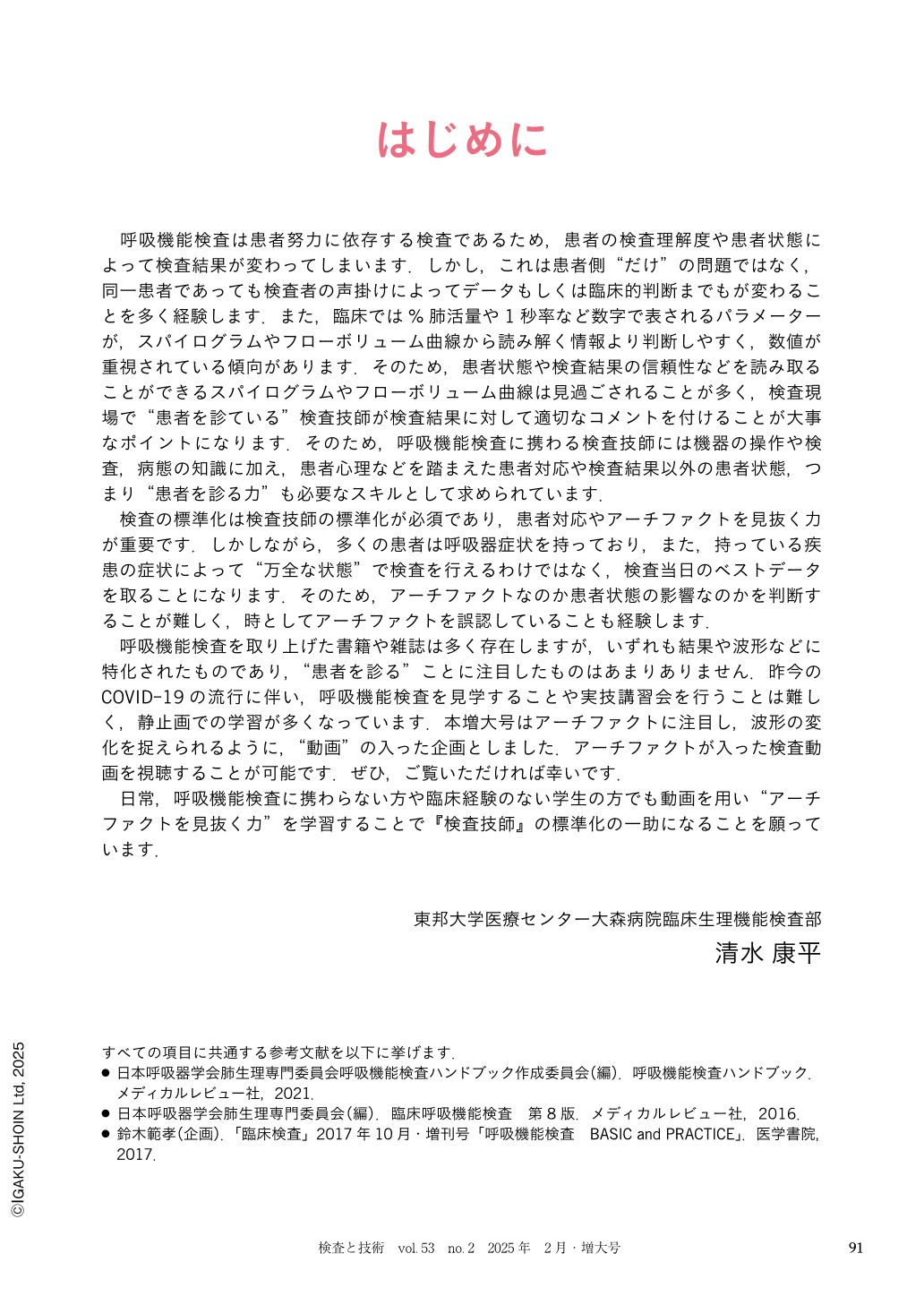
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


