- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
緒 言
厚生労働省による令和5年度の労働安全衛生調査によると,令和4年11月1日から令和5年10月31日までの1年間にメンタル不調で1カ月以上休職した人がいる事業所は13.5%となっている。こうした状況で事業所の63.8%はメンタルヘルス対策に取り組んでいると答えており,その手段として「ストレスチェック」と「メンタル不調者への必要な配慮の実施」をあげている。また長時間労働が要因となっているという視点から「働き方改革」として残業時間のチェックや有休取得が厳しく行われるようになっている。
ただこうした対策は,メンタル不調の人を見つけ支援する,という方向性であり年々増加傾向にあるメンタル不調者を減少させる方向には進んでいない。「健康経営」が叫ばれているが,現在の対策は,「病気ではないが元気ではない」というメンタルヘルス予備軍の人のメンタルを支援する方向には向かっていない。
こうした状況を変化させるにはこれまでの「不調を早めに見つける」という視点から「活気のある人を増やす」ことで不調者を減らすという視点に転換することが必要だと思われる。
1990年代後半から米国を中心に研究がすすめられてきたポジティブサイコロジーの視点を参考にして,働き方改革だけにとどまることなく,「企業風土」をウェルビーイングの方向に導くという視点から,日本の職場風土が文化的にかかえる心理的な問題点を加味した改革なくしては,状況を改善できないと考えている。ポジティブサイコロジーはウェルビーイングを高めるエビデンスに基づく介入方法を研究して心の活気を増やすことで,うつ気分を減少させるという概念を持つ。
メンタル不調は単に長時間働くという原因だけが問題ではないため,形だけ「健康経営」として時間が守られていても解決はできない。職場での上下関係で意見が言えない環境や賃金や待遇の格差,ハラスメントなど職場の環境を含めた要因が問題の根底にある。
さらに職場のメンタルヘルス対策の必要性を企業の経営トップが認識しているかどうかがこれからのウェルビーイング経営に向けて必要だが,残念ながら現状では,多くの経営者はメンタル不調対策を「弱いものを見つけて支援する」こととしてとらえ,人事総務担当者に丸投げということが多い。経営トップの関心事は企業業績を伸ばすことに集中しているものだが,メンタル不調で休職者が増えたり,病気にはならないが活気がない労働者が増えれば業績は低迷する。したがって企業のメンタルヘルス対策は企業業績に大きくかかわっている。近年そうした視点からウェルビーイング経営に向けて一石を投じる改革が英国からスタートしている。
それが英国最大規模の投資運用機関CCLA(Charches, Charities and Local Authorities)で策定したCorporate Mental Health Benchmarkである。企業風土を見直し,働く人が気持ちよく働けるような職場を事業主がどの程度提供しているか,ウェルビーイング経営を実践しているかを評価することを目的として,2022年にスタートした。今回はこうした取り組みを紹介しながらポジティブサイコロジーを応用したウェルビーイング経営について考察する。
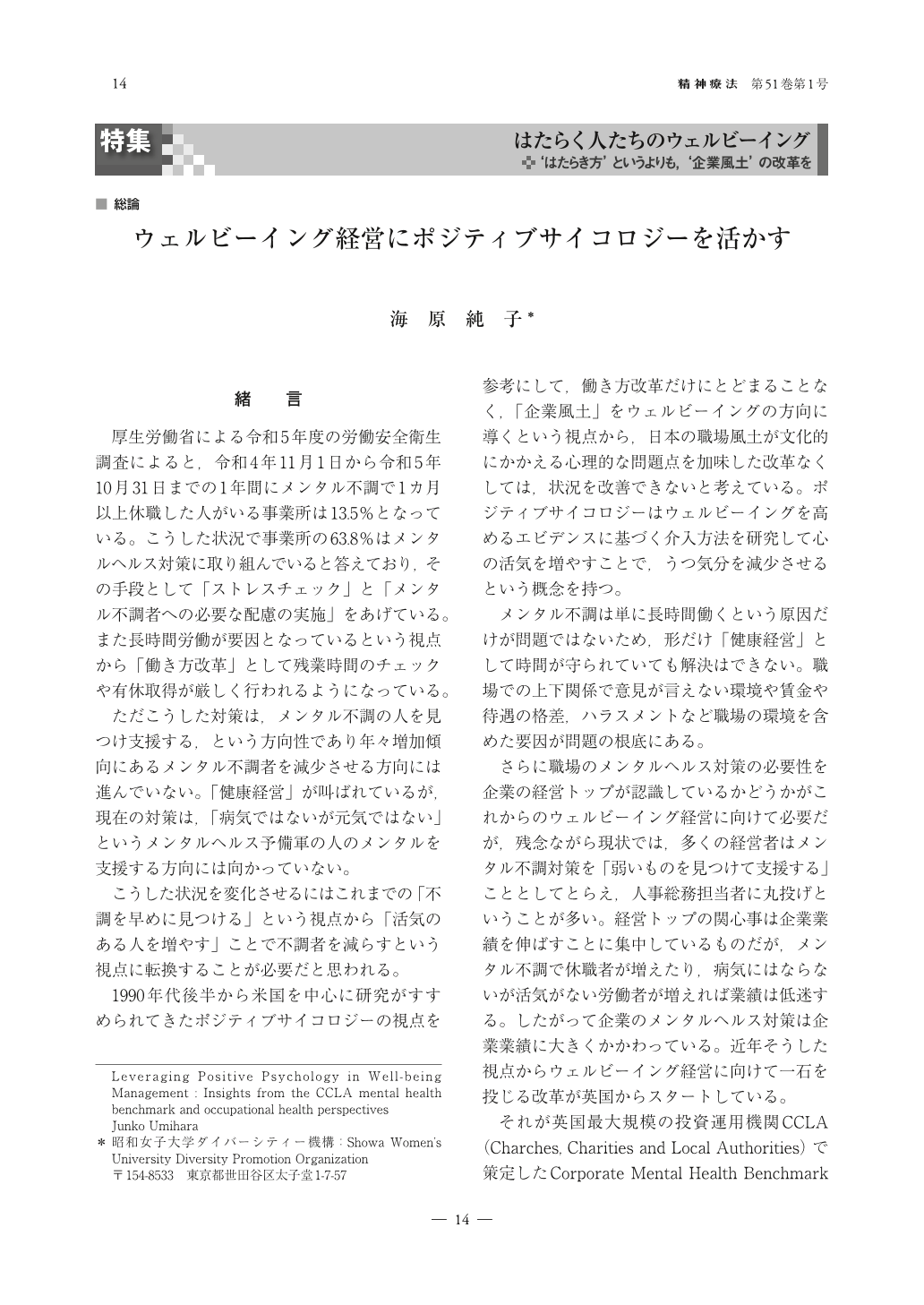
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


