- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 はじめに―生活を大切に考える統合的アプローチ
臨床の現実は既成の理論や技法のみでは対応しきれない難しさがしばしばある。さらに,人が生きていく心理的問題は,背景に生物・心理・社会的要因が輻輳して関わっている。従って,狭義の心理学的解釈理論だけで,事態を捉えようとするのではなく,複眼の視野で観察し,多軸で考え,多面的に関わる方法が望まれると,重篤な障害を抱える人々への臨床経験から帰納的に考え,実践してきた。その結果,特定の理論や技法に則るのではなく,統合的アプローチを行うに到った(村瀬,2006,2012;新保,2012)。現実には,障害や疾病は消褪せずとも,生活の質を向上させることにより,人は生きやすさが増すことを発達障害児や精神疾患を持つ人々,重複聴覚障害者とのかかわりでつぶさに経験した。「人生の悩みや病気の症状と生活とは,相互に影響し合っている。[中略]悩みや症状を洞察するよりも,自分の生活のありかたに気づく方がプラスになることが少なくない」と青木(2010)も指適している。
生活とは「人が命を維持し,育むために行っている必要不可欠な活動であり,その活動は衣・食・住を基礎として,次のような関係性の元に営まれている。まず第一に家の内の人間関係では,夫婦の関係,親子関係,兄弟姉妹,その他の関係がある。家の内と外に繋がる関係として職業生活,社会生活がある。
一方,心理療法が対象とする人の「こころ」について,『広辞苑』では「人間の精神作用のもとになるもの。知識・感情・意志の総体」と定義されている。これを実体に即して表現すると,「人が自分自身をどう捉え認識しているか,他者や物,ことへどのように関わるか,それらの現われの総体」と言えよう。こう考えると人が少しでも生きやすくなるように心理的に支援することは,生活全体を対象として視野に入れ,当面の課題や目的にそって,生活に即して,着手出来るところから関わり,成長変容を目指していくということが意味がある,いやむしろ必要であると言える。
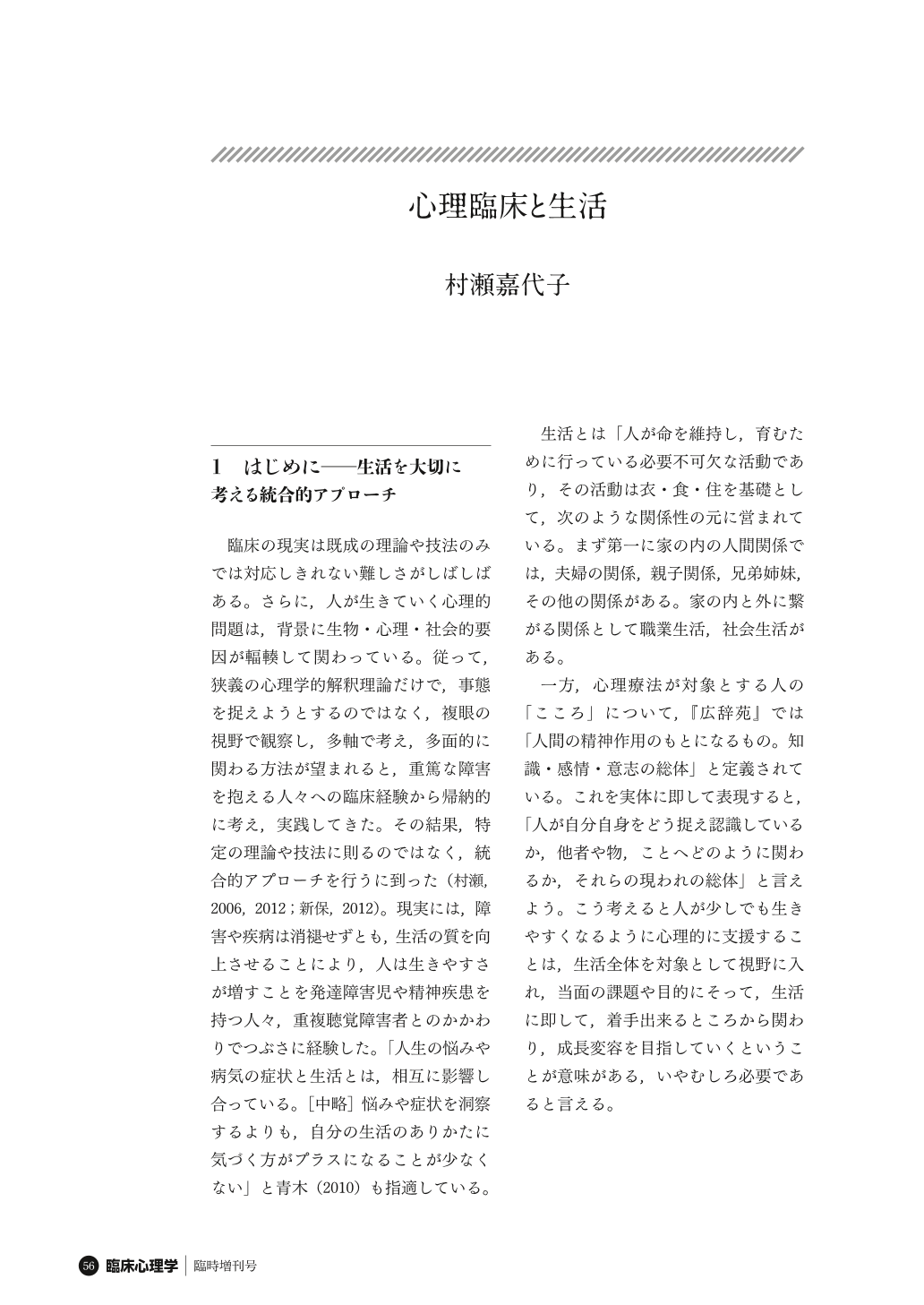
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


