- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 はじめに
人が人から暴力を受けること―心理臨床においては,どのような現場においても暴力を受けたという語りはしばしば聴かれるものではないだろうか。たとえば,過去に親から虐待を受けた,小学生の時に友人たちからいじめられた,以前夫から物を投げつけられたり罵られたりしたなど,暴力を受けたことがクライエントの今の在り方に影響を及ぼしている出来事などとして語られることがある。かたや,何かしらの暴力被害を受けたことによる混乱や恐怖,心理社会的なダメージを主訴としたケースも存在する。犯罪被害者支援センターや性暴力被害者ワンストップ支援センターなどのみならず,数は少ないかもしれないが,学生相談や病院,福祉現場などにもそのような相談が入ることがあるだろう。別の主訴で継続して来室していたクライエントが何らかの被害に遭うこともある。これらを踏まえて本稿では,被害者臨床におけるアセスメントについて,特に知人から予期せぬ暴力を受けたケースを想定して考察していきたい。
暴力には,身体的暴力のほか,精神的暴力,性的暴力,必要なお金を理不尽な理由で渡さないなどの経済的暴力,人とのやりとりを制限・監視するような社会的暴力,SNS上での誹謗中傷のようなデジタル暴力などがある。どのような暴力であったとしても,それは個人の身体的・精神的・社会的なに同意なく一方的に侵入したり境界の変更を強要したりする行為で,個人の尊厳と自己コントロール感を奪う。
また,暴力の振るい手としては,家族や血縁者,配偶者や交際相手,教師や指導者,友人や先輩,仕事関連の人物などといった顔見知り,あるいは見知らぬ人,さらに最近増えてきたケースとしてはSNSで知り合った人物,デジタル暴力などでの匿名の他者などがある。本稿のテーマである知人からの暴力の場合,それまでに何かしらの関係性が存在するため,見知らぬ人からの暴力に比べて,相手や状況に対する両価的な気持ちや「自分にも非があった」といった自責感など,より複雑な心理状態になりやすい。
暴力が振るわれる経緯も,個人の暴力の体験の仕方に影響を及ぼす。じわじわと関係性が険悪になったり強い違和感や無力感を覚えるようになった後に振るわれる暴力と,そのような予兆なく振るわれる暴力とでは,受け止め方が異なって当然であろう。
前置きが長くなったが,筆者は性暴力被害者ワンストップ支援センター(以下,ワンストップ支援センターまたはセンター)で活動を続けていることもあり,本稿では職場同僚の男性から性暴力被害を受けた男性という設定でケースを想定する。事例については架空事例であるが,できるだけ現場で体験するリアリティを担保するよう努めている。
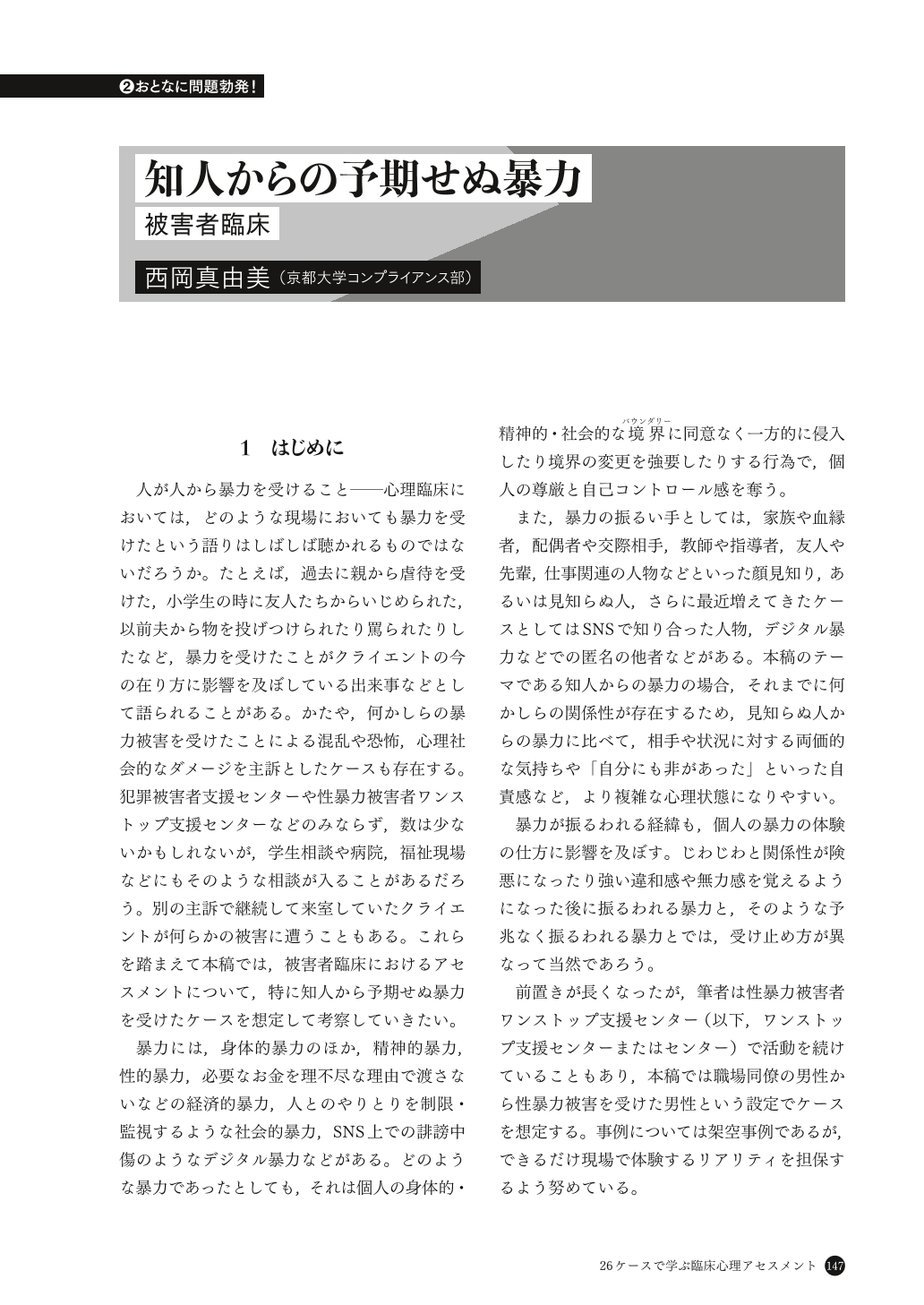
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


