特集 26ケースで学ぶ臨床心理アセスメント――インテークとフィードバックをつなぐ〈スキル7〉
特定の行為が止められない――強迫症
矢野 宏之
1
1EMDR専門カウンセリングルーム リソルサ
pp.86-91
発行日 2025年8月30日
Published Date 2025/8/30
DOI https://doi.org/10.69291/cp25070086
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 強迫症の病態と認知行動療法モデル
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-TR(DSM-5-TR)によれば,強迫症とは強迫観念とそれを打ち消す強迫行為に特徴づけられる精神疾患である。現在,強迫症の症状は,大きく4つの因子に分かれることが知られている。①確認を繰り返す確認強迫,②タブーに関する想像が止められない反芻強迫(純粋強迫観念),③整理整頓や納得を過度に追求する整理整頓強迫,④手洗い・汚染に関する洗浄強迫である。DSM-5-TRにおいては,強迫観念および強迫行為のどちらかのみでも診断基準を満たすことができる。それは,反芻強迫が目に見える強迫行為を取らずに,一見すると強迫観念のみを持つように見えること,整理整頓強迫は言語で表現される強迫観念を持たず,一見すると強迫行為のみを持つように見えることが関係している。またDSM-5-TRでは,自分の強迫観念の不合理性に対する洞察の程度に特定子がある。洞察の程度は,治療反応に最も寄与する要因として知られている。
強迫症へのアセスメントは,認知行動療法の発展とともに進化してきた。初期の認知行動療法モデルでは,「強迫観念→不安→強迫行為→一時的な解放感」という悪循環が成立し,症状の維持には古典的条件づけが関与していると考えられていた(図の濃い灰色矢印参照)。
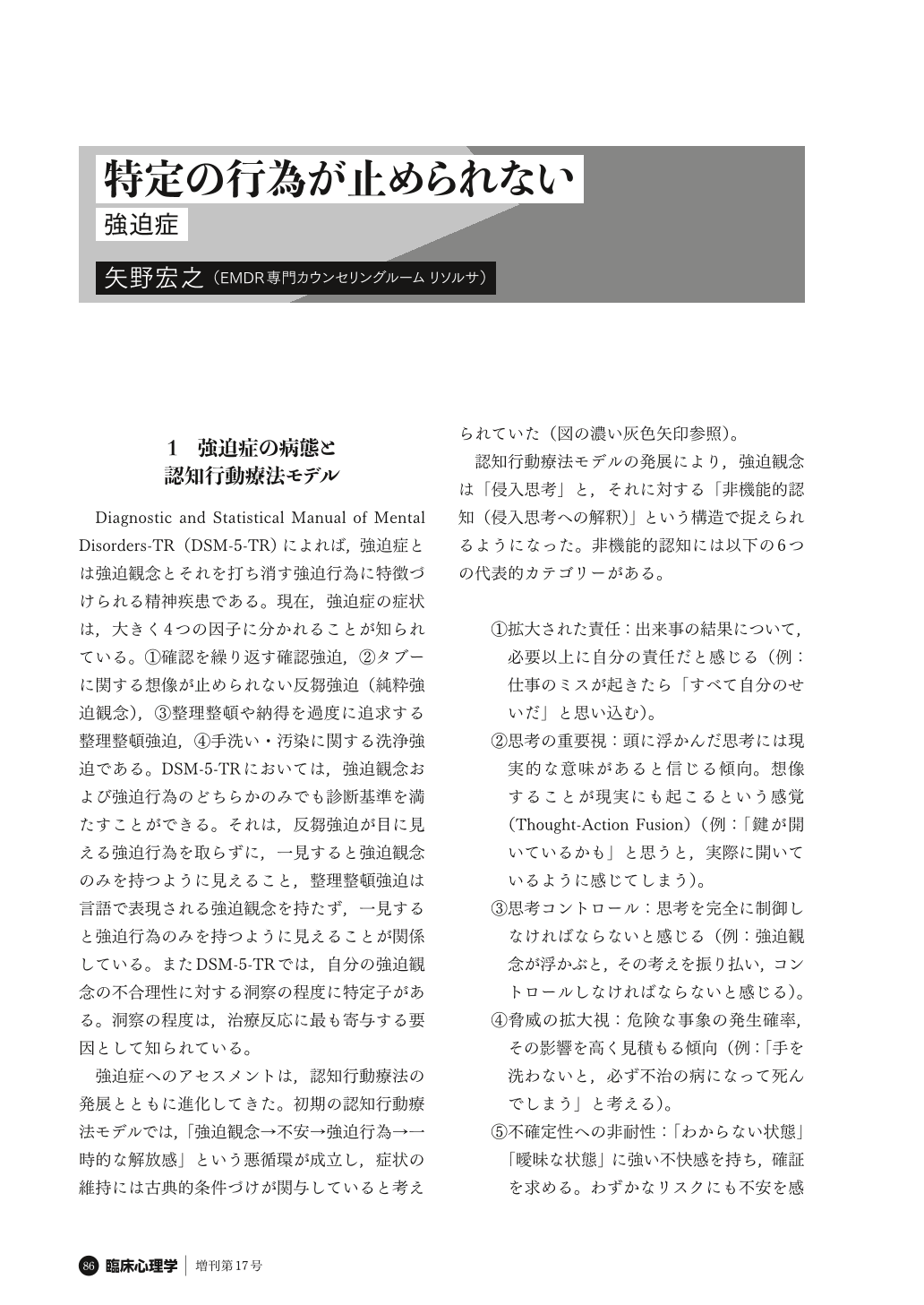
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


