- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
I 集合的・社会的・文化的トラウマに応答した精神保健医療福祉のパラダイムシフト
トラウマは,大きく以下の3つに分類されることがある。
1つ目は,たとえば出会い頭に他人から暴力を受けたというような,被害の内容や時期が明確な単回性のトラウマである。
2つ目は,虐待など長期に反復される複雑性のトラウマである。たとえばネグレクトのなかで親に愛着せざるを得なかった子どもが,自分自身の在り方を変容させることで生き延びた結果,じわじわと蝕まれ形成されていく心の傷や,身の守り方の癖がこれにあたる。環境を変えることができず,自身を変容させて生き延びた過程そのものが,後に深い傷として刻まれる。
3つ目は,集合的・社会的・文化的トラウマである。マジョリティ向けに設計された社会構造がマイノリティに継続的な暴力や差別,排除をもたらし,生き延びるなかで傷つけられていく。こうしたトラウマは個人の心身に深い影響を及ぼし,しばしば命をも奪い,その後の生にも重く影を落とす。
対人支援を行う上では,これらさまざまな水準のトラウマが,個人のライフストーリーのなかで複雑に入り組んで影響を与えあっていることを,解像度高く理解していく必要がある。特に,トラウマインフォームドケアを実践する上では,支援の文化や構造自体が,無自覚のうちに集合的・社会的・文化的トラウマの再生産の場となる可能性について認識している必要がある。
たとえば精神疾患を持つ人は,精神疾患そのものによる影響と,スティグマ(無知・偏見・差別)による影響という二重の苦しみを抱えている。そして,精神疾患を持つ人の多くが,精神疾患そのものによる影響よりも,スティグマによる影響のほうが大きいと述べている。
特定の人々の機会や資源,幸福を制限する社会的な条件,文化的規範,政策を,構造的スティグマ(structural stigma)と呼ぶ。医療アクセスの格差,医療の質の問題,身体疾患に比して治療や研究に割り当てられる資金や人的資源が少ないことなど,精神疾患を持つ人はさまざまな構造的スティグマの影響を受けている。
既存のヘルスケアの制度設計自体が,構造的スティグマを構成しているという事実を認識した上で,人権に関連する差別に抗するための,包括的な研究および実効性のある取り組みを行うことが求められている。
本稿では,こうしたトラウマを構成する大枠の概念を念頭に置き,精神保健医療福祉のあり方自体が集合的・社会的・文化的トラウマを構成し,再生産し続けているという課題意識を前提とする。その上で,精神保健医療福祉の領域で近年展開されているパラダイムシフトを,集合的・社会的・文化的トラウマに応答し対抗しようとする試みと位置付けて紹介する。
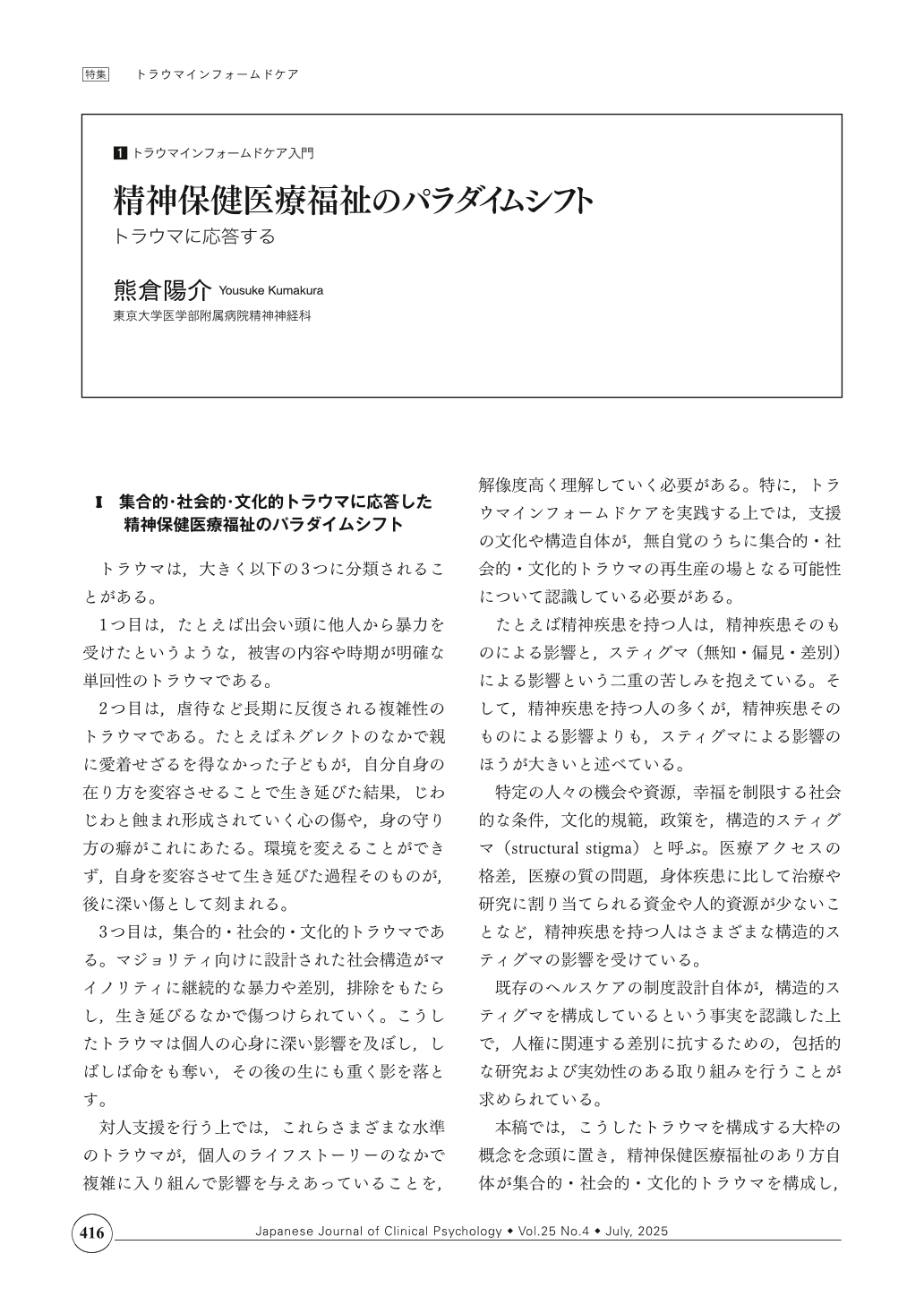
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


