- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
Ⅰ 長い前提
最初に編者から課された題目は「精神分析しないこと」というものだった。即座にこれは私の仕事ではなく,精神分析家によって執筆されるべきものだと思った。
精神分析には実践的・構造的定義がある。それは「精神分析家によって行われる,週4回以上の頻度でカウチを用いた自由連想法を介した療法」といったものであり,私は精神分析家でもないし,週4回以上の療法に取り組んだこともない。つまり精神分析をしたことがない。「する/しない」という選択以前の立場にある。
厳密には「精神分析的心理療法」,すなわち「精神分析的心理療法家が行う,週3回以下の頻度でなされる精神分析的な療法」もしたことがない。私が経験してきたのは,「精神分析の知を借りて行う(ときにカウチを用いて行う)週1,2回の頻度でなされる自由連想を介した探索的な心理療法」であり,それは岡田(2017)のいう「精神療法を少しでも精神分析らしくしようとして精神分析の外形的な要素を模倣」する「精神分析様精神療法」である。
精神分析家になるには相当な時間,金銭,労力を要する。その候補生になるだけでも,医師もしくは心理職としての5年以上の臨床経験,各国の精神分析協会が指定する基礎セミナーの受講(数年にわたる),協会による受理面接をパスした後の1年間の審査分析(週4回以上の分析体験)が求められ,その後も数年にわたる週4回以上の訓練分析,週1回のスーパーヴィジョンをセットアップした精神分析事例への取り組み(2事例),協会指定のセミナー受講を経て,ようやく精神分析家として認定される(精神分析的心理療法家は訓練分析や訓練ケースの頻度が週1回ないし2回となる)。当然,1回ごとの訓練分析やスーパーヴィジョンには料金がかかる。生活や人生の大半をそこに費やさねばならないという意味で,きわめて取得難度の高い資格であることは間違いないだろう。私自身はこの訓練への参入に向けて自身の人生を動かしている最中にある。
さて,編者の企画書には「大学院で学んできた専門知には,ときに世間や各々の現場では当然視されている知(世間知,現場知)を,あるいは“ふつうの人間的応答”を排除する力(“呪い”と編者は表している)があり,この特集では現場で学ぶしかないありふれた臨床技法を記してもらいたい」「専門知に根差した関わりと,このありふれたテクニックの実施とをめぐる葛藤を記してもらいたい」とある。ただ,私自身は編者がいう意味での葛藤は乏しい。そこには金銭的事情により先に臨床現場に出てから夜間の大学院に進学した(臨床心理士資格取得は30歳時である)という私の特異なキャリアが影響している。先に現場経験があり,大学院在学中も現場で働き続けていたので,編者のいう学派知・専門知の「呪い」にはどうしてもかかりにくい。ある理論や介入法が目前のユーザーや現場に役立つか否かで―特に私自身がそれを有効利用できるかどうかで―その専門知の価値を判定してしまうからである。
大学院にて専門知・学派知を体系的に学ぶまで,私は圧倒的な臨床事実の洪水に呑まれていた。剝き出しの現実に晒され続けていた。そのような私に対し,専門知・学派知は事態を考える術を与えてくれた。しばしば専門知というフィルター越しに臨床事実を見ることが注意喚起されるが,私の体験はまったく逆である。むしろ,専門知の学びは事をよく見えるようにしてくれた。そのなかでもっとも事態を考えるのに役立った知が「精神分析」であった。もちろん,他のさまざまな学派知も私には重宝した。そのうちに私のなかでは「精神分析様精神療法」も,問題の具体的な対処法,解決法を模索する認知行動療法やブリーフセラピーのような介入法も,マネジメント的支援も,さほど矛盾なく並列的に共存するようになった。要はユーザーの主訴,ニーズ,状態像,彼らが置かれた環境的事情,支援者側の構造的事情を考慮するなかで,もっとも適した支援法を選択していけばよいと考えるようになった。この思考を形にしたのが『個人心理療法再考』(上田,2023)である。
以上の理由から編者のいう意味での葛藤や呪いは乏しいのだが,一方で私には別の深刻な葛藤がある。それは自身が行ってきた「精神分析の知を借りて行う探索的心理療法」が「精神分析」でも「精神分析的心理療法」でもないという事実に由来する葛藤である。
たとえ「精神分析様」と評されたとしても,私自身はこの「精神分析の知を借りて行う療法」が一定の成果をあげてきたと感じている。だが,それを「精神分析」や「精神分析的心理療法」の文脈に則して学術的・公的に検討する資格がない。「精神分析の知」を借り受けながら,それを学術的に検討できないことは自家撞着である。ここに葛藤がある。今回のような原稿依頼も本来的には応じるべきでないと思っている。
ただ,本特集が求めているのは,学派知・専門知を超えた現場体験や介入法とのことである。確かに私自身「精神分析の知を借りて行う探索的心理療法」を,その構造的形態を整えて実施する機会はほとんどなく(自身の開業オフィスと以前に勤めていた精神科病院で数例取り組んできたのみである),私の日々の実践はそれ以外の支援方策で占められている。そのありようを書けばよいのなら,何か書けるかもしれない。さらには「精神分析」や「精神分析的心理療法」に人生をかけて接近しようとしている身だからこそ書けることがあるかもしれない。このような想いで今回筆を執っている。私なりに何かを語ってみようと思う。
なお,「精神分析しないこと」という題目は私にはそぐわないので,「精神分析様の営為をしないこと」に変更したことをご了承願いたい。
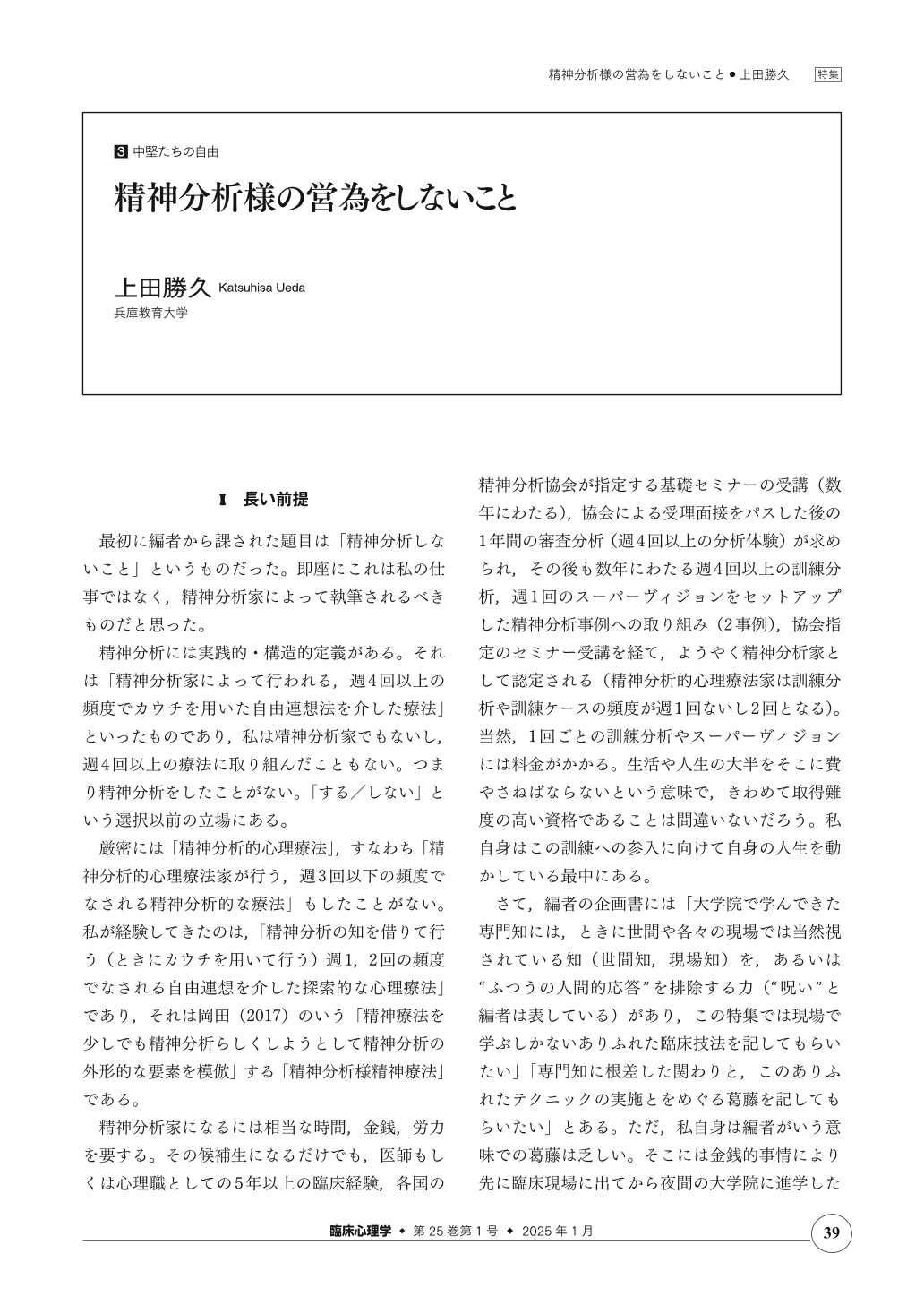
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


