目でみるシリーズ 画像でみる緑内障の病態
第24回 画像検査でみる近視緑内障眼 ~OCTA篇~
秋山 果穂
1
,
齋藤 瞳
2
1東京大学医学部眼科学教室
2東京大学医学部眼科学教室 講師
pp.1-6
発行日 2025年2月20日
Published Date 2025/2/20
DOI https://doi.org/10.34449/J0024.01.69_0001-0006
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
現在,近視人口の増加は世界的な問題となっており,2050年には強度近視の人口は約10億人に達すると予測されている1).近視は緑内障の最大のリスク因子として知られており,近年のメタアナリシスでは近視が1D強くなることで緑内障のリスクは約20%上昇し,-6Dを超えるとさらにリスクが高いことが報告されている2).近視の増加に伴い近視緑内障もさらなる増加が予想されるが,近視眼では眼軸延長に伴い視神経・網膜に多様な変化を生じており,検鏡的な緑内障の評価が難しいとされている.そこで,近視眼の緑内障評価においては光干渉断層計(OCT)をはじめとする画像検査による定量的評価が必須といっても過言ではないが,OCT検査で最もよく用いられる指標である乳頭周囲網膜神経線維層厚(cpRNFLT)を用いた評価にも課題が残り,非強度近視眼と比較して偽陽性・偽陰性を生じやすいことが知られている3).そこで,近年新たな緑内障評価ツールとして注目を集めているのが,光干渉断層血管撮影(OCTA)である.OCTAは従来網膜循環疾患の評価に活用されていたが,近年は緑内障性障害の評価における有用性が報告され,さらには眼軸延長に伴う構造変化の影響を受けづらい指標として,強度近視緑内障の評価における活用が期待されている4).本稿では,OCTAでの緑内障性障害の評価の捉え方を紹介し,通常のOCTとの比較を交えて近視眼におけるOCTA活用のポイントについて解説したいと思う.
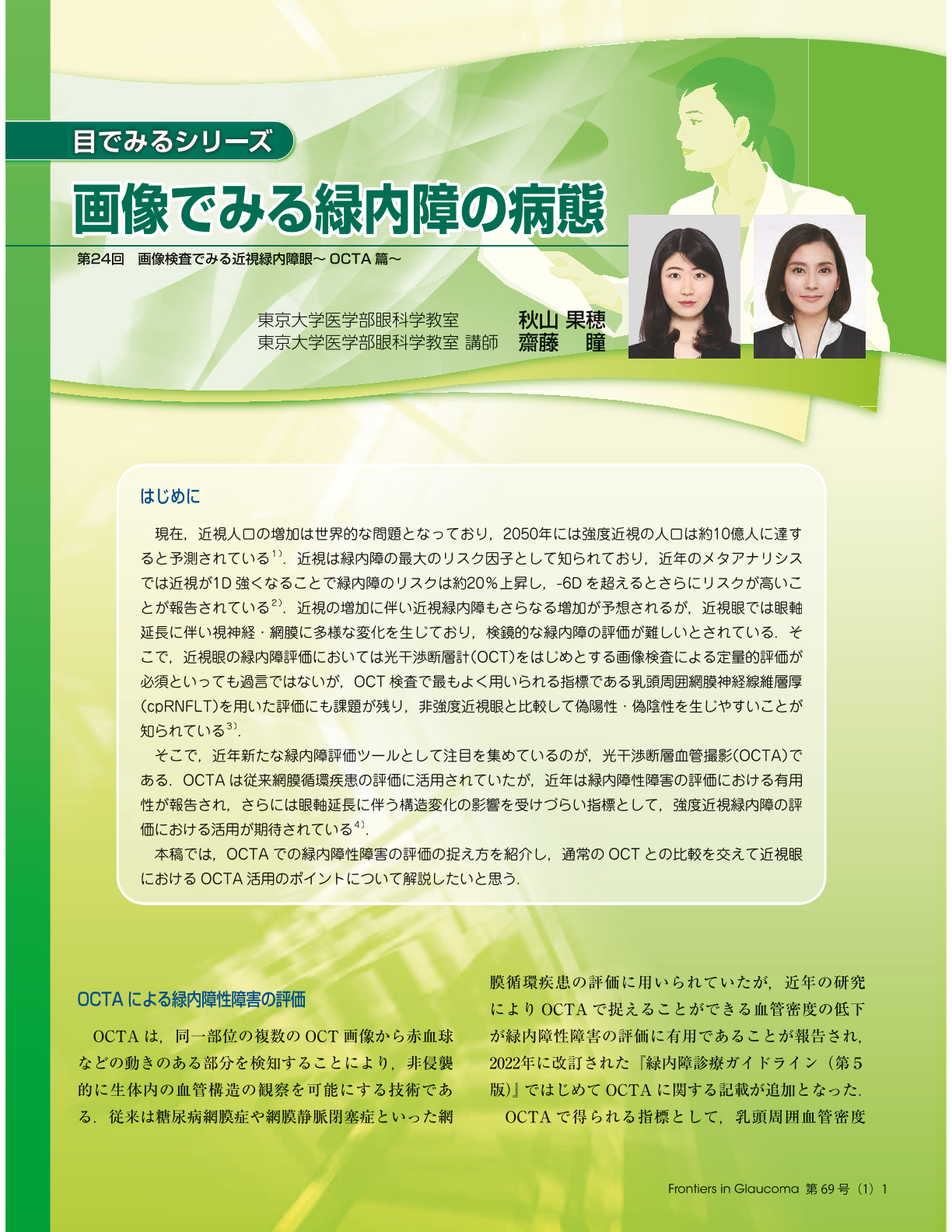
Medical Review Co., Ltd. All rights reserved.


