Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 What? 子どもの発達における視覚の関与は?(特に一定程度見えていると思われる子どもについて)
一定程度見えていると思われる子どもは,見えにくさにより発達の遅れや偏り,強いストレスを抱えやすい.情報の統合が困難で理解に時間を要し,空間認知の不正確さから物にぶつかる,運動や新環境への適応が難しい等の問題が生じる.また,他者の表情やジェスチャーを読み取りにくく,社会的関係構築に支障をきたすこともある.さらに,眼精疲労や精神的疲労により集中力低下や情緒不安定を招き,学習面でも文字や図表の理解に困難を伴う.そのため,残存視力を活かし発達を支援する視覚リハビリテーションは不可欠である.
Q2 Who? 視覚リハビリテーションを要する子どもはどのような特徴があるか?
視覚リハビリテーションを要する子どもは,低視力,視野狭窄,光順応障害,色覚異常,コントラスト感度低下,眼球運動や両眼視機能の異常等,多様な視機能の課題を抱え,日常生活や学習,社会性においても困難を伴う.具体的には,物にぶつかりやすい,探索行動が少ない,手元作業や身辺自立が難しい,読書・書字や屋外移動が困難といった行動特徴や,板書・教科書の読解困難,図形理解や集中力の低下,学習意欲の減退等がある.
Q3 When? Where? いつから,いつまで実施するのが適切か(時期と場所)?
視覚に異常が疑われた時点からできるだけ早期(乳幼児期)に開始し,発達段階に応じて内容を変えながら継続的に行う.終了時期は明確ではなく,ライフステージや環境の変化に応じて再評価・再介入を行い,本人が自立し生活の質を維持できるまで柔軟に対応する.実施場所は医療機関,療育・発達支援センター,特別支援学校,地域の学校,相談支援事業所,地域リハビリテーションセンター,家庭等多岐にわたり,関係機関が連携して個別の支援計画に基づき支援を行う.
Q4 How? どのように評価し,視覚リハビリテーションを行うべきか?
視覚リハビリテーションは,視機能・発達・環境等を多角的に評価し,個別最適化された支援計画に基づき実施する.評価では,眼科医や視能訓練士による詳細な視機能検査,日常生活での視覚利用状況を観察する機能的視覚評価,発達・心理評価,家庭や学校環境の把握を行う.その結果をもとに,多職種が連携して弱視治療や補助具の活用支援,感覚統合訓練,学習環境調整,保護者支援や環境調整等を行い,子どもの発達促進と生活の質向上を図る.
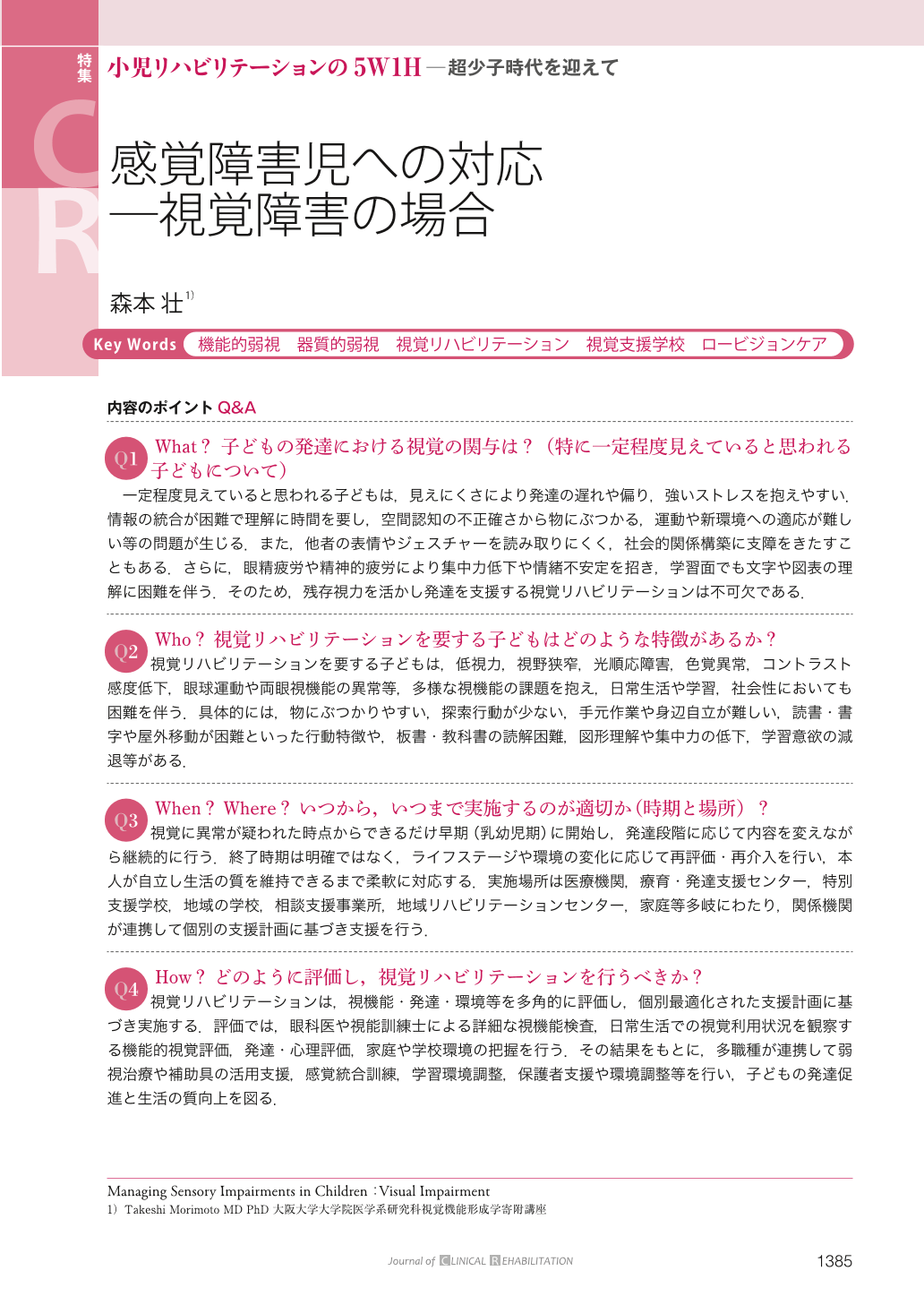
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


