- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
食事は生きるうえで欠かせない営みであるとともに,食べる楽しみや幸せなどを通じ,QOLに直結する日常生活動作です.しかし,摂食嚥下障害などさまざまな要因により,自分で食事を摂取することができず,他者に頼らざるをえない方も多く存在します.
ところが,食事介助の方法や技術によっては,誤嚥や窒息のリスクが増大したり,食事摂取量の減少につながったりすることもあり,さらに,食べる(飲み込む)力をもっているにもかかわらず,不適切な介助のために誤嚥性肺炎を起こしてしまうと,その後の経口摂取が制限されてしまうことも起こりえます.食事摂取量の減少によって栄養状態が悪化すると,嚥下機能や身体機能の低下を引き起こし,ひいてはQOLの低下につながるのです.
一方で,誤嚥のリスクが高い場合でも,嚥下機能に合わせた安全な食事介助を行うことで,誤嚥リスクを軽減し,経口摂取を維持することができるといわれています.食事介助によって,エネルギー・たんぱく質摂取量の増加,体重の増加,栄養状態の改善などの効果があると報告されており1-5),また,トレーニングを受けた介助者による食事介助では,安全性が高く,介助を受ける者の満足度も高くなることが報告されています4,6).
食事介助は単に食具で食べ物をすくい,口に入れるという動作をさすものではありません.食事をするための環境を整える,姿勢を調整し,食べ物への認識を高める,食べる力を引き出すようなスプーン操作,適切な一口量やペースでの提供を行う,などのさまざまな技の組み合わせです.安全に食事を行うことはもちろんのこと,食事を楽しむことも大切であり,介助される側が食べやすく,むせなどの苦しさがないことが求められます.食事介助に関する技術やトレーニングの質向上は,さらに加速する超高齢社会において誤嚥性肺炎を予防し,経口摂取を維持するうえで重要な課題です.しかし,いままでに食事介助技術やその評価に焦点を当てた研究はほとんどなく,食事介助技術を客観的に評価する指標はありませんでした.そこで,筆者を含む研究チームは「食事介助スキルスコア」を開発しました7).
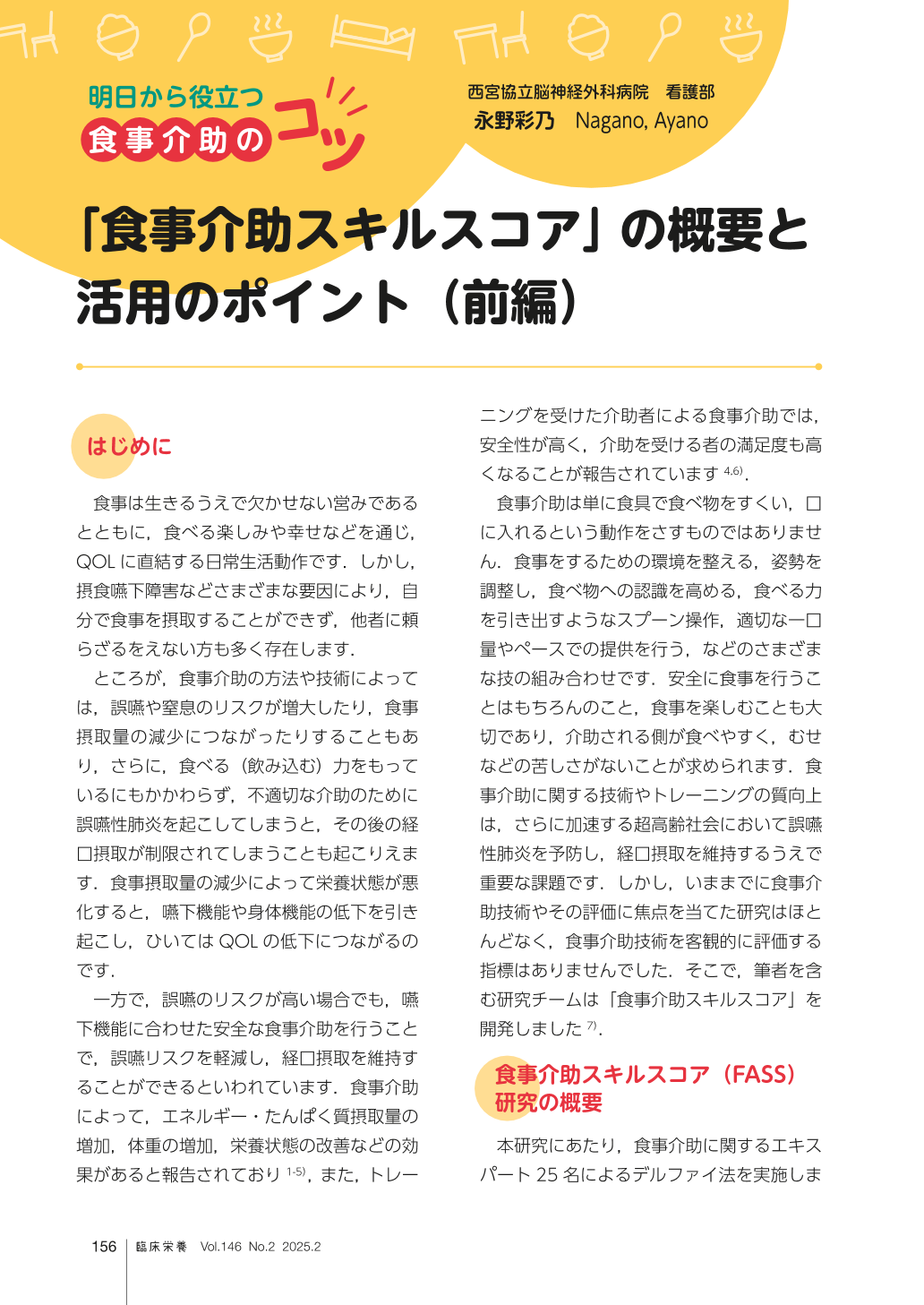
Copyright © 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All Rights Reserved.


