特集 医工・産学連携
消化管神経叢の新規生体蛍光観察
小池 勇樹
1
,
溝口 明
2
,
東 浩輝
1
,
佐藤 友紀
1
,
長野 由佳
1
,
松下 航平
1
,
問山 裕二
1
Yuhki Koike
1
,
Akira Mizoguchi
2
,
Koki Higashi
1
,
Yuki Sato
1
,
Yuka Nagano
1
,
Kohei Matsushita
1
,
Yuji Toiyama
1
1三重大学医学部附属病院消化管・小児外科
2三重大学個別化がん免疫治療学
pp.984-988
発行日 2025年9月25日
Published Date 2025/9/25
DOI https://doi.org/10.24479/ps.0000001318
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
「切除すべき部位」と「温存すべき部位」を術中に診断できるようになることは,外科医にとっても夢のような技術であるだけでなく,最適な切除ラインが術中に同定できれば,それは結果として患者にとって予後の改善や術後合併症の減少につながり,その臨床的恩恵は計り知れない。われわれはこれまで,生体組織の深部観察や長時間の動態解析に優れた多光子レーザー顕微鏡(multiphoton laser scanning microscopy:MPLSM)を用いた生体観察手法による研究を継続的に行ってきた。各種疾患モデルマウスを用い,生体内で生じる動的変化をリアルタイムに観察・解析することで,さまざまな病態に関する知見を報告してきた。最近では,新生児マウスの生体腸管固定法(世界初)を開発し,これを新生児壊死性腸炎モデルマウスに適応し,さまざまな新知見を解明した。さらに,本稿共著者である溝口らが発見したクルクミンを用いた生体蛍光染色法を組み合わせることで,通常は蛍光発色を持たないヒト組織に対する生体深部のリアルタイムイメージングを可能とする新規生体蛍光観察手法(curcumin vital staining-intravital fluorescent observation method:CVS-IFOM)を確立した。本稿では,これら技術の開発過程および現在進行中の医工産学連携による研究展開について概説する。
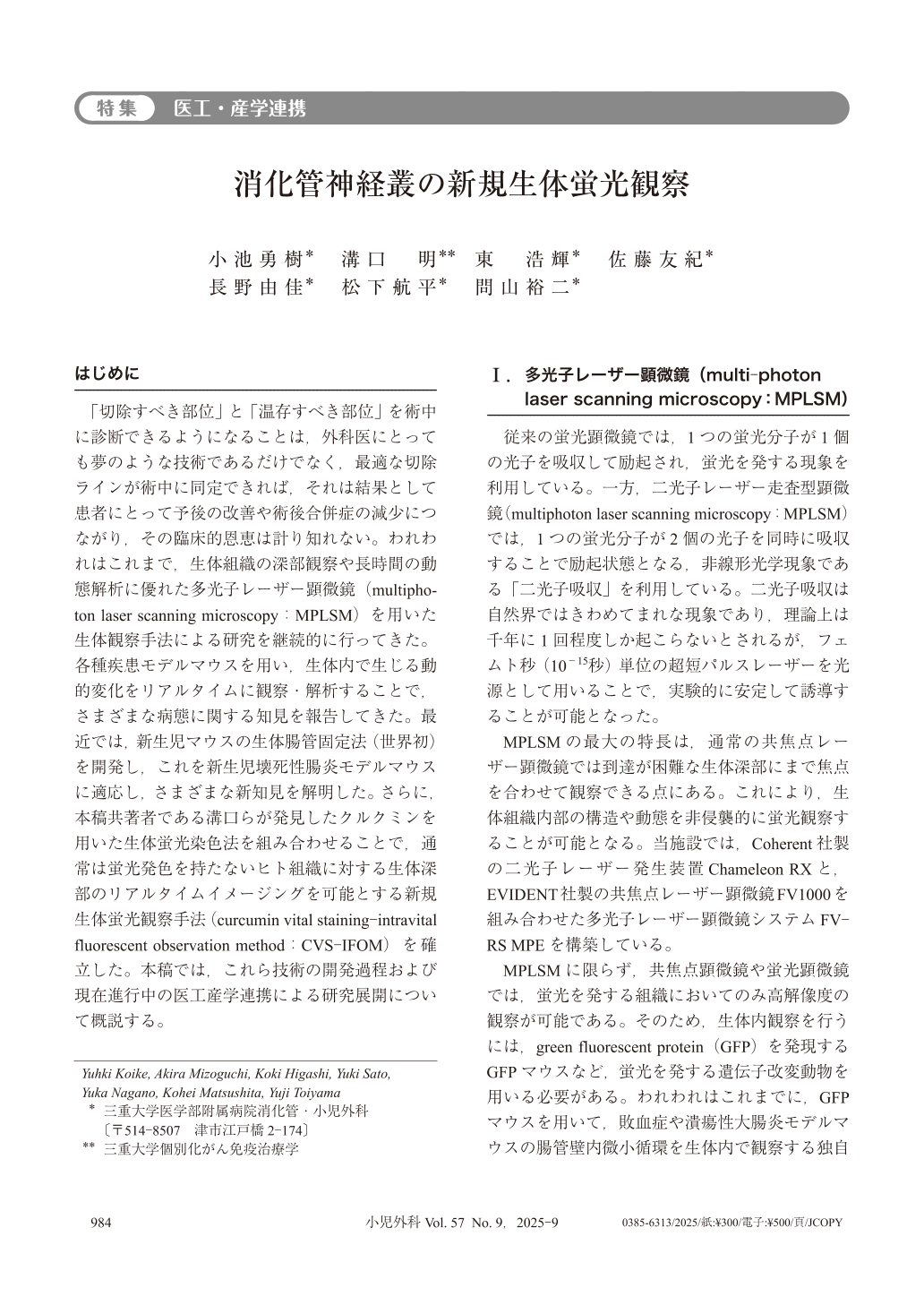
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


