- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
光干渉断層計(OCT)が眼科診療で使われるようになり早20年以上が経つ。タイムドメイン(TD)-OCTは2000年頃に本邦に導入され,主に網膜疾患において網膜断層像を視覚化する技術として広まった。緑内障分野では,筆者を含め少数の研究者がその臨床応用を行ってきたが,TD-OCTの最終機種であるツァイス社のStratus OCT 3000において正常眼データベースが導入されたことで,ようやく2010年頃にその有用性が認められた。さらにスペクトラルドメイン(SD)-OCTの登場により,高速かつ画質の高い画像を得られるようになり,本邦でも爆発的に広まった。今や一家に一台として,緑内障診療に欠かせない機器となったのは周知の事実である。以前のOCTはツァイス社製のみであったが,現在はハイデルベルグ社スペクトラリス,オプトビュー社solixに加え,日本製であるトプコン社の3D OCTシリーズ,ニデック社RSシリーズ,キヤノン社OCT-R1と多数の選択肢がある。また,波長掃引(スウェプトソース)方式のOCTが登場し,キヤノン社OCT-S1やトプコン社のDRI OCT Tritonが該当する。SS-OCTではより高侵達・広範囲の画像が撮像できようになったが,緑内障診療においてはSD-OCTと日常的使用感に大差はないと思われる1)。ソフトウェアにもいくつかアップデートがあり,OCTアンギオグラフィが注目されているが,他稿で詳細が述べられる。ほか,AIによるノイズ除去・網膜各層のセグメンテーションといった機能が最新の機種では備わるようになった。また,トラッキング機能によりまばたきや固視不良の影響の低減が可能になり,患者にとっても検査側にとってもよりユーザーフレンドリーなものとなりつつある。スキャンスピードはTD-OCTでは1秒あたり400枚程度だったものが,SD-OCTでは数万枚となり,ついにはニデック社の最新OCTであるGlauvasで毎秒25万枚に到達した。このようにハードウェア・ソフトウェアともに年々進化をしているが,臨床現場での緑内障診療における後眼部OCTの使用法は10年以上前のSD-OCTの登場以来,ほぼ変化がないように筆者は感じており,増え続ける膨大なデータを医師側が使いこなせていないのではないかと思う。OCTによる緑内障診断に関して基本的な診るべきポイントや注意点には残念ながら近年にアップデートはあまりなく,本誌の65巻(2023年)10月号に詳しく述べられている2)ので割愛する。本稿では他稿には掲載されてこなかったOCTの効果的な活用法とOCTを用いた緑内障進行判定について日常診療の目線から述べる。
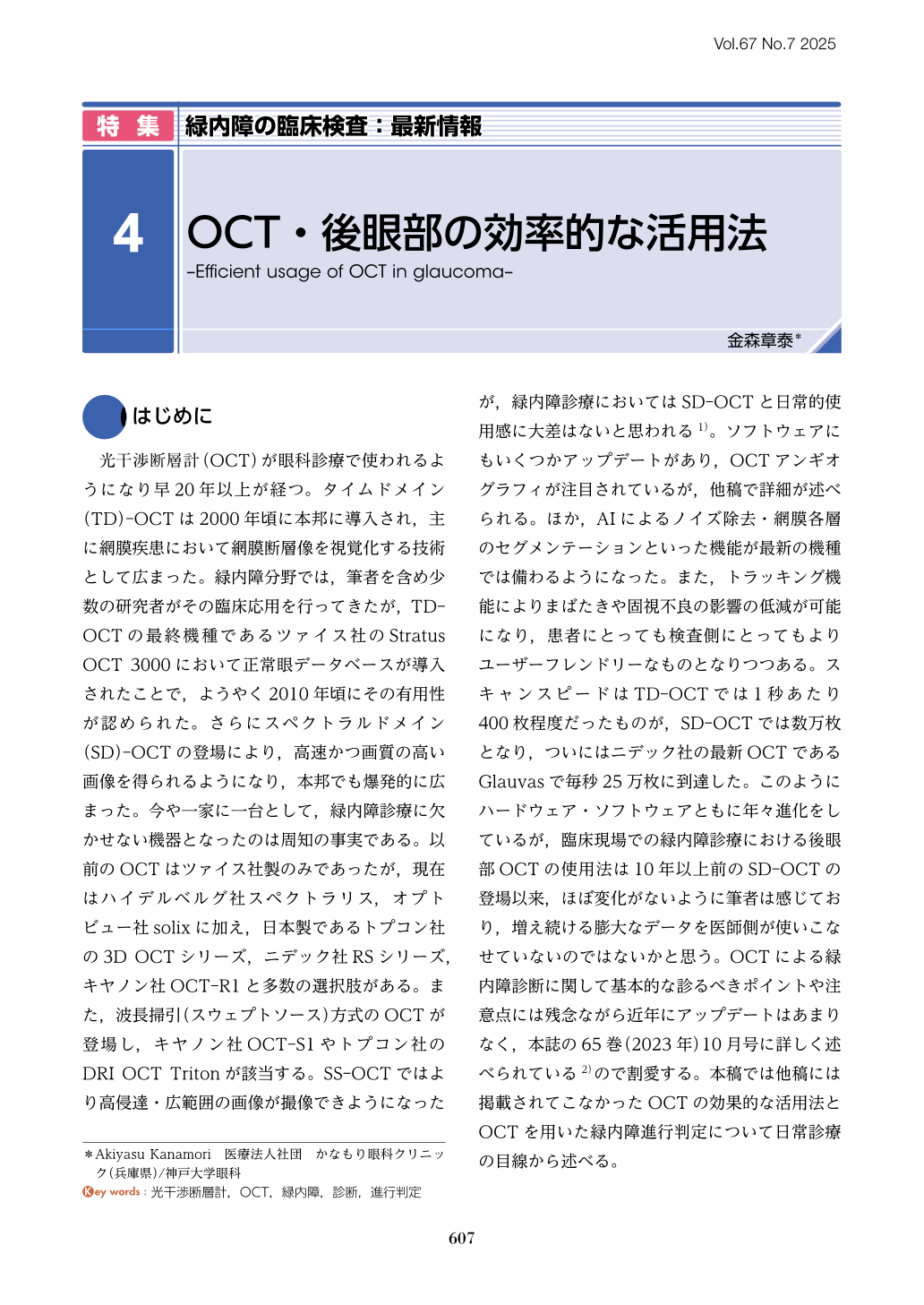
Copyright © 2025, KANEHARA SHUPPAN Co.LTD. All rights reserved.


