特集 患者の思いを引き出して支え,力を高める意思決定支援
意思決定支援ガイドラインの解説と臨床現場での活用方法
小川 朝生
1
Asao OGAWA
1
1国立がん研究センター東病院精神腫瘍科
pp.146-150
発行日 2025年3月1日
Published Date 2025/3/1
DOI https://doi.org/10.15106/j_kango30_146
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
- サイト内被引用
はじめに
がん医療の発展により,治療の選択肢は飛躍的に増えてきている.一方で,治療効果や有害事象もさまざまになり,どの選択肢を選ぶのが望ましいのか,判断も複雑になってきた.また,医療を含めた社会全般において,意思決定のあり方も変わろうとしている.その背景には2014年にわが国が障害者権利条約を批准したことがある.
従来,精神や知的な障害をもつ人の意思決定の場面では,「本人が決められないのならば,決められる人が本人の代わりに『良かれと思って』決める.それが結局は本人のためなのだ」という保護的な対応が行われてきた(代理代行).しかし,周囲の人がたとえ良かれと思ったとしても,本人の意向をすべてくむことは困難である.本人の真意を活かすためには,本人が自ら決めることが重要であり,そのためにも本人が決めることができるような支援を重視する方向に転換してきている.実際に,いま議論されている意思決定支援は,英語ではsupported decision making(支援付きの意思決定)である.このことからも本人の自己決定を重視していることが理解されよう.
意思決定支援を実践するうえで,わが国が公開したガイドラインを知ることは重要である.しかし一方で,複数のガイドラインが作成されているうえ,その相互関係がわかりにくく,実践につなげにくいとの悩みも聞かれる.ここでは,わが国が意思決定支援に関連して策定したガイドラインの背景とその相互関係,個々の活用方法を紹介したい.
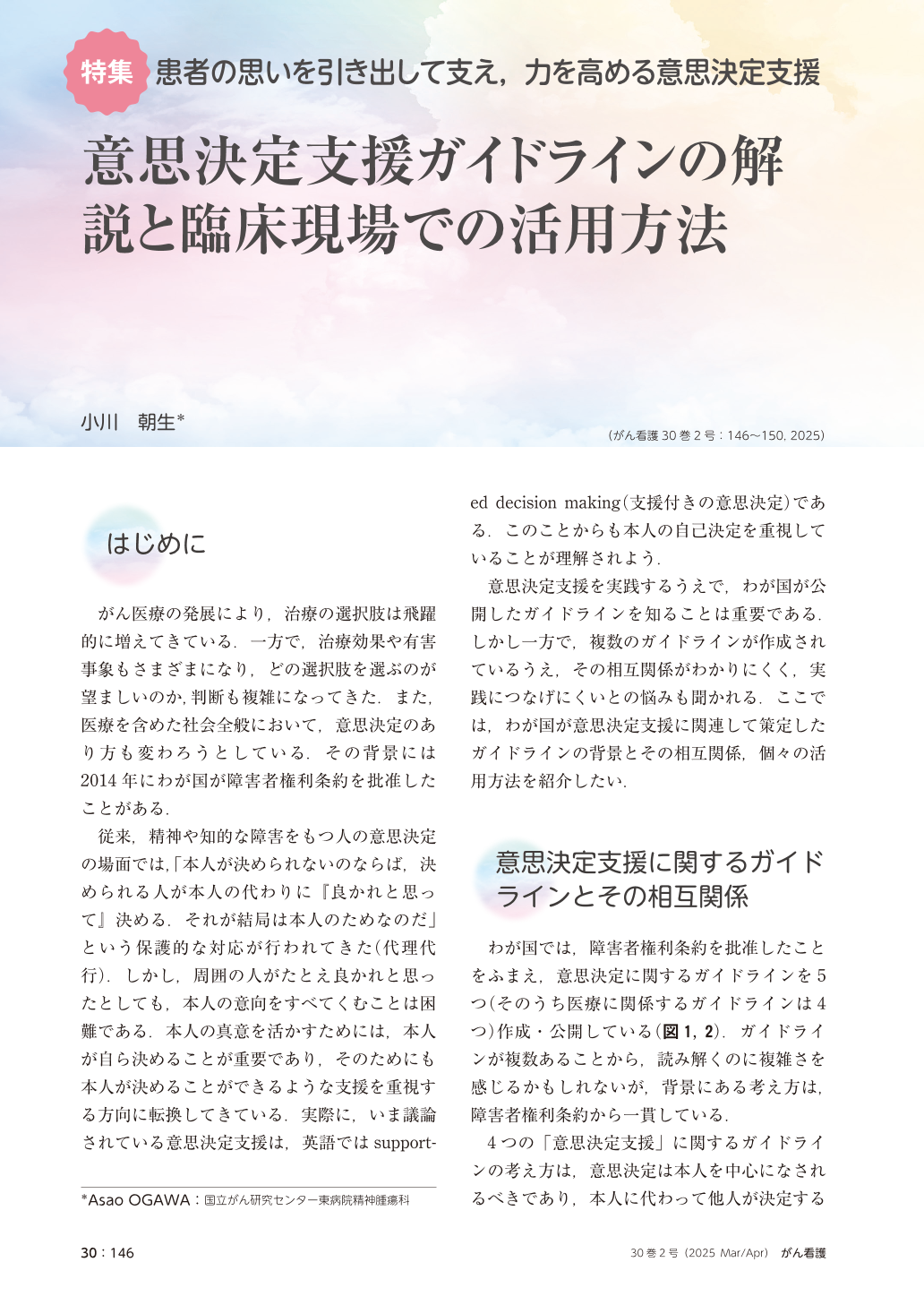
© Nankodo Co., Ltd., 2025


