- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
がん医療の発展により治療の選択肢は増え,また複雑化しています.がん治療の多くは結果が不確実であり,メリットだけでなく,副作用などのデメリットも伴います.どの治療を選択するかによって,その後のQOLが大きく変わることもあるため,患者本人や家族等が,疾患や治療,生活への影響などについての情報をよく理解し,納得して意思決定することは重要と言えます.
近年,インターネットなどで医療情報はすぐに入手できますが,がんによる不安や動揺がある中で,患者が氾濫している情報から正しいあるいは自分にとって適切な情報を選択し,読み解き,整理し,自分の状況に照らし合わせて意思決定に役立てるということは,よりいっそうむずかしくなってきていると思われます.
また,意思決定においては,従来日本人に多いと言われていたパターナリズムから脱却し,本人の価値観を尊重することが強調されるようになってきました.「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」や診療報酬でも,意思決定支援を提供できる体制の整備や,適切な意思決定支援に関する指針を定めるよう記載されています.しかし,自分の価値観を明確にし,医療者にそれを伝えて話し合える患者はまだ多くはなく,支援体制についても十分整っているとはまだまだ言えない状況ではないでしょうか.
さらに,2人に1人ががんにかかる時代,意思決定が困難な人々もがんにかかり,なんらかの決定をしなければならない状況も増加しています.近年では,意思決定に関するガイドラインが複数作成されており,意思決定がむずかしく思われる人であっても,本人のこれまでの人生観や価値観,どのような生き方を望むかなどについてできる限り把握し,その人にとっての最善を探る支援が求められていますが,実際に行うのは容易なことではありません.
本特集では,意思決定に関する知識や情報を整理するとともに,意思決定にかかわる患者の力を補い高めるにはどうすればいいのか,また,意思表示や決定が困難な患者の価値観や推定意思を引き出して,少しでも患者の希望に近い決定となるようにするためには,どのように考えかかわっていくとよいのかについて,知識や事例を通した実践内容を提示しています.
本特集が,がん患者や家族の意思決定にかかわる看護師の方々にとって,支援が必要な患者・家族,そして自分たちが行う支援内容や体制について改めて考え,取り組みを進めていくきっかけとなることを期待しています.
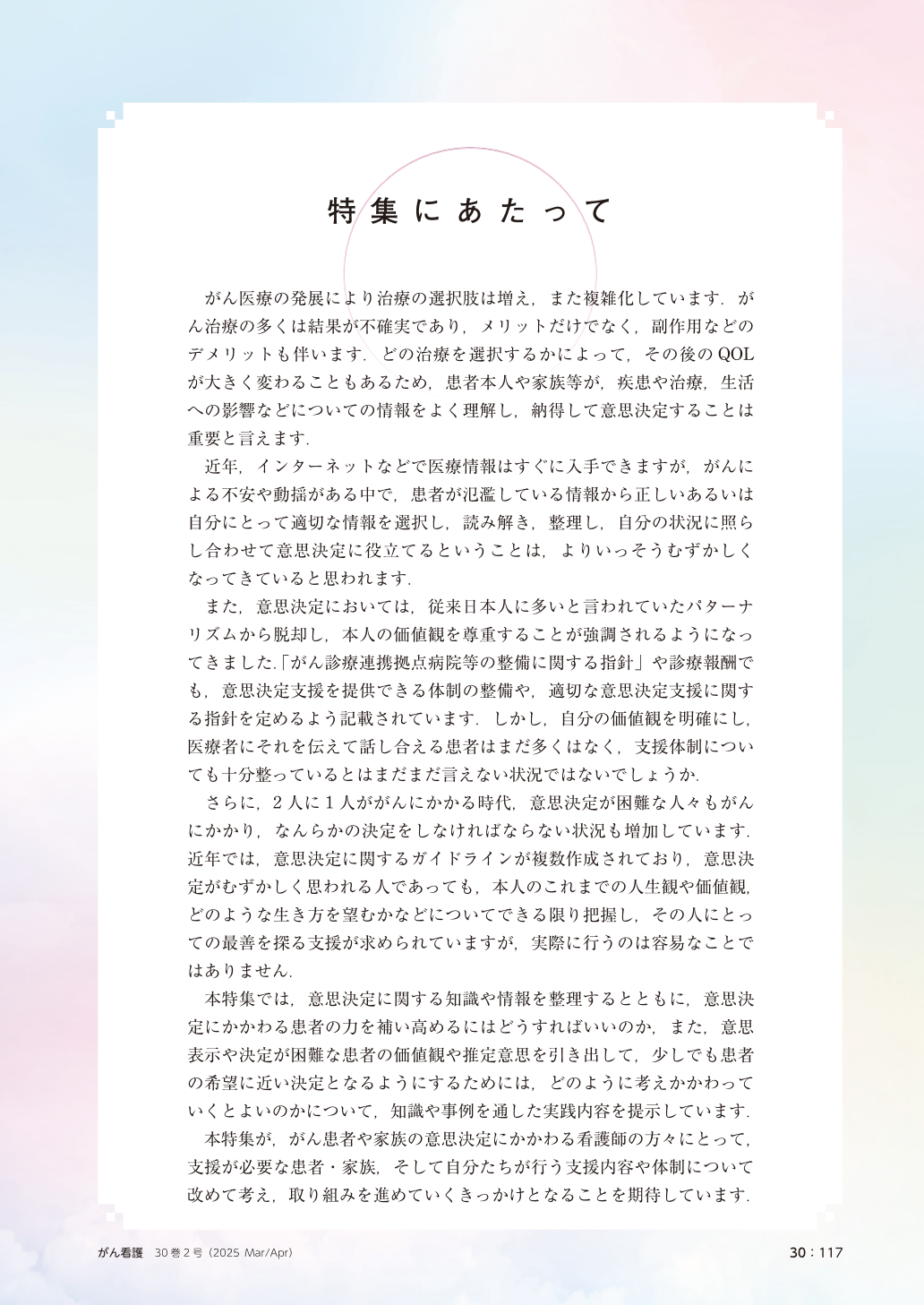
© Nankodo Co., Ltd., 2025


