変革する心房細動診療とその実践up-to-date
心房細動を管理する 脈の不整を治すべきか、受容すべきか? リズム管理の意義はどこにあるのか?
奥山 裕司
1
1大阪府立病院機構大阪府立急性期総合医療センター 心臓内科
キーワード:
医療費
,
抗不整脈剤
,
心拍数
,
心房細動
,
洞結節
,
臨床試験
,
多施設共同研究
,
洞性調律
Keyword:
Anti-Arrhythmia Agents
,
Atrial Fibrillation
,
Clinical Trials as Topic
,
Health Expenditures
,
Heart Rate
,
Sinoatrial Node
,
Multicenter Studies as Topic
pp.451-454
発行日 2008年3月1日
Published Date 2008/3/1
DOI https://doi.org/10.15106/J00974.2008149302
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
本邦の心房細動患者の生命予後はもともと良好であることから、薬物治療などに伴う副作用を最大限回避しつつ、症状の改善を目指すことが重要である。現在の洞調律維持治療で自覚症状や運動能、ある程度の左心機能の改善は期待できるが、生命予後の改善が得られるとの明確な証拠はない。抗不整脈薬の催不整脈作用・心機能低下作用については、常に注意を払う必要がある。洞調律維持治療と心拍数調節治療とのあいだには、明確な生命予後についての差はなく、いたずらに洞調律維持治療にこだわる必要はない。若年の孤立性心房細動では症状が強いことが多く、まずは洞調律維持治療を選択する。治療方針に迷う場合は洞調律維持治療ではなく、心拍数調節治療を選択するほうが無難であろう。
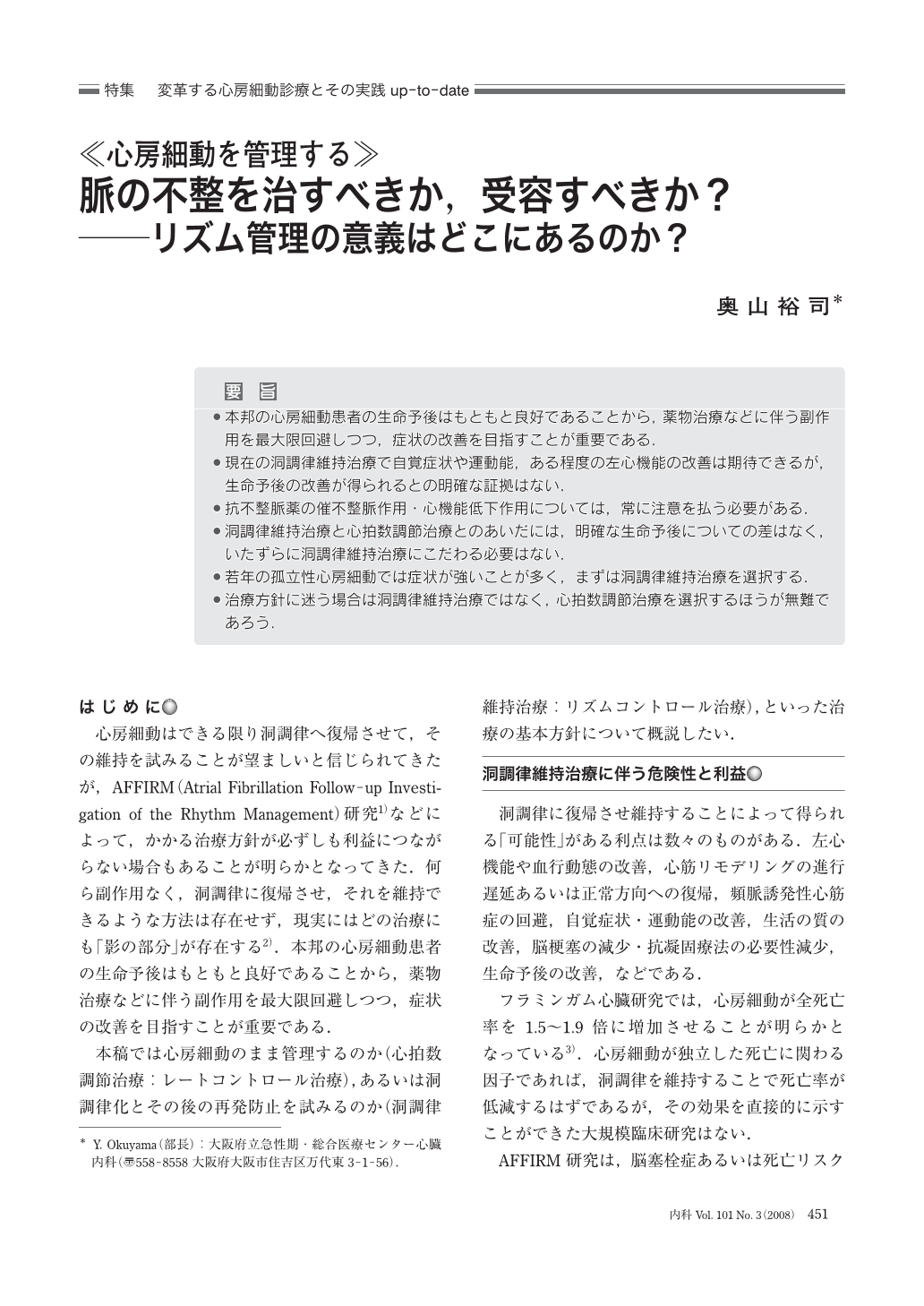
©Nankodo Co., Ltd., 2008


